
ボイスボットとデコールCC.CRMの連携によって、電話対応の手間や情報共有の遅れといった従来の課題がどう変わったのでしょうか?
現場のリアルな声をもとに、導入の背景から運用、実際の効果まで詳しく掘り下げます。
【関連記事】そのお悩み、AI搭載型CRMで解決できます!コールセンターへのAI導入の課題とは
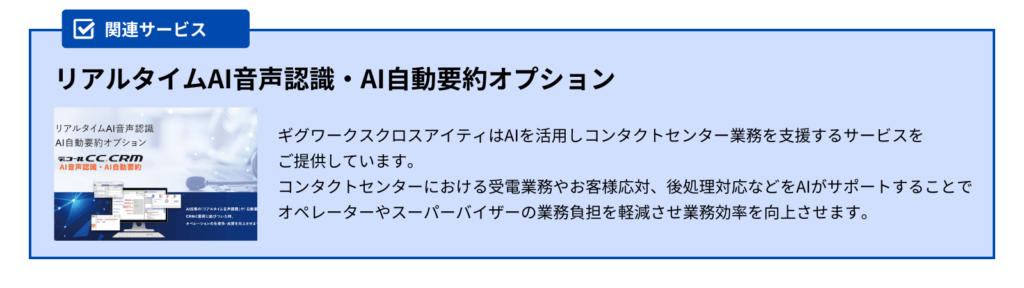
2025年最新版!ボイスボットと関連技術
人手不足や顧客対応の高度化を背景に、ボイスボット市場は今、大きな変革期を迎えています。ここでは、国内市場の最新動向、注目の技術トレンド、そして主要なボイスボットサービスを紹介します。
市場拡大とその背景
コールセンターやカスタマーサポートの現場では深刻な人手不足が続き、業務効率化やコスト削減のためボイスボット導入が急増しています。現在、ボイスボット市場は高い成長率を維持し、今後数年でさらに拡大が見込まれています。従来はオペレーターが対応していた一次受付や定型的な問い合わせを自動化することで、企業は人的リソースをより重要な業務に集中できるようになりました。近年は、低価格帯の用途特化型製品も増加し、業種や規模を問わず幅広い現場で活用が進んでいます。今後は、高度な問い合わせに対応できる高機能型と、特定業務に特化した低価格型の二極化が一層進むと予想されています。自治体での災害情報通知やサービス業での予約受付・リマインドなど、用途の多様化も市場拡大を後押ししています。
生成AIとマルチモーダルAIの進化
マルチモーダルAIとは、音声・テキスト・画像・動画など複数の異なる情報(モダリティ)を同時に処理・統合できるAI技術です。従来のボイスボットは音声やテキストなど単一データのみを扱っていましたが、マルチモーダルAIの導入により、今後は「音声+画像」や「音声+テキスト+動画」など複数の情報を組み合わせた対話が実現します。たとえば、ユーザーが電話で問い合わせをする際に音声だけでなく画像や書類も同時にAIが解析し、より正確な回答や案内ができるようになります。これにより、ボイスボットは「聞く・話す」だけでなく「見る・読む・理解する」ことも可能となり、人間に近い多角的なサポートが実現します。今後は生成AIの誤情報対策や、シナリオ型と生成AIを組み合わせたハイブリッド運用が主流となり、社外利用も拡大が期待されます。こうした技術革新が、企業の競争力や顧客体験(CX)の質を大きく左右する時代となっています。
主要なボイスボットサービス
AI Messenger Voicebot
AI Messenger Voicebotは、FAQ自動応答や複雑な業務フロー対応に強みを持つ国産ボイスボットです。特徴は、AI Shift独自の自然言語処理技術と、現場ごとに最適化できる柔軟なカスタマイズ性。導入後も専任チームが継続サポートし、運用改善やデータ分析まで一貫して支援します。
CAT.AI CX-Bot
CAT.AI CX-Botは、ノーコードで音声シナリオを構築できる点が特長。FAQやチャットボットとの連携が簡単で、既存の業務システムとも柔軟に連携可能です。運用のしやすさと拡張性が高く、複雑な業務プロセスにも対応します。
LINE WORKS AiCall
LINE WORKS AiCallは、LINE WORKSとの連携による電話とLINEのシームレスな連携が最大の特徴。電話からLINEへの自動誘導や、LINE上での予約・問い合わせ対応が可能で、LINEユーザーとの親和性を生かした顧客体験を実現します。
MOBI VOICE
MOBI VOICEは、業務担当者自身がシナリオ作成・編集できる「ノーコード運用」と、多言語対応が強み。ダッシュボードでの通話分析や、コールセンター業務の細やかなカスタマイズが可能です。
commubo
commuboは、日本語の自然な対話に特化したAIエンジンを搭載。リアルタイム応答の速さや、複数拠点・複数番号の一元管理など、現場の運用負荷を大きく下げる設計が特徴です。
PKSHA Voicebot
PKSHA Voicebotは、日本語認識の精度と、業界ごとのテンプレートが豊富な点が強み。ノーコードで複雑な対話フローを構築でき、外部システム連携やSMS通知など多様な業務に対応します。
関連技術の最新トレンド

ボイスボット分野では、2025年現在、AI技術の進化がサービスの根本的な質を大きく変えつつあります。ここでは、実際の業務現場や顧客体験を変革する主要な技術トレンドについて詳しく解説します。
大規模言語モデル(LLM)の活用
GPT-4、Llama 3、Claude 3などの大規模言語モデル(LLM)は、ボイスボットの会話能力を飛躍的に向上させています。
2025年上半期にはOpenAI「oシリーズ」、Google「Gemini 2.5」、Anthropic「Claude Opus 4」など、各社から新モデルが続々登場し、推論能力や文脈理解、専門知識の活用力が大幅に強化されました。これにより、ボイスボットは長文のやりとりや複雑な質問、曖昧な要求にも柔軟に対応できるようになっています。さらに、企業独自の業務知識や用語に合わせたカスタマイズも容易になり、現場ごとのニーズに即した会話体験を実現しています。
マルチモーダルAIの進化
マルチモーダルAIとは、音声・テキスト・画像・動画など複数の異なる情報(モダリティ)を同時に理解・生成できるAI技術です。
従来のボイスボットは音声やテキストなど単一の情報しか扱えませんでしたが、最新のマルチモーダルAIは、例えば「音声+画像」や「音声+動画」など複数の情報を組み合わせた対話が可能になっています。
小売業界では、顧客が商品画像を送信しながら音声で質問できるサポートが実現し、医療現場では診療記録・画像・音声を統合的に解析することで診断精度が向上しています。教育や建設、製造など多様な分野でも、現場の映像や記録データをAIがリアルタイムで解析し、最適な対応やアドバイスを提供する事例が増えています。
RAG(検索拡張生成)の活用
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、AIが企業独自のナレッジベースやFAQデータと連携し、より正確で実用的な回答を生成する技術です。
従来の生成AIは学習済みデータの範囲でしか応答できませんでしたが、RAGを活用することで、リアルタイムで社内文書やマニュアル、最新のFAQから必要な情報を検索し、その内容を反映した応答が可能となります。
これにより、社内ヘルプデスクや顧客サポートの自動化が進み、業務効率化とサービス品質向上の両立が現実のものとなっています。
フルデュプレックス音声対話AI
フルデュプレックス音声対話AIは、人間同士の会話のように「話す」と「聞く」を同時進行できる技術です。
従来のAIはユーザーの発話が終わるまで応答できませんでしたが、J-MoshiやMoshi、ChatGPTアドバンスドボイスモードなどの最新モデルでは、相手の話を聞きながら割り込みや相槌ができるため、会話のテンポや自然さが大幅に向上しています。
この技術は、接客やリモート会議、医療相談など「人間らしいやりとり」が求められる場面での活用が広がっています。
生成AIによる音声認識・応答技術の進化
生成AIの導入により、音声認識や回答生成の精度が飛躍的に向上し、曖昧な質問や文脈の変化にも柔軟に対応できるようになりました。
OpenAIの新モデルやWhisper v3などの音声認識AIは、騒がしい環境や多様な話し方にも対応し、正確な文字起こしと応答生成を実現しています。
また、音声をテキスト化せずそのまま解析・応答できる技術も進化し、会話のスムーズさやリアルタイム性が格段に向上しています。
感情・話し方の解析と自然な音声生成
話し手の感情や話し方をAIが読み取り、声のトーンやスピード、うなずきや息遣いまで再現することで、ユーザー体験がより自然になっています。
2025年の音声生成AIは、単なる機械的な読み上げを超え、喜怒哀楽や抑揚、間の取り方まで表現可能となりました。
これにより、顧客サポートやナレーション、医療・教育現場などで「人間らしいコミュニケーション」の実現が進んでいます。
AIエージェントの進化と今後の展望
AIエージェントは、単なる自動応答から“自律的な業務遂行”へと進化しています。
複数のタスクを同時にこなし、状況に応じて最適な判断や提案を行う「対話型AIエージェント」が、今後のボイスボット活用の中心になると見込まれています。
AIが人間のパートナーとして業務を補助し、より複雑な課題解決や意思決定支援を担う時代が到来しつつあります。
これらの技術革新によって、ボイスボットは「単なる自動応答」から「人間に近い高度な対話パートナー」へと進化しています。今後も、AIと人間の協働による新しい顧客体験や業務プロセスの創出が期待されています。
ボイスボットとCRMの連携
ボイスボットとCRM(顧客関係管理)システムの連携は、カスタマーサクセスの実現において不可欠な要素となっています。ここでは、ボイスボットとCRMの連携の仕組みと効果について紹介します。
連携の価値と仕組み
ボイスボットとCRMが連携すると、顧客との対話内容や応対履歴がリアルタイムでCRMに自動記録されます。これにより、オペレーターへのスムーズな引き継ぎや、過去のやり取りを踏まえた最適な対応が可能になります。たとえば、顧客がボイスボットで問い合わせを行った後、追加対応が必要な場合には、その内容が即座にCRMに反映され、担当者は履歴をもとに迅速かつ的確な対応ができます。
また、CRMに蓄積された顧客属性や購買履歴、過去の問い合わせデータをボイスボットが参照することで、よりパーソナライズされた応答や提案が実現します。たとえば、契約内容の確認やサービス変更の相談時に、顧客ごとの情報をもとに最適な案内を自動で行うことができます。
具体的な導入効果
- 対応品質の均一化:ボイスボットがCRMの情報をもとに標準化された応答を行うことで、担当者ごとの対応品質のばらつきを抑制できます。
- 業務効率化とコスト削減:顧客対応の一部をボイスボットが担うことで、オペレーターの負担軽減と人件費削減を実現。応対履歴の自動記録や要約保存により、後処理作業(ACW)も大幅に短縮されます。
- 顧客満足度の向上:24時間365日対応や、過去のやり取りを踏まえたスムーズな案内が可能となり、顧客の利便性と満足度が向上します。
- データ活用による継続的改善:ボイスボットとCRMの連携で蓄積された大量の対話データを分析し、FAQやシナリオの改善、新サービスの開発などに活用できます。
技術的なポイントと今後の展望
近年はAPIやWebhookを活用したリアルタイム連携が主流となり、複雑なシステム間連携も標準化が進んでいます。さらに、生成AIの進化により、曖昧な問い合わせや複雑な文脈にも柔軟に対応できるボイスボットが増加しています。感情分析や音声合成技術の進歩により、話し手の感情やトーン、話し方の特徴をCRMに記録し、活用できるようになっています。
今後は、CRM上の顧客情報や分析結果をもとに、AIが自律的にシナリオ改善やプロアクティブな提案を行う「エージェント型ボイスボット」の普及が期待されています。
また、複数チャネル(電話・チャット・メール・SNS等)での顧客接点データを統合管理し、全チャネル横断で一貫した顧客体験を提供する「オムニチャネルCRM」との連携も進むでしょう。
デコールCC.CRMのご紹介
ギグワークスクロスアイティが提供する「デコールCC.CRM」は、ボイスボット連携に最適化された次世代CRMプラットフォームです。
- 主要ボイスボットとの連携:AI Messenger Voicebotなど主要ボイスボットと連携可能です。
- 生成AIによる自動分析・改善提案:対話データを自動でVOC分析し、顧客の不満やニーズを可視化。シナリオやFAQの改善提案もAIがサポートします。
- 業界特化型テンプレートを標準装備:医療・金融・小売など18業種向けに最適化されたワークフローを用意し、初期設定の手間を大幅に削減します。
デコールCC.CRMは、ボイスボットとCRMの「連携」を超え、業務全体のDXを実現するための基盤です。詳しい資料請求やデモのご相談は、ギグワークスクロスアイティまでお問い合わせください。
ボイスボットの今後の展望

2025年のボイスボット市場は、生成AIやマルチモーダルAI、大規模言語モデルの進化により、従来の自動応答システムから“人に近い対話パートナー”へと大きく進化しています。業務効率化やコスト削減だけでなく、顧客ごとの最適な対応やパーソナライズが実現し、企業の競争力強化にも直結しています。今後は、CRMとの連携やAIエージェントの活用がさらに進み、データ活用や顧客体験の高度化が加速するでしょう。ボイスボットは、単なる自動化ツールを超え、企業と顧客をつなぐ新たな基盤として、ますます重要性を増していくと考えられます。






