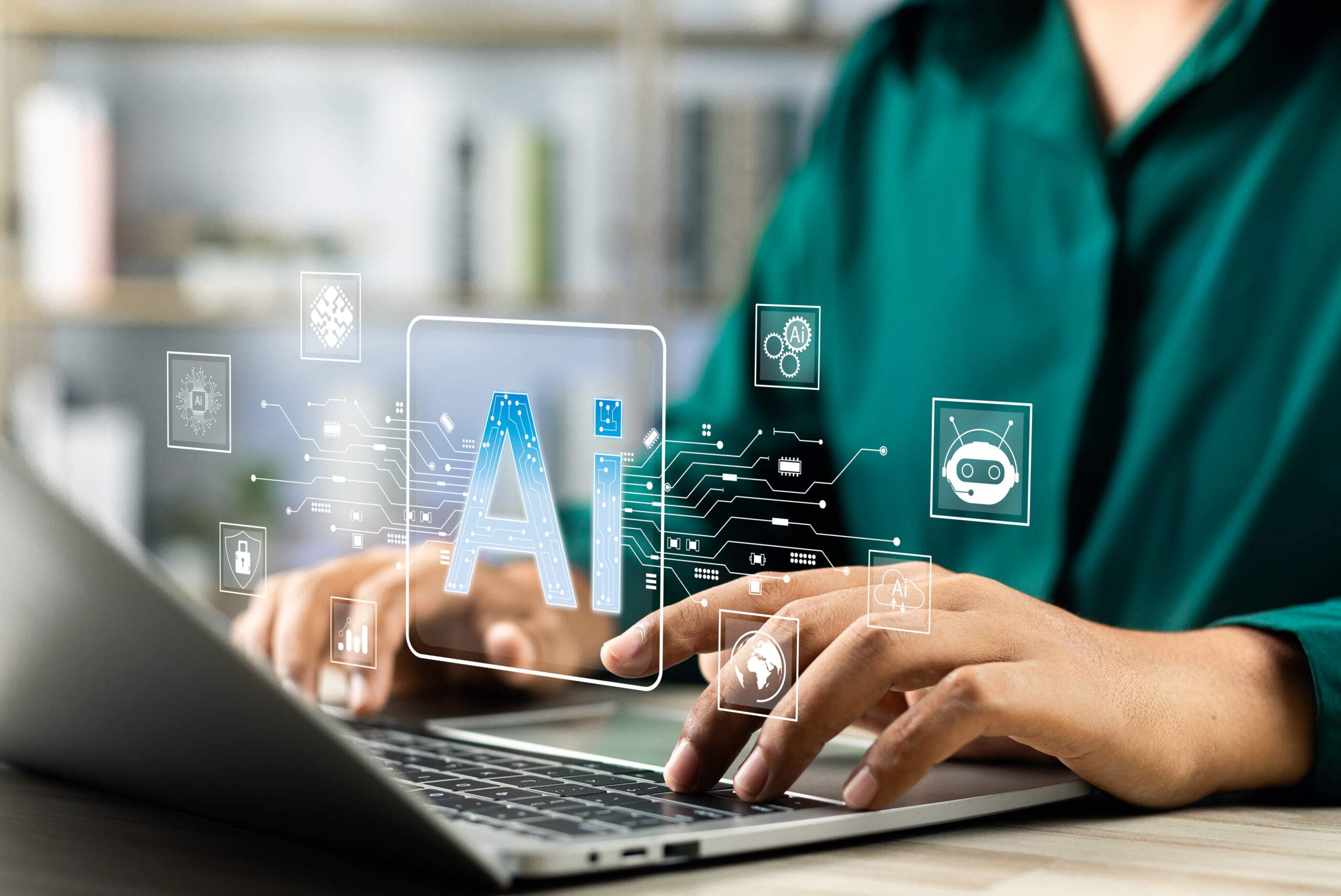近年、生成AIと著作権を巡る問題が世界各国で同時並行的に浮上しています。文章や画像を自在に生み出すChatGPTやStable Diffusionのような生成AIは、創作活動や産業のあり方を大きく変える一方で、著作物の無断利用や生成物の権利保護といった法的課題を引き起こしています。米国ではアーティストや出版社による大規模訴訟が進み、EUは透明性確保を義務づけるAI法を施行しました。さらに日本でも2025年、主要新聞社が米国の生成AI企業を提訴するなど、問題は国内に波及しています。本記事では、生成AIと著作権を巡る基本的な論点から最新の国際係争までを整理し、現状と今後の展望を解説します。
【関連記事】GPT-5はいつ登場?OpenAIの最新AIモデルとは

生成AIと著作権を巡る係争
生成AIの急速な発展に伴い、著作権を巡る問題が世界的に注目されています。特に、AIが学習に使用する著作物の権利関係や、AIが生成するコンテンツの著作権帰属が大きな争点となっています。
米国カリフォルニア州の集団訴訟(2024年8月)
2024年8月、著名アーティストらが「Stable Diffusion」「Midjourney」などの画像生成AI開発企業に対して集団訴訟を提起しました。原告は、自らの作品が無断で学習データとして取り込まれたと主張。
裁判所は予備的判断で、著作権で保護された作品が無断利用されている場合、開発企業に法的責任を問える可能性があると認め、損害賠償やサービス停止に発展するリスクを明確にしました。
さらに同年末には、米国の複数出版社がOpenAIを相手取って訴訟を起こし、記事が無断でChatGPTの学習に使われていると主張する動きも生じ、訴訟は拡大の様相を見せています。
欧州連合(EU)の法制度動向(2024~2025年)
EUでは2024年12月にAI法(AI Act)が成立。高リスクAIの規制に加え、著作権保護された学習データの透明性開示を義務化する条項が盛り込まれました。
これにより、生成AI開発企業は「どのコンテンツを学習に使ったか」を明示する必要があり、著作権者への対価請求やライセンス交渉の動きが広がると予測されています。
また2025年前半には、著作権者団体と生成AI企業の間で、音楽・映像作品の利用料を巡る交渉が本格化し、Spotifyや主要レーベルともライセンス交渉が進展するなど、デジタル音楽配信に類似した市場モデルの形成が注目されています。
米国著作権局の報告書(2025年2月)
2025年2月、米国著作権局は報告書を公表し、次のように整理しました。
- AI単独で生成された作品には著作権が認められない
- 人間の創作的関与があれば著作権保護の対象となり得る
- 特に、詳細で創造的なプロンプトは著作権保護の対象になる可能性がある
この指針は各国の裁判や政策形成にも影響を与えており、生成AIを利用するクリエイターがどの段階で著作権を主張できるかという議論に直結しています。
新聞社とPerplexityの係争(2025年8月、日本)
2025年8月、読売新聞社が米国の生成AI検索・要約サービス企業 Perplexity AI を相手取り、約22億円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。
続いて、朝日新聞社と日本経済新聞社も同様に、著作権侵害および不正競争行為を理由に44億円の損害賠償を請求しています。
主な争点
- 記事の無断利用:新聞社が執筆・配信した記事が、無断で複製・保存され、AIの回答に使われている。
- アクセス遮断の無視:「robots.txt」など情報収集拒否の指示を無視し、クローリングを継続。
- 有料記事の利用:有料会員向けや提携先媒体の記事が許可なく使用されている。
- 誤情報による信用失墜:AIの誤回答によって新聞社の信頼が損なわれ、不正競争防止法違反の可能性がある。
新聞社側の主張・要求
- 著作物の無断利用差止め
- 保存データの削除
- 誤情報の送信差止め
- 損害賠償(読売:約22億円、朝日・日経:計44億円)
近年、生成AIと著作権を巡る問題がグローバル規模で同時並行的に発生しています。これらの動きはいずれも、著作物の利用方法や権利者への対価、誤情報に対する責任の所在といった課題を浮き彫りにしており、生成AIの発展と社会的受容を大きく左右する分岐点に差し掛かっていると言えます。

生成AIと著作権

生成AIはここ数年で急速に普及し、多様な分野での活用が進んでいます。ChatGPTや画像生成AIが一般にも広く利用される一方、著作権侵害リスクや法的トラブルへの関心が高まっています。ここでは生成AIの仕組みと著作権問題の基本的な論点について解説します。
生成AIの仕組み
生成AIとは、膨大な学習データをもとにして、人間の言葉や画像、映像などを自動的に生成する技術です。中心となる技術として「大規模言語モデル(LLM)」と「拡散モデル(Diffusion Model)」があり、それぞれ異なる原理を持っています。LLMはテキストデータを大量に学習し、入力文(プロンプト)に対して自然な文章を生成します。一方、拡散モデルはノイズだらけのデータを段階的にきれいな画像やテキストへ復元するという仕組みです。画像の場合はランダムなノイズ画像から始めて、段階的にノイズを取り除きながら鮮明な画像を作り出します。テキスト生成でも「無意味なトークン列」から段階的に意味のある文章を生成していきます。
ここで重要なのが学習データに関する問題です。生成AIがより人間らしい言語や芸術的なイメージを生成するには、著名な小説、論文、画像など多くの著作物が学習データとして利用されています。この学習データが著作権で保護されたものである場合、法律上のトラブルが生じる可能性があります。日本では平成30年(2018年)の著作権法改正により、「AIの学習目的での著作物利用」は原則として著作権侵害にならないというルールが誕生しました。しかし、その利用方法や出力結果が問題になる場面も多く、技術の進化とともに議論が複雑化しています。
著作権問題の基本的な論点
生成AIと著作権を巡る議論の核心には、いくつかの重要な論点があります。
学習段階での著作権侵害の可能性
生成AIの学習段階で著作権侵害が生じるかどうかは、世界中で議論されています。日本の現行法では、AIの学習・開発目的で著作物を利用することは、通常「著作権侵害に当たらない」としています。これは、著作物を「享受する」のではなく「データ解析の材料」として利用する場合に限られており、著作権法第30条の4が根拠となっています。ただし、学習データをそのまま出力した場合や過度な依拠(特定作家やアーティストの作風をほぼ再現するなど)が認められると著作権侵害リスクが高まります。
生成物に著作権はあるのか
AIによる生成物(文章や画像)に著作権が認められるかについては、日本では「人間の創作性(個性)」を要件としています。AIが自律的に生成しただけのものには、現状著作権は発生しません。つまり、AIが出力した作品そのものは著作物幇助や模倣などに該当しなければ著作権の保護対象外ですが、AIで生成された画像や文章が既存の著作物と酷似している場合は、著作権侵害になる可能性があります。
使用者の責任範囲
AIを利用して生成物を商業利用や二次利用する場合、その使用者が著作権侵害に問われる可能性があります。特に、AIの出力結果を公開・販売・再配布する際、既存著作物との類似性や依拠性が認められれば民事責任、場合によっては刑事責任が問われます。企業規模や個人が問われず、損害賠償請求やサービス停止などのリスクがあることは意識すべきです。
利害関係
生成AIを巡る著作権問題の背景には、AIモデルを提供する事業者(開発企業)、AIを利用するユーザー、データ提供元(著作物の権利者)の間の利害対立が存在します。AIモデル事業者は技術革新やサービス拡張を目指し、ユーザーは効率的な創作活動を追求します。一方、データ提供元は自身の著作物が無断で利用・模倣されることを懸念しています。この三者間の権利調整が今後の法制度や運用の焦点となります。
画像生成AIを巡る問題
画像生成AIは、2025年に入りますます進化を遂げています。一方で、画像生成に伴う著作権問題や倫理問題が社会的な関心を集めており、今後の法的対応が注目されています。ここでは画像生成AIの著作権リスクやトラブルについて解説します。
画像生成AIの技術動向
- Stable Diffusion 3 / 3.5
オープンソースモデルをベースにしながら、3.5版では人物の顔や背景描写の安定性や多様性が著しく向上しました。著作権侵害リスクを軽減するため、学習データの選定や不適切素材のフィルタリング技術が強化されています。 - Midjourney v7
「AIアーティストとの共創」を掲げ、コミュニティ参加型で機能を日々進化。v7では繊細なスタイル制御や感情表現が可能となり、コンセプトアートやイラストレーション分野で高い評価を受けています。 - Adobe Firefly 2.0
商用利用を保証する透明性の高いライセンス対応済みデータセットに基づき、Creative Cloudとの連携強化。広告やマーケティング業界で広く使われており、Photoshopとのシームレスな連携も大きな強みとなっています。
画像生成AIの著作権リスクと法的トラブル
画像生成AIは、従来にない複雑な著作権リスクを抱えています。特に次のような問題が注目されています。
- 著名アーティストの画風模倣による生成画像の商用利用問題
- トレードマークや著作権保護されたビジュアル要素の誤用
- 学習データに無断使用された作品との関係
Getty Images vs. Stability AI訴訟
有名ストックフォト企業Getty Imagesは、Stable Diffusionを開発したStability AIを相手取り、無断で自社の著作物がAIの学習に使われたことによる損害賠償と無許可モデルの停止を求めています。この訴訟は、生成AIの学習データ利用に関わる法的な位置づけを問い直す重要な事件として注目されています。
著名アーティスト風の画像生成問題
特定の著名アーティストの画風を真似た画像生成が商用市場に出回り、著作権者やファンの間で抗議が相次いでいます。こうした事例は倫理的問題も含め、画像生成プラットフォーム側の利用規約強化やコンテンツ審査の必要性を浮き彫りにしました。
トレードマーク権侵害の事例
画像内にブランドロゴやキャラクターが無断で使用されるケースがあり、企業側はブランド価値保護のため監視や法的措置を強化しています。
企業はこれらのリスクを踏まえ、学習用データの適切な管理や利用規約の改訂、生成コンテンツの監視システムの整備に力を入れています。
LoRAと著作権
LoRA(Low-Rank Adaptation)は、既存の生成AIモデルに対し、特定のキャラクターや画風を軽量かつ高速に組み込むファインチューニング技術です。これにより、個人ユーザーや同人活動者でも少ない画像データで特徴を反映した生成が可能となり、幅広い創作活動の活性化に寄与しています。
しかし、LoRAの無断配布や利用をめぐり、著作権及び商標権侵害の問題が浮上しています。キャラクター権利者やクリエイターらは無許可LoRAへの抗議を強め、PixivやBOOTHなどの同人プラットフォームもガイドラインの整備に乗り出しました。LoRA技術の合法利用と権利保護のバランス確保に関する社会的議論も続いています。
画像生成AIの問題と対策
現在利用されている画像生成AIの多くは、著作権の問題を抱えているのが現状です。
特に、無断で著作物が学習データに使われるリスクや、生成画像が既存の著作権や商標権を侵害する可能性が指摘されています。また、こうした問題が原因で画像生成AIに対する社会的印象が悪化し、「利用しただけで非難される」状況も生まれています。
これらの問題に対して、現状では以下の3つの対策が重要とされています。
- 許可済みのデータのみを学習データとして使用すること
権利者から許可を得た画像や独自に生成したクリーンなデータセットの利用が推奨されており、これにより著作権侵害のリスクを根本から減らせます。 - 学習および生成物の権利元を明確化し、管理体制を強化すること
学習に使う素材と生成画像について、誰が権利を持っているかを明示し、責任の所在をはっきりさせることが求められています。 - 生成物の監視体制を整え、不正使用への対応を厳格化すること
プラットフォームやサービス提供者は、生成画像の利用状況を監視し、不適切な利用や侵害行為が見つかった場合には迅速に対処する体制を整えています。
しかしながら、現状ではまだ多くがユーザーやモデル制作者のモラルに頼る部分が大きく、法制度や運用ルールの整備が追いついていません。
これが画像生成AIへの不信感や誤解を生み、健全な利用環境の阻害要因になっています。
今後は技術的な精度向上と同時に、法整備や教育、市場ルールの明確化を進めることで、法律と倫理の両面から問題に取り組み、画像生成AIを安心して活用できる環境を整備することが急務です。
生成AIの透明性とルール作りが急務

生成AIは革新的な技術であり、教育・ビジネス・芸術と幅広い分野で可能性を切り開いています。しかし同時に、著作物の無断利用や生成物の作者性、誤情報による信用失墜といった課題が深刻化し、各国で訴訟や法整備が加速しています。米国の集団訴訟や出版社訴訟、EUのAI法、日本の新聞社による提訴はいずれも共通して、「誰が責任を負い、誰に対価が支払われるべきか」という根本的論点を突きつけています。今後は技術企業と著作権者、利用者の間での権利調整が不可欠となり、透明性やルール作りのあり方が社会的受容を大きく左右するでしょう。生成AIを安心して活用できる環境を築けるかどうかは、まさにこれから数年の制度設計と実務運用にかかっています。