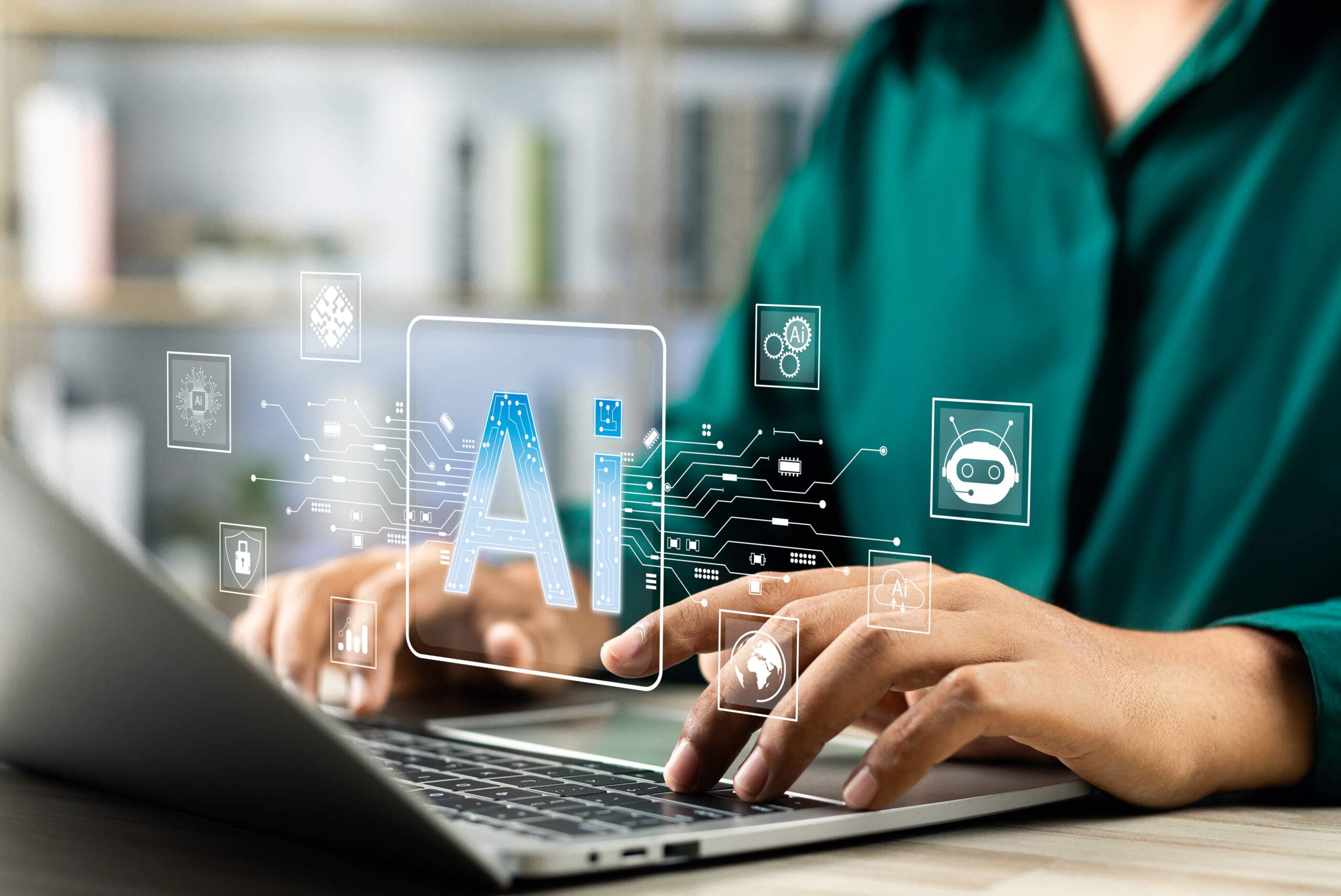「AI理解度チェック」がバージョンアップし、「生成AIの理解度」や「実務で使える知識が身についているかどうか」をより正確にチェックできるようになりました。全30問の選択式テストで構成され、単一回答・複数回答形式を取り入れながら、具体的な業務活用事例や生成AIの活用シーンを題材にした設問、さらに現場でつまずきやすい実務的な問題を通じて、受検者のAIリテラシーの実用性を可視化します。
【関連記事】中堅・中小企業のAI活用を推進!導入事例から知る「AI理解度チェック」の活用法
単なる基礎知識のチェックにとどまらず、AIの理解が実際の業務遂行にどの程度役立つかを測るため、「わかったつもり」から「使える知識」へとレベルを明確に区別。これにより、企業は部署や個人ごとの弱点を具体的に把握し、的確な研修や育成プランを設計できます。
所要時間は15分から30分程度と短時間で受検でき、回答後にはカテゴリー別の詳細なスコアを含むレポートをメールで受け取れるため、現状分析と次のアクションがスムーズに進みます。また、一定数のご希望には無料での個別診断も提供しており、多くの中小企業やDX推進担当者に気軽に活用いただけるサービスです。
こんな方におすすめ
- 中小企業の経営者の方
- DX推進やAI活用担当者、情報システム部門のご担当者
- 営業現場での業務改善や提案支援にAIを活用したい営業職の方
まずは「自身のAI知識」を見える化し、現場で使えるAIリテラシーへ一歩踏み出してみませんか?
今すぐチャレンジ!

リニューアルした「AI理解度チェック」の目的と概要
リニューアルした「AI理解度チェック」は、企業の成長戦略やデジタル化推進に不可欠な“生成AIを使いこなせる人材”の発掘・育成を目指して開発されたサービスです。単なる知識確認ではなく、実際に業務でAIを活用できる応用力やリテラシーを測定することで、自社の現状と課題を客観的に把握し、具体的な人材育成・現場のDX推進に役立てることができます。
なぜ今「生成AI活用人材の見える化」が必要なのか
生成AIは、議事録の要約や文章作成の効率化といった日常業務から、プログラム支援や新規サービスのアイデア創発まで、あらゆる場面での利用が進んでいます。すでに多くの企業が一部業務に導入し始めており、今後は生成AIを積極的に活用できるかどうかが、企業の持続的な成長や競争力の維持を左右する大きな要因となっています。
このときに重要となるのは、専門的な操作スキルよりも「リテラシー」、すなわち正しく理解して安全かつ有効に使いこなす基礎力です。生成AIは便利である一方、誤った回答をそのまま利用すれば業務リスクにつながります。そのため「どのように問いを立てればよいか」「生成された結果をどう検証するか」といった実践知こそが、成果を生み出すための鍵となります。そして、一過性の学習ではなく日常の業務で利用を習慣づけることこそが、社内での活用定着につながります。
また、上からの指示で「AIを使ってみよう」と取り組む姿勢だけでは十分ではありません。自ら業務に取り入れ、主体的に生成AIを使いこなそうとする人材が企業にとって欠かせない存在となります。そうした人材は単なるツール利用者にとどまらず、周囲に知見を広げたり、業務改善のアイデアを生み出したりする“社内の推進役”として力を発揮します。
だからこそ、組織は「誰が生成AIを積極的に活用できているのか」「どの分野で知識不足が見られるのか」を正しく把握することが求められます。生成AI活用人材を見える化することは、教育方針の設計や人材配置だけでなく、企業全体の成長基盤を強化するための第一歩と言えるでしょう。
主な内容
AI理解度チェックは全30問構成で、単一回答と複数回答を組み合わせた選択式テストです。設問には「現場でつまずきやすい実践的な内容」や「業務活用シーン」に基づく問題が多く含まれているのが特徴です。
- チェック形式:
単なる基礎知識の暗記ではなく、実際の業務課題やケースに沿った理解度を問います。 - 実務重視の出題:
例えば「AI導入の効果をどう評価するか」「セキュリティやリスク管理のポイント」「業務でAIをどう使い分けるか」「現場メンバーがAIを使いこなすために必要なステップ」など、企業のDX・業務改善につながる設問が中心です。 - カテゴリ別評価:
受検後には「AI指導活動支援力」「業務取り組み力」「セキュリティ基礎」「AIの使い分け」などのカテゴリーごとのスコアがレポートされ、自社の強みと弱みを客観的なデータで可視化できます。
AI理解度チェックがもたらす実用的な効果
- “分かったつもり”から“実用レベル”に到達できる:
理論だけでなく、実際に現場でAIを活かせるかどうかが明らかになります。 - 弱点の明確化:
カテゴリごとの弱点を把握できるため、優先すべき研修や育成ポイントが見えてきます。 - 企業の「立ち位置」が分かる:
客観データに基づき、競合との差別化や今後の改善策の方向性も明確化できます。
AI理解度チェックは、企業のAIリテラシー現状を客観的かつ実用的に診断し、業務に直結する能力の見える化と組織力強化に貢献する仕組みです。
以下のように文章を整えました。過剰な表現は抑え、わかりやすく自然な語り口にしています。ご確認ください。

「AI理解度チェック」の活用事例

「AI理解度チェック」は単なるAI知識の確認にとどまらず、実務に直結するリテラシーを測定し、的確な育成や活用推進の土台をつくることができます。ここでは、実際にこのチェックを活用している2社の事例を紹介します。
製造業A社の場合:全社のAIリテラシーの底上げ
製造業A社は精密部品の製造を主力とし、主要取引先から品質向上やデジタル化推進の要求を受けていました。一方で、現場作業員と管理職、営業と生産現場の間でAIに対する理解や活用意欲に差があり、これが社内連携や生産性向上の妨げとなっていました。
こうした状況を受け、A社では「AI理解度チェック」を導入しました。最初に製造部門の現場スタッフ約10名で試験的に実施し、その後、部門長や経営企画部も含めて計38名に拡大しました。
チェック結果により、基礎知識だけでなく、生成AIを日常業務で安全かつ効果的に使う力の差を数値とグラフで把握できました。部門ごとにどの分野で知識不足や誤解があるのかも明らかになり、現場の具体的な課題が見えてきました。
結果を踏まえ、A社は以下のような教育や業務改善の取り組みを始めました。
- データ活用やAIモデルの基礎、実際の生産ラインでの活用法を含む研修を実施し、生産効率化ツールのトレーニングも行いました。
- 生成AIを使った顧客提案や競合分析に特化した営業研修も実施。
- AIプロジェクトマネジメントや社内推進の手法を学ぶリーダーシップ研修も展開しました。
これらにより、管理職の理解度の差が縮まり、部門間の情報共有が増え、意思決定の速度や質が向上。現場からも生成AIを活用した業務改善提案が出るようになり、品質向上や不良検出の効率化に実際の効果が見られています。
コールセンター業B社の場合:現場スタッフのリテラシー強化
健康食品通販のB社は、電話だけでなくLINEやチャットなど多様な顧客接点を扱う一方で、人手不足と問い合わせの複雑化による対応負荷が大きくなっていました。AIチャットボットの導入検討は進みつつも、現場のスタッフには「AIが何をできるか」「自分で上手く使えるか」といった不安や抵抗感があり、AI活用が進んでいませんでした。
そこで「AI理解度チェック」を管理職からスタッフ約50名に段階的に実施。受検結果から、AIリテラシーの現状や業務に活かせる具体的な課題が赤裸々に浮き彫りになりました。どの業務でAIが活用できるか、プロンプト設計の難しさ、AIの回答精査が必要な場面などが明確になりました。
結果を共有したことにより、スーパーバイザーを中心に自主的な勉強会が立ち上がり、スタッフ同士がAI活用の疑問や問題を相談し合い、解決を図る文化が根付きました。
また管理職も現場の課題を把握し、効果的なフォローや教育計画が可能となり、チームのモチベーションとAI活用への意欲が高まりました。
B社ではこれによりAIチャットボットの有効活用と、スタッフの長期的なAI活用力強化、業務効率の向上を実現しています。
AI理解度チェックに今すぐチャレンジ!

AI理解度チェックは、生成AIを業務で活用できる人材を正確に評価し、育成や活用計画に役立てるためのツールです。基礎知識だけでなく、実務の現場に即したリテラシーを測定することで、個人や部署ごとの強みや課題が明確になります。企業が現場の状況を客観的に把握し、社員自らがAI活用を促進するための有効なツールです。まずは現状を知り、新しい働き方への一歩を踏み出しましょう。ぜひ、AI理解度チェックをご活用ください。