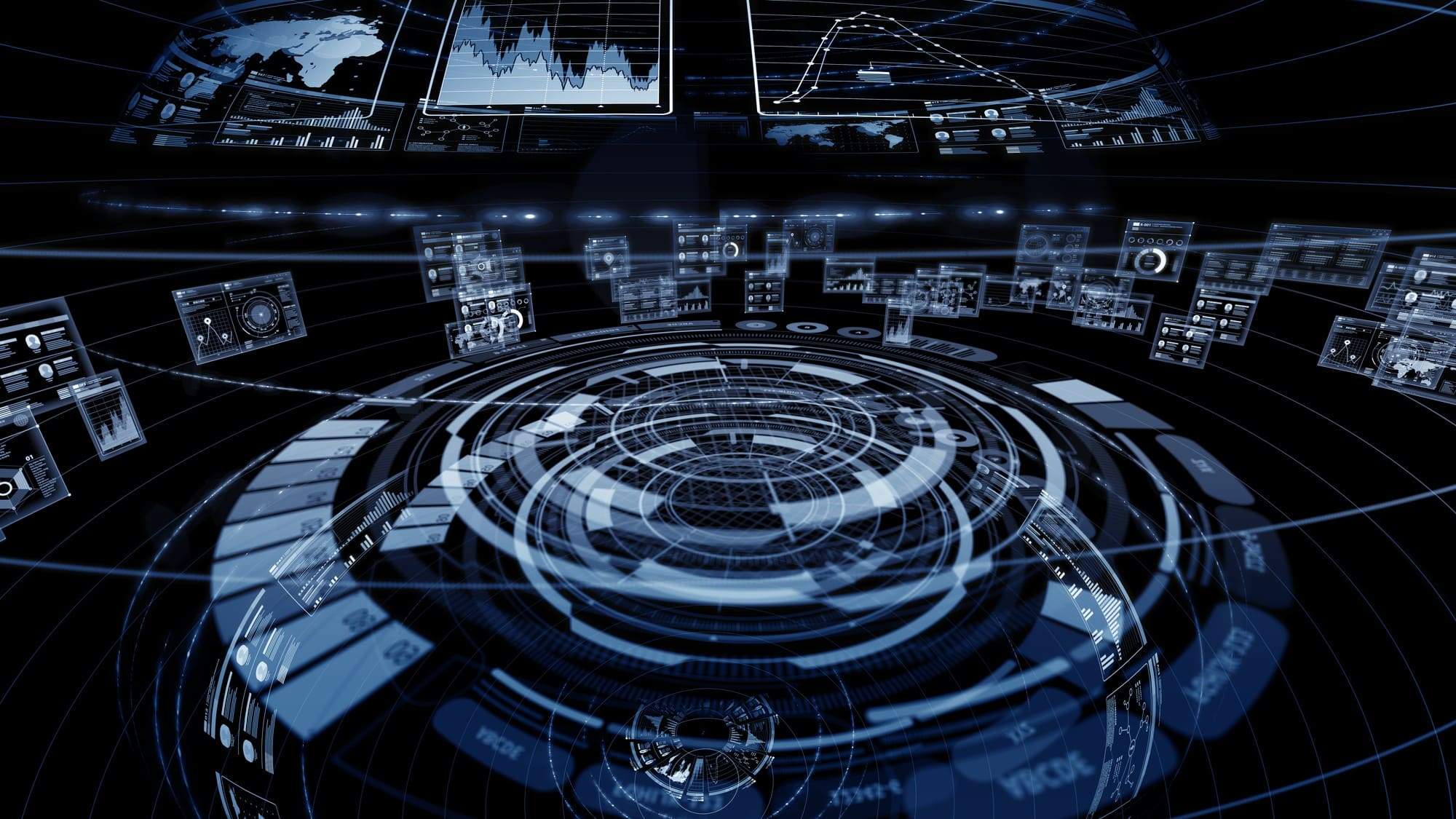2025年、量子コンピュータ技術は長年の理論段階を越え、いよいよ「実用化フェーズ」に突入しました。各国が国家予算規模で量子研究に投資し、企業も次世代産業の覇権をかけて開発競争を繰り広げています。日本でも純国産量子コンピュータの稼働やAIとの統合実験が進み、量子時代の到来が現実のものとなりつつあります。さらに、量子ネットワークや量子暗号といった通信技術の発展により、従来の情報インフラやセキュリティ構造も大きな変革を迎えています。この記事では、量子コンピュータの最前線から量子インターネット、そしてポスト量子暗号まで、世界で進む研究開発の動向とその社会的インパクトを総合的に紹介します。
【関連記事】「プレイアンドオウン」とは?オンラインゲームの新たな経済モデル

実用化フェーズに突入!量子コンピュータの最新ニュース
2025年は国連が「国際量子科学技術年(IYQ)」に定めた年であり、量子コンピュータ分野で歴史的な進展が次々と実現しています。長年理論や研究段階にあった量子技術がついに実用化の兆しを見せ始め、国内外の企業や研究機関が先端技術の開発・実証を競っています。特にAIとの融合が進展し、難解な計算問題や創薬、金融最適化など多様な分野での応用が期待されています。国際的な標準化やセキュリティ対策も進展し、量子コンピュータによる社会変革の土台が整いつつあります。この記事では国内外の最新動向や技術競争、将来展望について詳しく紹介します。
国内の動向
純国産量子コンピューターの稼働開始
2025年7月28日、大阪大学量子情報・量子生命研究センター(QIQB)において、純国産の超伝導量子コンピューターが正式に稼働を開始しました。この量子コンピューターは、主要部品とソフトウェアがすべて日本製で構成され、日本の技術力の結晶といえる成果です。大阪大学を中心に理化学研究所や複数の企業が連携し、システム全体の国内調達と統合を実現しました。
このプロジェクトは政府が掲げる「量子産業化元年」の象徴的なプロジェクトであり、新薬開発や新素材探索などでの実用化に向けた日本の重大な一歩となっています。さらに、2025年8月の大阪・関西万博では、一般来場者が遠隔操作で量子計算を体験できる展示プログラムも実施され、国内外から注目を集めました。
今後は144量子ビットへのスケールアップが計画されており、国内量子技術の持続的な発展が期待されています。
【参考】日本の技術力 世界にアピール 純国産量子コンピューター稼働
富士通の1万量子ビット超プロジェクト
富士通は2030年度までに1万量子ビットを超える大規模な超伝導量子コンピューターの実現を目指し、研究と開発を加速させています。これは現在の技術より格段に大きなシステムであり、長期的な実用化に向けた重要なマイルストーンです。
プロジェクトでは、量子ビットの集積度向上や高精度の誤り訂正技術の強化、冷凍技術の革新など、多角的に技術課題の解決に取り組んでいます。将来的には材料開発や複雑系の最適化、金融シミュレーションなど幅広い産業への応用が期待されています。
ソフトバンクの量子機械学習適用
ソフトバンクは理化学研究所と協力し、30量子ビットの量子コンピューターを使った機械学習技術を通信障害診断に応用することに成功しました。実証実験では、故障予測の精度が約82%に達し、量子機械学習の実用化可能性を強く示しています。
この成果は通信業界において量子技術活用の先駆的事例として注目されており、今後はさらなる精度向上と他分野での応用拡大が期待されています。
世界の動向
米国、中国、欧州は国家レベルで量子技術研究に数百億ドル規模の投資を行っており、基礎研究から実用化、そして暗号技術の再構築まで幅広い領域にわたる競争が激しく展開されています。各国は世界最先端の量子技術を獲得するために、産官学の連携を強化して人材育成や知識ノウハウの集積に努めており、2025年は量子革命期の中核となる重要な研究開発のマイルストーンが数多く達成されています。この流れは、今後数年で量子コンピュータが幅広い産業に浸透するための強力な追い風となっています。
Microsoftのトポロジカル量子ビット
Microsoftはトポロジカル量子ビット技術において革新的な進展を遂げ、エラー率を劇的に低減し12論理量子ビットを実現しました。この技術は量子ビットをノイズに非常に強い「魔法の鎧」のような状態に保つことができ、耐障害性量子コンピュータの実現に向けて大きく前進しています。2025年2月に発表された量子チップ「Majorana 1」は、8量子ビット搭載ながらも、100万量子ビット規模のスケールアップを見据えた設計であり、世界の量子コンピュータ開発競争において注目されるマイルストーンです。
【参考】マイクロソフトが独自の量子チップ、新方式で100万量子ビットが視界に
Googleの105量子ビットWillowチップ
2024年にGoogleは、105量子ビットを搭載したWillowチップを開発し、エラー訂正精度を大幅に向上させました。これにより、量子優位性をより実用的な形で確立することに近づき、量子コンピュータ実用化の重要なステップを踏み出しました。これまでの技術的課題の多くを克服し、クロスチップ通信やエラー耐性等において新たな基準を確立しています。
IBMの1,121量子ビットCondorプロセッサ
IBMは2024年に1,121量子ビットを誇るCondorプロセッサを完成させ、2025年にはさらに改良されたKookaburraプロセッサの開発に着手しています。これらは2030年代の耐障害性量子コンピュータの実用化を見据えたもので、量子ソフトウェア開発の拠点となる「National Quantum Algorithm Center」をシカゴに設立し、周辺エコシステムの構築にも力を入れています。
【参考】IBMが世界で初めて耐障害性を備えた大規模量子コンピューター「IBM Quantum Starling」の開発に着手
ポスト量子暗号の標準化
2024年に米国の[NIST(ナショナルインスティテュートオブスタンダードズアンドテクノロジー)]が主導してポスト量子暗号(PQC)の主要アルゴリズムが正式に標準化され、2025年には複数の業界で実証実験や段階的な社会実装が進められています。PQCは、量子コンピュータが解読可能とする既存の暗号システムへの対策を目的とし、グローバルな安全保障の要ともなる技術です。中国や欧州も独自の標準化作業や規制整備を並行して推進しており、量子安全技術の獲得競争は経済競争力や国家の安全保障に直結しています。

量子コンピュータの歴史と主要な方式

量子コンピュータは、古典コンピュータの限界を超え、量子力学の原理を使ってこれまで解けなかった複雑な問題を高速に処理できる革新的な技術として注目されています。研究は1980年代の初めから始まり、今では実用化を目指してさまざまな方式が開発されています。ここでは、量子コンピュータの歴史と主な方式を分かりやすく紹介します。
量子コンピュータの歴史
量子コンピュータの発想は、1960〜70年代の量子力学の基礎研究までさかのぼります。
1981年、リチャード・ファインマンが「従来のコンピュータでは量子システムを正確にシミュレーションできない。量子の性質を使った計算機が必要だ」と提唱したことが、量子計算研究の始まりでした。
1985年にはデビッド・ドイッチュが量子チューリングマシンの理論を提案し、1994年にはピーター・ショアが素因数分解を効率的に行う「ショアのアルゴリズム」を発表。1996年にはロブ・グローバーが高速検索アルゴリズムを考案しました。これらの成果が、量子コンピュータが従来の計算機を超える可能性を明確に示し、世界的な研究ブームを生み出しました。
1990年代末から2000年代にかけては、理論研究から実際の装置開発への移行が加速しました。
特に日本の中村泰信博士らは、30年以上前に超伝導量子ビットの実証に成功しており、この分野の先駆的な研究が現在の超伝導量子コンピュータの基礎となりました。
2011年にはカナダのD-Wave社が量子アニーリング方式の商用機を発表し、IBMやGoogleも汎用量子コンピュータの開発を本格化。2025年にはついに1000量子ビットを超える大規模プロセッサが登場しています。
主要な量子コンピュータの方式
量子コンピュータを実現するための方法にはいくつかのアプローチがあり、それぞれに特徴と課題があります。
超伝導方式
超伝導量子ビットは、超伝導体のジョセフソン接合を利用して人工的に量子の2準位を作り出す方式で、現在もっとも広く研究が進められています。
冷却した超伝導回路を使い、マイクロ波パルスで制御することで高速な量子ゲート操作が可能です。動作速度が速く集積度も高いのが強みで、IBMやGoogleの量子チップもこの方式を採用しています。
数ミリケルビンという極低温での動作が必要という難しさはありますが、技術の進歩によってスケールアップが進み、誤り訂正の研究も活発です。日本の中村泰信博士らの研究は、この分野で世界的に重要な成果を上げています。
イオントラップ方式
イオントラップ方式は、電磁場で捕らえたイオンを量子ビットとして使い、その内部の電子状態をレーザー光で制御する方法です。
この方式の特徴は、コヒーレンス時間(量子状態を保てる時間)が非常に長く、量子情報を安定して保持できる点にあります。誤りに強く、ゲート操作の精度も高いことが実験で確かめられています。
IBMなどの研究機関がこの方式の開発を進めており、量子通信や量子ネットワークへの応用も期待されています。一方で、大規模化や高頻度演算のための装置設計には高度な技術が求められます。
光方式
光量子ビットは、光子の偏光や位相を使って情報を表現する方式で、常温で動作しながら長距離通信が可能な点が特長です。
光子は伝送しやすく、低損失で高速に量子情報を送れるため、量子ネットワーク構築に向いています。小型で扱いやすい装置の開発も進んでおり、大阪大学をはじめとする研究グループが実用化に向けた研究を活発に行っています。
トポロジカル量子ビット
トポロジカル量子ビットは、量子情報をトポロジー(形の数学)によって保護し、外部ノイズに強いのが最大の特徴です。
Microsoftの研究チームは2025年、この方式で8論理量子ビットを実装したチップ「Majorana 1」を開発し、エラーを大幅に減らすことに成功しました。
この方式は、量子ビットを構造的に守る仕組みを持つため、他の方式に比べて外乱に非常に強く、将来的には100万量子ビット規模の大規模量子コンピュータを実現する鍵になると考えられています。実用化にはまだ研究が必要ですが、期待は非常に大きい技術です。
これらの方式はそれぞれ異なる特性を持ち、今後は用途に応じて使い分けたり、複数の技術を組み合わせたりする可能性もあります。量子コンピュータ技術は多方向で発展を続けており、今後の進歩と実用化に大きな期待が寄せられています。
量子インターネットとセキュリティ
量子コンピュータの研究が進む中で、もう一つ注目を集めているのが量子インターネットです。これは、量子の性質を利用した新しい通信ネットワークであり、現代のインターネットや暗号通信の仕組みを根本から変える技術とされています。
量子コンピュータの登場によって、現在の暗号システムが解読されてしまうリスクが現実味を帯びてきた今、「量子によって壊される側から、量子によって守る側へ」という技術転換が求められています。この章では、量子インターネットの仕組みと役割、量子暗号通信、そしてポスト量子暗号の取り組みについて分かりやすく解説します。
量子インターネットとは
量子インターネットとは、量子状態(たとえば光子の偏光やスピン)を使って情報を送受信する新しい通信網のことです。最大の特徴は、量子もつれ(エンタングルメント)と呼ばれる現象を活用する点にあります。
2つの量子ビットがもつれ状態になると、一方の状態を観測するだけで、遠く離れたもう一方の状態も瞬時に決まります。この性質を利用すれば、物理的な距離に関係なく安全に情報を共有できる新しい通信形態が実現できます。
量子インターネットでは、通常のデータ通信に使われる「光ファイバー」や「衛星通信」といった経路を介して、光子を量子情報のキャリアとして転送します。しかし、量子情報は非常に繊細で、途中で観測されたりノイズを受けたりするとすぐに状態が崩れてしまう(デコヒーレンス)ため、技術的な課題も多く残っています。
この問題を解決する鍵とされているのが量子中継(Quantum Repeater)です。量子中継は、もつれ状態を分割して順に「中継」しながら再構成する仕組みであり、数百キロメートル単位の長距離量子通信を可能にする重要な技術として研究が進められています。
現在、日本、アメリカ、中国、欧州各国で量子通信インフラの実証実験が行われており、日本でもNTT、東大、NICTなどが共同で「量子ネットワーク拠点」を構築中です。将来的には、量子コンピュータ同士を全球的に結ぶ「量子ネットワーク」が形成され、インターネットの通信構造そのものを置き換える可能性も指摘されています。
量子暗号通信
量子暗号通信は、量子の性質を利用して盗聴を不可能にする通信技術です。代表的なのが量子鍵配送(Quantum Key Distribution, QKD)と呼ばれる方式です。
QKDでは、通信相手同士が光子の偏光など量子状態を使って暗号鍵を共有します。この過程で第三者がその光子を盗聴しようとすると、量子状態が必ず変化するため、盗聴の有無を検知できます。これにより、鍵自体を安全にやり取りできる「理論的に盗聴不可能な通信」を実現できるのです。
最も有名なプロトコルは「BB84方式」(1984年提案)で、現在も量子通信の標準的な仕組みとして世界中で実験・実装が行われています。日本では、東京と埼玉を結んだ光ファイバー上でNTTがQKD技術を運用試験しており、政府データや金融システムなど高機密通信への応用も検討されています。
ただし、量子暗号通信にも課題があります。光ファイバーを通す距離が長くなると量子状態が壊れやすく、使用できる範囲が制限されること、装置コストがまだ高いことなどです。また、送信機や受信機の物理的欠陥を狙った「サイドチャネル攻撃」に対しては完全ではありません。そのため、量子通信の安全性を保証するための認証技術やハードウェア安全設計の研究も進められています。
ポスト量子暗号と課題
量子通信が現実化しつつある一方で、量子コンピュータによって既存の暗号が解読されるリスクも深刻な問題になっています。特にRSA暗号や楕円曲線暗号のような「素因数分解」や「離散対数問題」に基づく暗号方式は、ショアのアルゴリズムにより短時間で破られる可能性があるとされています。
この脅威に対応するため、世界各国では「ポスト量子暗号(Post-Quantum Cryptography, PQC)」の標準化が進められています。PQCは量子コンピュータでも解けない数学的構造(格子問題や符号理論など)を利用した新しい暗号方式で、アメリカのNIST(国立標準技術研究所)が2024年に初の標準方式を採択しました。日本の研究機関や企業も同プロジェクトに多く参画しています。
ただし、PQCも万能ではありません。計算コストが増大しやすく、ハードウェアへの実装が難しいこと、既存の通信プロトコルとの互換性など、実用段階では解決すべき課題がまだ多く残っています。
また、量子暗号通信とPQCのどちらを社会インフラとして採用すべきかは国や業界によって議論が分かれており、場合によっては「併用」による多層防御(Defence in Depth)の考え方が有力視されています。
量子コンピュータが計算の世界を変えると同時に、量子インターネットと新たな暗号技術は通信とセキュリティの未来を塗り替えつつあります。安全なデジタル社会を保つためには、「量子に壊されない世界」ではなく、「量子そのものを使って守る世界」をいかに実現するかが、これからの大きなテーマになっていくでしょう。
量子技術の進化に注目

量子コンピュータは、AIや暗号資産といった話題の陰で注目されにくい存在ですが、その研究と開発は確実に進展しています。現時点で一般の人が量子コンピュータを直接目にする機会は限られていますが、国家規模のサイバー攻撃などに量子技術が悪用されれば、その影響は国際社会全体に及ぶ可能性があります。量子技術は、未来の産業基盤であると同時に、安全保障上の重要課題でもあります。
その一方で、日本はこの分野で世界的にも先駆的な成果を挙げており、国産の超伝導量子コンピュータの稼働や光を利用した新しい方式の開発など、独自の強みを発揮しています。こうした動きは、量子時代を支える技術力として国内外から高く評価されつつあります。量子技術の進化は、社会の仕組みや産業構造を大きく変える可能性を秘めており、その歩みは未来への確かな希望を感じさせます。