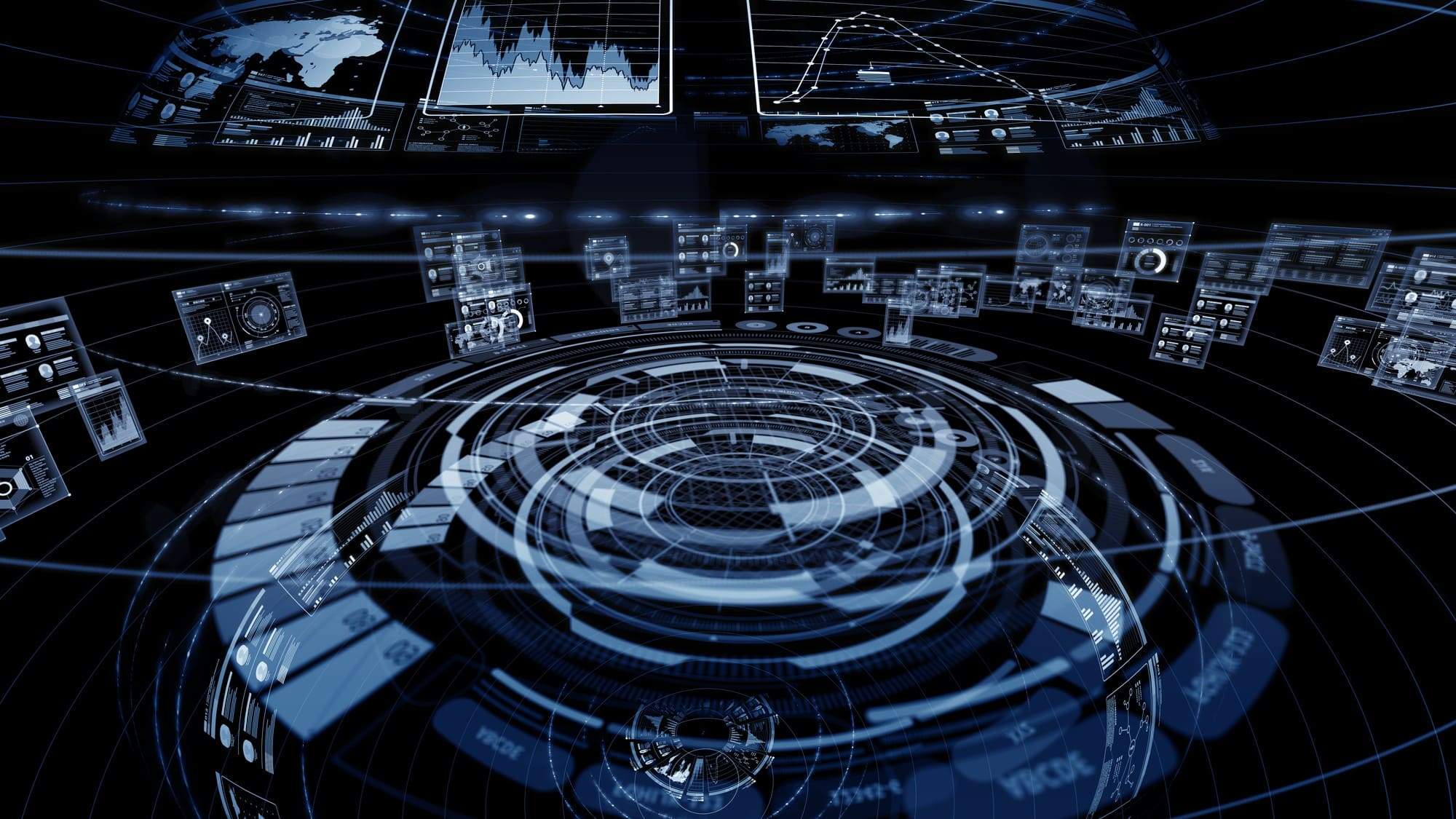2025年の大阪・関西万博は、単なる国際イベントではなく、AIやロボティクス、環境エネルギーなどの社会実装を試す「未来社会の実験場」となりました。
会場では、空飛ぶクルマの実証やスマートエネルギーの管理、AIによる多言語対応など、最新技術が現実の課題解決へ向かう姿が数多く見られました。
この半年間の開催で得られた成果は、テクノロジーの進歩にとどまりません。
持続可能な社会を実現するために、人々の意識をどう変え、社会の仕組みをどう整えていくかを考える契機にもなりました。
この記事では、日本が描くモビリティ革命と未来社会の姿をたどります。
【関連記事】【2025年最新版】トポロジカル量子ビットとは?量子コンピュータの開発最前線

「大阪・関西万博」が描いた未来
2025年春から秋にかけて開催された大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」という壮大なテーマのもと、世界中の企業、研究機関、自治体が集まりました。総来場者数は約2820万人に達し、万博史上でも最大級の規模となりました。会場では、最先端の科学技術と持続可能な社会のあり方を融合させる「リアルな未来実験」が繰り広げられ、単なる見本市を超えて、人とテクノロジーの新しい関係を描く場となりました。
eVTOLが象徴した空のモビリティ革命
最も注目を集めたのは、SkyDrive社による電動垂直離着陸機(eVTOL)「空飛ぶクルマ」の実証飛行でした。会場内に設けられた専用離発着場「EXPO Vertiport」では、操縦士と乗客を乗せた機体が静かな電動音とともに浮上し、時速約100キロで滑らかに飛行しました。その光景は、映画やアニメでしか見たことのなかった“未来の空の移動”を現実のものとしました。
一部の来場者は実際に搭乗体験を行い、都市間を空で結ぶ次世代交通の可能性を肌で感じることができました。空飛ぶクルマは、交通混雑の解消や災害時の緊急輸送など、社会課題の解決に向けた新たな手段として注目を集めました。
AIとデジタルが支えた次世代の万博体験
会場運営にはAIとデジタル技術が多方面で活用されました。多言語翻訳AIを搭載した音声案内システムや、顔認証によるスマート入場が導入され、煩雑になりがちな国際イベントの運営をスムーズにしました。来場者はパスポートやチケットを提示することなくゲートを通過でき、混雑緩和とセキュリティの両立を実現しました。
案内ロボット「ugo」は来場者から高い評価を得ました。自然な会話に応じながら目的地まで案内したり、安全確認を行ったりと、人と機械が協働する新しい運営スタイルを実現しました。ロボットとの対話を通じて、テクノロジーが生活に自然に溶け込む未来像が示されました。来場者と技術が共に未来を描く“共創型の万博”が実現したといえます。
環境エネルギーと生命科学の融合
環境・エネルギー分野や生命科学でも最先端の取り組みが披露されました。会場では、水素燃料で動く船舶や移動車両が運用され、再生可能エネルギーを基盤とする新しい都市モデルの実証が行われました。海上会場では、水素と太陽光を組み合わせたエネルギー供給システムが紹介され、脱炭素社会を見据えた現実的な技術が注目を集めました。
iPS細胞を用いた再生医療の展示では、病気の予防や個別医療の実現を目指した新しい医療の形が紹介されました。バイオとAI、医療とデータの連携が、人が健康に生きる未来の可能性を示しました。
「未来社会の実験場」が残したもの
大阪・関西万博の大きな特徴は、展示にとどまらず、社会実装へつながる実証の場となったことです。出展企業、自治体、大学が会期終了後も連携を続け、実験データの分析や地域での実践を進めています。この“レガシー・プロジェクト”が、万博を単なるイベントではなく、継続的なイノベーションの拠点へと発展させています。
また、ボランティアや学生、一般来場者が共創の担い手として参加したことも印象的でした。技術は特別な専門家だけのものではなく、社会全体で育てていくものだという意識が広がりました。誰もが未来づくりの担い手となり、社会の中で新しい価値観が育っていきました。人を中心に据えたテクノロジーのあり方を模索する動きが、着実に広がっていきました。
2030年へ続く希望の青写真
万博で示された数々の技術実証は、2030年以降の都市や社会を形づくる基盤になると期待されています。空飛ぶクルマの運航ルート構想、AIによる観光支援や医療サポート、水素エネルギーを核とした未来の都市づくりなど、次世代社会への動きがすでに始まっています。
半年間にわたる「未来社会の実験」は、技術の進歩だけでなく、人と自然、人と都市、そして人と未来の関係を問い直す場となりました。大阪・関西万博は、かつての「進歩の祭典」を超え、共生と調和をテーマにした「希望のデザイン展」へと進化しました。その成果は今も社会の中で生き続け、これからの社会づくりの基盤となるでしょう。

移動革命の最前線:「空飛ぶクルマ」とモビリティネットワークの革新

空を移動する時代は、もはや未来の話ではありません。2025年の大阪・関西万博で世界に披露された空飛ぶクルマは、次世代モビリティの象徴として注目を集めました。電動垂直離着陸機(eVTOL)は、空域を新たな移動空間として活用し、都市の渋滞や地方の移動の不便さといった社会課題の解決に向けた重要な技術となりつつあります。陸上の自動運転車やAI制御の交通システムと連携することで、これまで分断されていた交通インフラに革新をもたらそうとしています。
eVTOLが拓く新しい移動エコシステム
eVTOLの最大の特徴は、従来の航空機と異なり滑走路を必要としないことです。垂直離着陸が可能なため、都市中心部や海上、ビル屋上などにも離発着場を設置できます。環境面では電動化によるゼロエミッション化が進み、静粛性にも優れており、環境配慮型モビリティとしての期待が高まっています。
大阪・関西万博での実証飛行を契機に、日本では複数の企業が国土交通省と連携しながら安全基準や運航ルールの整備を進めています。SkyDrive、トヨタ、ANAホールディングスなどが開発中の機体は、都市間移動だけでなく、災害時の物資輸送や離島支援など多様な用途を想定しています。AIが機体の距離や経路を管理し、リアルタイム通信で気象や空域情報を共有することで、人とAIが協働する空の交通網が整いはじめています。
都市交通の再設計と地方への波及
eVTOLの登場は、新しい交通手段の誕生にとどまりません。地上の自動運転バスやMaaS(Mobility as a Service)と連携し、空と陸を行き来できるシームレスな移動ネットワークを構築する動きが進んでいます。東京や大阪では、鉄道駅や商業施設上空を活用した「立体モビリティ拠点」の計画が進み、地下・地上・空をつなぐ立体的な移動が現実味を帯びています。
一方、地方では過疎化により交通手段が失われつつある地域で、eVTOLとドローンを組み合わせた物流・医療支援システムの開発が期待されています。高齢者の移動支援や観光ルートの再設計など、生活インフラとしてのモビリティ活用が注目されています。こうした取り組みは、地域経済の再活性化と人口分散型社会の実現を後押しする動きとして位置づけられています。
官民一体による制度設計とインフラ整備
政府も「空の移動革命」を国家戦略として推進しています。国土交通省を中心とする官民協議会では、飛行空域の管理、安全認証、騒音基準、操縦資格などのルールづくりが進行中です。2025年度中には新たなロードマップが策定され、2020年代後半からの都市圏運航、2030年代には全国での商用展開が見込まれています。
東京都では「空飛ぶクルマ実装プロジェクト」を立ち上げ、離着陸場(Vertiport)の整備や都市景観との調和を検討。関西圏でも湾岸部を中心に、観光エリアや防災拠点を結ぶルート構想が進んでいます。自治体と事業者の連携が各地で進み、輸送・観光・防災を一体化した社会実装モデルが動き出しています。
日本の競争戦略と国際的ポジション
世界では米国のJoby AviationやArcher Aviation、中国のEHang、欧州のVolocopterなどが商用化競争を繰り広げています。こうしたなかで日本は、安全性・環境適合性・社会受容性の三本を柱に独自の戦略を展開しています。
政府と企業は、国際標準に対応した安全基準の国産化を進め、AI航行管理を含めた空域交通ルール(UTM: UAM Traffic Management)の制度設計に取り組んでいます。特に災害支援や離島交通など日本特有の課題に即したユースケースを重視し、海外との差別化を図っています。
産業構造面では、自動車産業と航空産業を融合した次世代移動産業クラスターづくりが進んでいます。トヨタ、スバル、ホンダなどの大手メーカーがスタートアップと協業し、機体、電池、通信、AI制御までを国内サプライチェーンで一貫製造する体制を構築中です。経済産業省も2030年代を見据え、脱炭素化と交通安全の両立を目指すモビリティ産業立国構想を掲げています。
これらの政策と技術の統合は、単に新産業を生み出すだけでなく、日本版モビリティモデルを世界市場に発信する基盤にもなっています。データ、通信、エネルギーが結びつくことで、モビリティは単なる「移動手段」から社会インフラそのものへと進化しようとしています。
モビリティが導く新たな社会像
空飛ぶクルマは、未来の乗り物としてだけでなく、人と都市のつながりを再構築する新しい技術へと変化しています。AIや脱炭素エネルギー、地上交通データの融合が進むことで、人の移動は単なる利便性を超え、社会全体をつなぐ新しい仕組みへと発展しつつあります。
日本がこの分野でリードできるかどうかは、個々の技術力だけでなく、社会全体が新しい移動のあり方を受け入れ、都市設計や生活文化まで取り込めるかにかかっています。空飛ぶモビリティは、テクノロジーの進化にとどまらず、私たちの暮らし方や都市の形を変えつつあるのです。
持続可能な未来社会は作れるか
持続可能な未来社会の実現は、人類が直面する最大のテーマです。環境問題、人口減少、地域格差、高齢化、労働力不足など、複合的に絡み合う課題を同時に解決していくことが求められています。その鍵を握るのが、AIとロボティクスを中心とするテクノロジーです。これらは単なる効率化の道具ではなく、社会の仕組みと価値観を変えていく原動力になっています。
社会課題を支えるAIとロボットの共進化
最新のAI搭載ロボットは、すでにさまざまな分野で欠かせない存在です。医療・介護の現場では患者の見守りや初期診断支援を行い、教育では学習データを解析して個別最適な指導を実現。農業や製造業でも自動化や精密管理を担い、人手不足を補いながら生産性と品質を向上させています。
なかでも、自律移動ロボットや人と協力して働く協働ロボット(コボット)は、都市部に限らず地方でも導入が進んでいます。過疎化が進む地域では物流の“最後の一マイル”を支え、農業支援や除雪、介護現場でのサポートなど、多岐にわたる分野で活用が広がっています。こうした技術の普及は、新たな雇用創出と地方産業の再生にもつながっています。
エネルギーとデータが支える持続可能な社会基盤
エネルギー分野では、AIによる需要予測とスマートグリッド制御が実用化段階を迎えています。再生可能エネルギーの発電量を予測し、電力需給を自動で調整する仕組みにより、無駄のない電力循環が可能になりました。これにより、温室効果ガスの削減に加え、地域単位で運用できる分散型エネルギー経済が形成されつつあります。
また、デジタル通貨やキャッシュレス決済の拡大は、経済的包摂を推進しています。小規模事業者や高齢者、外国人労働者など、これまで現金中心の取引で制約を受けていた層にも経済参加の機会を広げています。こうした「誰も取り残さないデジタル経済」の流れこそ、SDGsが掲げる理念を現実の社会基盤として実現する試みといえます。
スマート化する社会インフラと新たな安全保障
AIとロボティクスの応用は、社会基盤の根幹にも及んでいます。スマートシティや防災分野では、センサーやドローンが災害予兆を監視し、発生時には自動で避難経路を提示します。交通や物流では、AIが渋滞状況や配送ルートをリアルタイムで最適化し、環境負荷の少ない運用を実現しています。
さらに、河川や山林の環境監視、建設現場の安全管理にもAIが活用され、人の労力を抑えながら災害リスクを低減しています。これらの技術が結びつき、国家レベルでの「テクノロジーによる安全保障」も新たな段階へ進みつつあります。サイバー空間と物理空間の統合的な防災・保全システムが、現実社会に根を下ろし始めています。
倫理・共感・共創の時代へ
ただし、技術の発展はそのまま幸福を意味するものではありません。AIやロボットの導入が進むほど、倫理的判断や人間らしい感性の価値が一層問われるようになっています。個人情報の扱いやアルゴリズムの透明性、多様性と公平性の確保といった課題は、今後の社会設計の中心に据えられるでしょう。
真に持続可能な社会とは、単に技術が進む世界ではなく、人がテクノロジーを信頼し、共に成長できる仕組みを持つ社会です。AIやロボットを人の代替ではなく、人の能力を引き出す共創のパートナーとして位置付けることが欠かせません。テクノロジーと人との関係をどう築くか――それが、これからの10年を左右する重要な鍵となります。
行動変容が未来を変える
テクノロジーが進化しても、それをどう使うかを決めるのは人間です。AIやロボットを社会に根づかせるためには、制度や技術だけではなく、私たち一人ひとりの意識改革と行動変容が求められます。学校教育ではデジタルリテラシーやAI倫理教育が急速に進み、企業や自治体でも人材育成の仕組みが広がっています。
さらに近年では、働き方や学びの在り方にも変化が見られます。リモートワークやオンライン教育の普及により、人々が時間や場所に縛られずに学び、働く文化が根づきつつあります。こうした変化は「技術に適応する社会」から「技術と共に成長する社会」への転換を促しています。つまり、AIやロボティクスによる未来社会を支えるのは、人間の柔軟な思考と学び直しの力、その積み重ねによる文化的進化なのです。
万博が示した共生のビジョン
2025年の大阪・関西万博は、まさにこのような価値観を世界に示す舞台となりました。会場では、AI医療支援システム、エネルギー自動制御グリッド、災害対応ロボットなどが実証され、「いのち輝く未来社会」というテーマを具現化しました。
2030年を見据えた今、私たちは、AIとロボティクスの力を最大限に活かしながら、地域や世代を超えて支え合う共創型の社会を築く責任があります。技術と人が互いに信頼し、協調しながら進化する未来――その先に、真の持続可能社会が見えてきます。
テクノロジーと人が共に創る未来へ

未来社会は、遠い将来の理想ではなく、すでに現在の延長線上にあります。
大阪・関西万博で見えたのは、テクノロジーが人の想いと結びついたときに生まれる新しい希望のかたちでした。
AIの進化は、近い将来、人間を超える知的存在を生み出すと予測されています。
その時、社会は何を選び、どのように共存していくのか――その答えをいまから正確に描くことはできません。
しかし、テクノロジーの進化に私たちが最も期待するのは、その未知の時代を自らの手でどう描けるかという可能性にあるでしょう。
モビリティの革新は、人と人が地理的な制約を超えてつながる新たな時代の到来を告げています。
技術と人が共に歩み、未来を築く力。そこに、持続可能な「やさしい社会」の答えが見えてきます。