
組織内の知識を効果的に活用することは、企業の競争力向上に不可欠です。本記事では、暗黙知と形式知の違いを解説し、FAQシステムを活用した効果的な社内ナレッジ活用法を紹介します。
【関連記事】社内資料をまるごと活用!デコールFAQ Makerで実現する業務改革とは
暗黙知と形式知
組織内の知識は、大きく暗黙知と形式知に分類されます。これらの違いを理解することで、効果的な知識管理が可能になります。知識管理の重要性は、ビジネス環境の急速な変化と情報技術の発展により、ますます高まっています。
暗黙知と形式知の違いとは|身近な例とナレッジマネジメントのポイントを解説
暗黙知の定義と特徴
暗黙知は、個人の経験や勘に基づいて獲得された知識であり、言語化しにくく、他者への共有が難しい知識です。マイケル・ポランニーが提唱したこの概念は、「我々は語れる以上のことを知っている」という言葉に集約されます。
暗黙知の主な特徴は以下の通りです。
- 個人的である:個人の経験や直感に基づいているため、その人固有の知識となります。
- 文脈依存である:特定の状況や環境に強く結びついています。
- 動的である:常に変化し、進化し続けます。
- 実践的である:実際の行動や実践を通じて獲得されます。
例えば、スポーツにおける状況判断や相手の動きを読む力、職場での社交的なスキルやコミュニケーション能力などが暗黙知の例として挙げられます。これらのスキルは、長年の経験や練習を通じて獲得されますが、その過程を明確に言語化することは困難です。
熟練した職人の技術も、典型的な暗黙知の例です。彼らは長年の経験を通じて、材料の微妙な違いを感じ取り、最適な加工方法を選択することができますが、その判断基準を明確に説明することは難しいでしょう。
形式知の定義と特徴
形式知は、言葉や数式などで誰でも意味を理解できるように表現された知識です。これは、文書化され、体系化された知識であり、容易に共有・伝達することができます。
形式知の主な特徴は以下の通りです。
- 明示的である:言語や数式、図表などで明確に表現されています。
- 体系的である:論理的に整理され、構造化されています。
- 客観的である:個人の主観に依存せず、誰もが同じように理解できます。
- 伝達可能である:文書やデジタルデータとして容易に共有できます。
学校で学ぶ数学や科学の公式や法則、業務マニュアルや手順書、会社のルールや規定などが形式知の例として挙げられます。これらの知識は、明確に文書化されており、誰でも同じように理解し、適用することができます。
例えば、製造業における製品の組立手順書は、典型的な形式知です。この手順書には、各部品の名称、組立の順序、必要な工具、注意点などが詳細に記載されており、経験の浅い作業者でも正確に作業を行うことができます。
暗黙知と形式知の違い
バランスを取りながら自転車に乗る感覚は、典型的な暗黙知です。多くの人は自転車に乗ることができますが、その感覚を言葉で正確に説明することは非常に困難です。自転車に乗るためには、ペダルを漕ぐ力、ハンドルの操作、体重移動などを同時に行う必要がありますが、これらの要素をどのように組み合わせるかは、個人の経験と感覚に大きく依存します。
一方、「アクセルやブレーキを踏む」などのマニュアル化された運転方法は形式知として分類されます。これらの操作方法は、明確に言語化され、誰でも理解できる形で文書化されています。例えば、「右に曲がるときは、まず速度を落とし、右手でハンドルを右に回す」といった指示は、形式知の一例です。
暗黙知と形式知の違いは、知識の獲得方法と共有の容易さにも表れます。暗黙知は主に個人の経験や実践を通じて獲得され、その共有には直接的な指導や観察が必要となります。一方、形式知は文書や講義を通じて学ぶことができ、デジタルデータとして容易に共有・伝達することが可能です。
組織における知識管理においては、暗黙知と形式知の両方を適切に活用することが重要です。暗黙知は組織の競争力の源泉となる可能性がありますが、個人に依存するため、その人材が離職した際に知識が失われるリスクがあります。そのため、可能な限り暗黙知を形式知化し、組織全体で共有できるようにすることが求められます。
同時に、形式知だけでは対応できない複雑な状況や問題に直面した際には、暗黙知が重要な役割を果たします。したがって、形式知の蓄積と共有を進めつつ、暗黙知の価値を認識し、その共有と活用を促進する仕組みを構築することが、効果的な知識管理の鍵となります。
「デコールFAQ Maker」で暗黙知を形式知に変換!
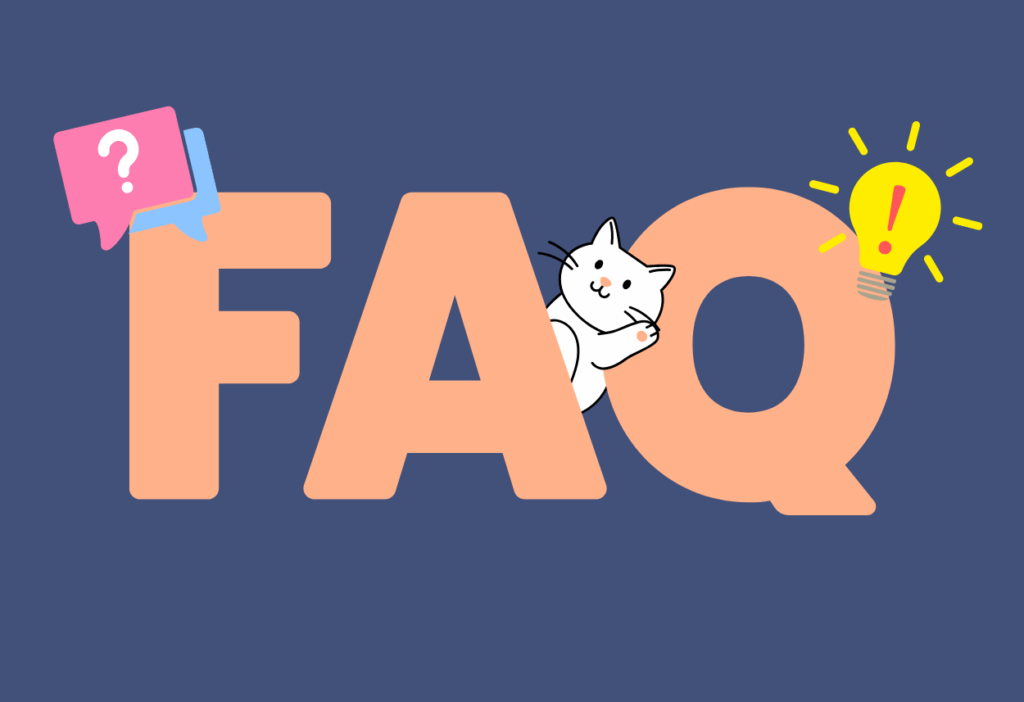
デコールFAQ Makerは、最新のAI技術を活用して効率的に社内ナレッジを形式知化し、共有するためのツールです。このシステムは、暗黙知を形式知に変換し、組織全体での共有と活用を実現します。
FAQシステム導入の課題
情報の更新と管理
FAQシステムを効果的に運用するためには、情報の更新と管理が不可欠です。多くの組織では、FAQの内容が古くなったり、不正確になったりすることが課題となっています。また、新しい情報を迅速に反映させることも重要です。
デコールFAQ Makerは、AIを活用して情報の更新と管理を効率化します。システムが自動的に類似のFAQを検出し、統合や更新の提案を行うことで、管理者の負担を軽減します。
暗黙知から形式知への変換
個人の経験や知識を組織全体で共有可能な形式知に変換することは、大きな課題の一つです。多くの貴重な知識が個人の頭の中にとどまり、組織全体で活用されていないケースが多々あります。
デコールFAQ Makerは、この課題に対して革新的なソリューションを提供します。AIによる自然言語処理技術を活用することで、個人の経験や知識を効率的にFAQ形式に変換し、組織全体で共有可能な形式知として蓄積します。
デコールFAQ Makerの主な機能
様々な形式の文章をFAQに変換
デコールFAQ MakerはGPT-4を活用し、様々な形式の文章を効率的にFAQ形式に変換します。既存のマニュアルや営業資料などのPDFファイルを直接取り込み、その内容を基にFAQを自動生成する機能を備えています。
これにより、規約、マニュアル、営業資料、IR資料など、様々な既存のPDFコンテンツから初期構築の工数をかけずにFAQを構築することが可能になります。また、テキストデータをコピー&ペーストで貼り付け、作成ボタンをワンクリックするだけで、複数のQ&Aを自動生成することもできます。
応対音声からFAQを生成
デコールFAQ Makerは、音声データからFAQを自動生成する機能により、暗黙知の形式知化を促進します。特にコールセンターなどの現場では、顧客との対話の中に多くの貴重な情報が含まれています。
この機能を活用することで、コールセンターの応対音声を自動的にテキスト化し、そこからFAQを生成することができます。これにより、現場の経験豊富なオペレーターの知識を効率的に形式知化し、組織全体で共有することが可能になります。
AIによるFAQの自動統合
デコールFAQ Makerは、AIを活用して類似のFAQを自動的に統合し、効率的なナレッジ管理を実現します。同じような内容のFAQが複数存在すると、ユーザーが必要な情報を見つけにくくなる問題がありましたが、この機能によりその課題を解決します。
また、質問文の類似表現や関連タグ(検索用キーワード)の自動生成機能も提供しており、FAQの検索ヒット率を向上させ、ユーザーが必要な情報をより簡単に見つけられるようサポートします。
社内ナレッジ活用はデコールFAQ Makerにお任せ!
暗黙知と形式知の違いを理解し、FAQシステムを活用することで、効果的な社内ナレッジ活用が可能になります。デコールFAQ Makerは、AIの力を借りてこのプロセスを効率化し、組織全体の知識共有を促進します。
また、デコールFAQ Makerは約60か国語の多言語に対応したFAQコンテンツを効率的に作成できるため、グローバル企業やグローバルユーザーに向けたFAQ構築を支援します。
さらに、コールセンター向けCRMシステムにデコールFAQ MakerのAI機能を組み込み、音声テキストや応対ログからFAQを自動で作成する機能を提供する予定です。さらに、AI技術を活用して瞬時に適切な回答を提供し、業務効率化を実現するとともに、企業固有のナレッジを活用できる企業向けのAIチャットツールの提供も計画しています。
デコールFAQ Makerは、組織の知識管理を革新し、業務効率を大幅に向上させる強力なツールです。暗黙知の形式知化と効果的な共有を実現し、組織全体の生産性向上に貢献します。






