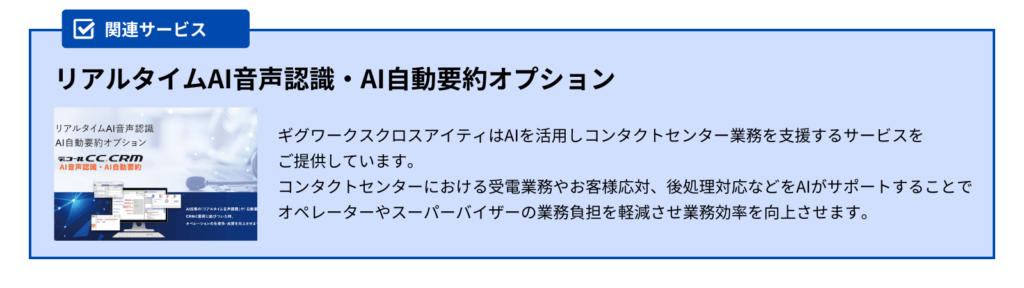近年、顧客接点が多様化する中で、チャネルを跨いだ一貫性のある顧客体験の提供が企業競争力の重要な要素となっています。デコールCC.CRMは、電話、メール、チャット、SNSなど多様なチャネルを一元管理する「オムニチャネル対応」を実現するCRMプラットフォームです。本記事では、デコールCC.CRMのオムニチャネル機能の詳細と、クロスチャネル分析による顧客行動の可視化および最適化のヒントを解説します。
【関連記事】マルチテナント&CTI連携で顧客対応を効率化!デコールCC.CRMの強みとは
デコールCC.CRMのオムニチャネル機能
デコールCC.CRMは、コールセンター業務に求められる多様な顧客接点を一元的に管理できるプラットフォームです。オムニチャネル対応を実現し、電話、メール、FAX、Webフォーム、チャット、ビデオ通話など、さまざまなチャネルからの問い合わせに対して、どのチャネルでも質の高い対応ができるのが大きな特徴です。チャネルを問わず一貫性のある顧客対応を実現することで、顧客満足度の向上を強力に支援します。
マルチチャネル対応
企業の顧客対応は、もはや電話だけにとどまりません。デコールCC.CRMでは、メール、FAX、Webフォーム、SMS、チャットなど、多様なチャネルを横断して顧客情報や対応履歴を一元管理できます。これにより、オペレーター同士の情報共有が円滑となり、対応漏れや情報の断絶を防止します。あらゆる顧客接点を一画面で把握できる環境を実現します。
マルチベンダーCTI連携
従来のPBXやIP電話システムに加え、さまざまなCTI(コンピュータ電話統合)環境とも柔軟に連携できる点も魅力です。クラウド型・オンプレミス型を問わず導入でき、既存資産を生かした効率的な運用が可能です。これにより、新旧設備の混在する現場にも無理なく導入できる柔軟性を確保しています。
セルフカスタマイズ機能
入力項目や帳票、オペレーション画面のスクリプト表示などをユーザー自身がカスタマイズできるため、現場の業務フローや運用ルールに最適化できます。カスタマイズ性の高さは、迅速な業務改善や運用定着に直結する強みです。
多言語・マルチテナント機能
グローバル対応にも万全で、日本語・中国語・英語・韓国語に対応可能。一つのシステムで複数拠点や部門の管理もできるマルチテナント機能を提供し、運用方式も専有型・共有型から選択できます。これにより、さまざまな規模や業態のコールセンターで導入しやすい仕組みとなっています。
CRM連携とFAQ自動表示
CRM(顧客管理)との連携により、電話着信時に自動的に顧客情報を呼び出して画面展開できる「クリックトゥコール」や、FAQを自動検索・表示する機能を搭載。オペレーターはスムーズかつ迅速に適切な対応ができ、回答精度と納期短縮を両立します。
従業員満足度の可視化
「ごきげんカウンター」機能により、オペレーターのモチベーションやストレス状態をスタンプやヒートマップで把握できます。離職予兆の早期察知や、職場改善にも活用されています。
デコールCC.CRMは単なる問い合わせ管理ではなく、顧客満足度(CS)と従業員満足度(ES)を同時に高めるCRMソリューションです。現場の運用効率を高めながら、分析や経営判断に資する仕組みも充実しています。
マルチチャネルに対応したコールセンター基盤が必要なときは、ぜひデコールCC.CRMをご検討ください。
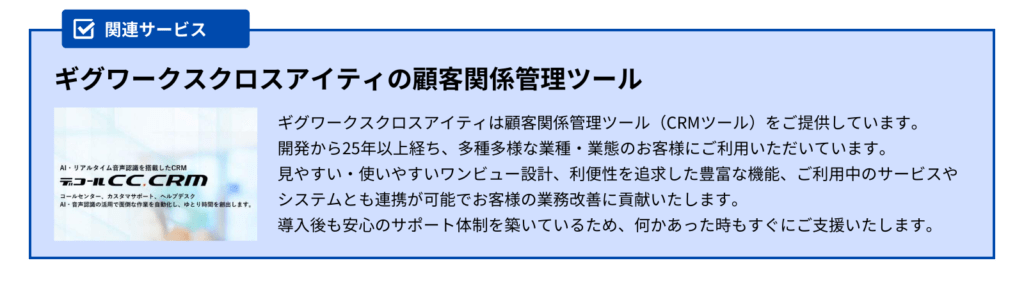
多様なチャネルを使い分ける!クロスチャネル分析とは

現代のビジネス環境では、顧客が企業と接点を持つチャネルが多様化し、その利用も一人の顧客が複数のチャネルを使い分けるのが当たり前となっています。ここでは、クロスチャネル分析の目的や具体的なステップ、手法について詳しく解説します。
クロスチャネル分析の重要性
現代の顧客は、電話、メール、FAX、Webフォーム、チャット、SNS、ビデオ通話など、多様なチャネルを自在に使い分けながら企業と接点を持つようになっています。このため、複数の顧客接点を持つことがスタンダードとなり、顧客ターゲットに合わせたカスタマーサポートやダイレクトセールスの最適化がますます重要となっています。
具体的には、若年層は主にスマートフォンを使いチャットやSNSを通じて問い合わせることが多いのに対し、シニア層は電話やFAXなど従来型のチャネルを好む傾向があります。さらに、小売業の例では、オンライン広告やECサイトでブランドを認知した顧客が、実店舗で商品を購入したり店頭で相談したりする行動パターンが見られます。このように、各チャネルごとに顧客の特性や行動が大きく異なり、チャネル単体の対応だけでは不十分です。企業はチャネル間の顧客の動きを正確に把握し、コミュニケーション設計やマーケティング施策を適切に最適化しなければなりません。
そこで必要になるのが、チャネルを横断した顧客データを統合的に分析する「クロスチャネル分析」です。これにより、
- どのチャネルが売上や顧客満足にどの程度貢献しているか把握できる
- 顧客がチャネルをまたいでどのような行動ルート(顧客ジャーニー)をたどっているか可視化できる
- 各顧客層がどのチャネルをどのように利用しているか分析できる
- オペレーターの教育や応対品質向上に役立つ示唆を得られる
など、経営層・現場双方にとって非常に有用な洞察を得ることができ、結果として顧客価値の最大化につながります。
クロスチャネル分析の主な目的
- 売上向上:各チャネルのパフォーマンスを正確に把握し、効果的なリソース配分やクロスセル・アップセルの機会を見つけて収益の最大化を目指します。
- 顧客満足度向上:チャネル間のシームレスな顧客体験を提供するとともに、一元管理された問い合わせ履歴を活用して迅速かつ的確な対応を実現します。
- オペレーターのトレーニングおよび応対品質向上:顧客の全体行動を把握したインサイトを踏まえた教育を施し、AI技術によるリアルタイムの応対支援システムと組み合わせて品質向上を図ります。
クロスチャネル分析のステップ
1. データ収集と統合
電話、メール、チャット、Webフォーム、SNSなど、すべての顧客接点チャネルからの対応データを収集します。そして、顧客IDを共通キーにして情報を統合。データの誤りや重複を取り除くデータクレンジングも行い、分析準備を整えます。
2. 顧客ジャーニーの可視化
集めたデータを基に、顧客がどのチャネルをどの順序で利用しているかを時間軸に沿ってマッピング。これにより顧客の行動パターンや接点の流れが直感的に把握できます。
3. チャネル性能の評価
対応時間、問題解決率、顧客満足度などのKPI(重要業績評価指標)を用いて、各チャネルの対応状況や効果を比較検証します。
4. セグメンテーションと行動分析
顧客をチャネル利用傾向でグループ化し、各グループの特徴やニーズ、好みの傾向を詳細に分析します。
5. 予測モデルの構築
機械学習やAI技術を活用し、顧客の次のアクションや最も効果的なチャネルの予測、さらには顧客生涯価値(LTV)の推定を行います。
6. インサイト抽出と戦略立案
得られた分析結果からビジネス課題を特定し、売上最大化や顧客体験向上のための具体的な施策や改善戦略を策定します。
7. 実行とモニタリング
立案した施策を実行し、その効果を継続的に計測。さらにデータを収集しPDCAサイクルを回しながら改善を繰り返します。
クロスチャネル分析の具体的手法
- ETLツールやデータレイクの活用:多様なデータソースから必要なデータを抽出・変換・統合し、蓄積・加工することで分析基盤を整備します。
- カスタマージャーニーマッピングツールやサンキーダイアグラム:顧客の行動やチャネル間の移動を視覚的に表現し、理解と改善を助けます。
- アトリビューション分析やマルチチャネルファネル分析:どのチャネルがどの程度の効果を発揮しているかを定量的に評価し、チャネルごとの貢献度を明らかにします。
- クラスタリングやRFM分析:顧客の購入履歴や利用頻度、直近の利用状況からセグメントを作成し、効果的なアプローチを検討します。
- 機械学習アルゴリズム(ランダムフォレスト、勾配ブースティングなど)やディープラーニング:データの複雑なパターン認識により、行動予測や顧客の価値評価を高精度に行います。
クロスチャネル分析は、単に複数のチャネルを利用するだけでなく、それらを連携させ、顧客の行動全体を把握・分析することで、より高度なマーケティング戦略や顧客対応を可能にします。今後も顧客接点の多様化が進む中で、クロスチャネル分析は企業にとって欠かせない重要な手法となるでしょう。
マルチチャネルで作る新たな顧客体験:美容品メーカーの場合
ここでは、多様なチャネルを連携させたマルチチャネル基盤を構築し、クロスチャネル分析を活用した美容品メーカーC社の事例について詳しくご紹介します。顧客の多様な接点に最適な対応を行い、新たな顧客層の発見とカスタマージャーニーの改善を実現した取り組みです。
C社の課題とマルチチャネル戦略
現代の美容業界では、オンラインとオフラインの両方で顧客接点が多様化しています。顧客の購買行動が複数のチャネルにまたがり複雑化する中、顧客一人ひとりに合わせて一貫性のある最適な顧客体験を提供することがブランドの競争力に直結しています。 C社はこの課題を解決するために、複数チャネルを統合するマルチチャネル基盤の構築とクロスチャネル分析の導入を進めました。
顧客ターゲットの検討からペルソナ設定へ
C社は、既存顧客の購買履歴や行動データを詳細に分析し、働く女性(25~40歳)を主なターゲット層に設定しました。将来的な市場拡大を見据え、シニア層や若年男性も潜在顧客としてペルソナを策定しています。各ターゲット層のチャネル利用傾向と購買動機に合わせて戦略を立てました。
- 働く女性層:スマートフォンを使ったチャットやSNSによるコミュニケーションを重視。
- シニア層:電話や実店舗での対面サポートを重視する。
- 若年男性層:InstagramやLINEなどのSNSを活用し、直接的なアプローチを展開する。
マルチチャネル基盤の構築と情報統合
C社は、公式WebサイトやECサイト、電話窓口、チャットサポート、InstagramやLINEといったSNS、さらに全国の実店舗の情報を一元管理する基盤を構築しました。
この基盤により、顧客の接点情報、購買履歴、問い合わせ内容などのデータを統合し、オペレーターやマーケターがリアルタイムで共有できる環境を整備しました。
これにより、例えばECで商品を閲覧後にInstagramのDMで質問し、実店舗で購入するまでの複雑な行動にも一貫した対応とパーソナライズが可能となりました。
クロスチャネル分析による顧客行動の可視化
C社は構築した基盤を用いて、クロスチャネル分析を行いました。
- ジャーニーマッピングツールを用いて、顧客がどのチャネルをどの順序で利用しているかを視覚的に分析。
- チャネルごとのコンバージョン率や顧客満足度の評価によって強化すべきチャネルと改善すべき箇所を抽出。
- 顧客属性ごとの行動パターン分析を行い、各セグメントごとに最も効果的なチャネルを特定しました。
例えばInstagramでの商品閲覧後、ECでの購入、LINE経由のアフターケア問い合わせが増えていることが確認されたため、チャネル間連携の強化とタイムリーな情報提供を進めています。
ケーススタディから学ぶカスタマージャーニーの最適化戦略
C社の事例は、カスタマージャーニー最適化における重要なポイントを示しています。まず、顧客ターゲットの明確な設定と詳細なペルソナ設計が不可欠です。C社は、年齢や性別に加えて、ライフスタイルやチャネル利用傾向、購買動機まで分析し、適切なコミュニケーション施策を設計しました。
次に、顧客のタッチポイントを包括的に洗い出し、ジャーニーマップで時系列に可視化することで、どのチャネルで離脱や不満が生じやすいかを把握しました。これにより、ECサイトのUI改善やチャネル間連携強化など解決すべき課題が明らかになっています。
また、多様な顧客フィードバックを活用し、各フェーズのKPIを設定して効果測定と改善を迅速に回す体制も重要です。C社は、顧客満足度やコンバージョン率、リピート率などを数値化し、施策の科学的な評価を実現しました。
さらに、OMO(Online Merges with Offline)戦略により、オンラインとオフライン間で一貫性のある顧客体験を保証する施策が成功の鍵となっています。たとえば、SNSで得た情報を実店舗スタッフが共有し、個別接客に活かすことで、途切れのないシームレスな体験を提供しています。
そして、現代のマーケティングに不可欠な要素として、AIや機械学習を活用した顧客行動予測や「次に取るべき最適なアクション(Next-Best Action)」の自動提案が挙げられます。 C社はCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を導入し、ビッグデータを駆使した分析で、マーケティング施策の精度とスピードを大幅に向上させています。
最後に、継続的なPDCAサイクルの高速運用により、施策の効果を常に検証し、変化に応じて柔軟に対応する組織体制も構築されていることが、持続的な成長の基盤となっています。
C社の事例は、多様なチャネルを統合し、顧客一人ひとりに最適化された体験を提供することの重要性を示しています。AIを活用した高度な分析や継続的な改善によって、変化する市場環境に柔軟に対応し続ける力が競争優位性を支えています。今後もこうした統合的なアプローチが、ビジネス成長の鍵となるでしょう。
現代のビジネスに求められるオムニチャネル戦略

現代のビジネス環境では、多様なチャネルを統合し、顧客一人ひとりに対して最適化された顧客体験を提供することが重要です。ペルソナやカスタマージャーニーマップにより顧客行動を可視化し、チャネル間の連携強化やカスタマーサポートの質の向上につなげることが有効です。またAIと機械学習を活用した顧客行動予測も注目されています。
デコールCC.CRMは、電話、メール、チャット、SNSなど多様なチャネルを一元管理し、一貫したオムニチャネル対応を実現するCRMプラットフォームです。顧客満足度向上と業務効率化を両立させる強力なツールとして、ぜひご検討ください。
こうした課題は、デコールCC.CRMのマルチテナント化する顧客ニーズと多様な組織体制に対応しながら、企業の顧客接点強化を確実に後押しします。