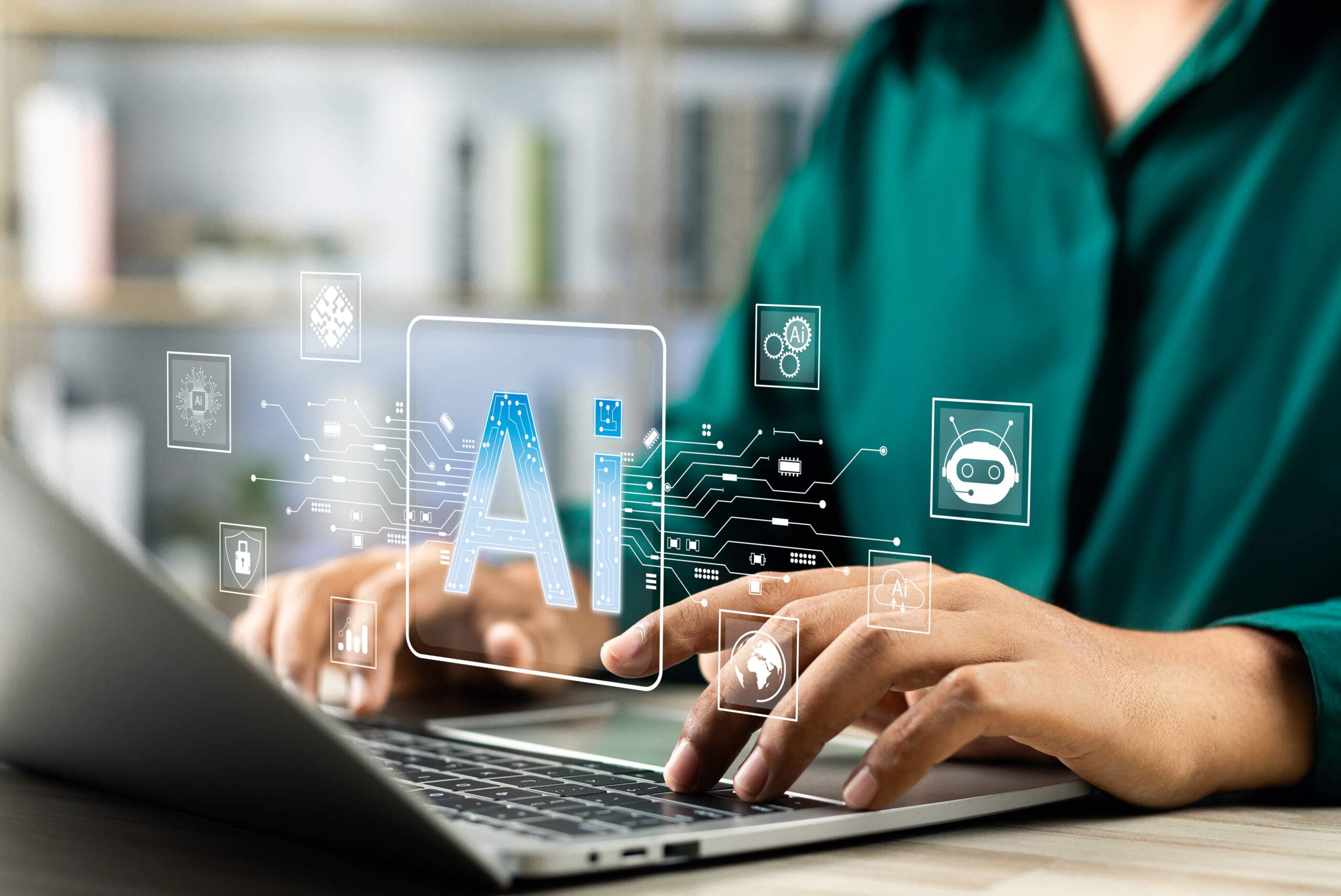デジタル化が進む現代において、中堅・中小企業もAI技術の活用が経営や業務効率化に不可欠となっています。しかし、人材やリソースが限られる中で、AI導入が思うように進まない企業も多いのが現状です。特に「既存の人材が十分にAIを活用できていない」ことが大きな課題として浮かび上がっています。
本記事では、健康食品や化粧品の定期通販を手掛けるB社の事例を通じて、AIリテラシーの可視化と現場主導の育成に取り組んだ実践例を紹介します。さらに、中堅・中小企業全般に共通するAI活用の課題と、その解決に向けた具体的なポイントを整理しました。AIを単なるツールとして導入するのではなく、既存人材の能力を最大限に引き出すことで、着実なDX推進につなげるためのヒントとしてご活用ください。
【関連記事】「AI理解度チェック」導入事例紹介:AIリテラシー底上げプロジェクト

通販事業者におけるAI理解度チェック導入事例
健康食品や化粧品の定期通販を展開しているB社は、従業員約150名を擁し、受電対応とアウトバウンドを融合したハイブリッド型コールセンターの運営に注力しています。変化する顧客接点への対応強化と業務効率化、品質向上を目指して、AI理解度の可視化に取り組まれました。
課題認識:多様化するチャネル対応とAI導入時の壁
B社では電話に加え、LINEやチャットといった多様な問い合わせチャネルが増加。その結果、特に現場の人手不足が深刻な影響を与え、対応負荷が増大していました。AIチャットボットやFAQの自動応答といったAI導入が検討される一方で、現場の理解不足と不安感が大きな障壁となり、特にリーダー層での業務適用方針が曖昧なため、導入が進まない状況に陥っていました。
導入のきっかけと取り組み内容
この状況を受け、B社の人材開発チームはまず現場のAIリテラシーを客観的に把握することを決定。外部の「AI理解度チェック」ツールを試験的に管理職5名で受検し、その結果を踏まえ約50名のコールセンタースタッフ全体へ適用範囲を拡大しました。
テスト結果の可視化と課題発見
受検結果はレーダーチャートやカテゴリ別スコアで詳細に可視化され、基礎的な知識の差と実践スキルの遅れが明確になりました。生成AIの基礎は比較的理解が進んでいる一方、実務での応用や適切なプロンプト設計など実践領域に課題があることが浮き彫りに。これらの洞察をもとに、人材開発チームは教育プログラムの再設計を実施しました。
現場への波及効果と組織の変化
結果共有により、「理解不足の要因」や「フォロー方法」の議論が活性化。特にスーパーバイザー層のAI活用意識が高まり、自発的な勉強会開催など現場主導の学習文化が創出されました。AIに詳しい人材が相談窓口として信頼を集めることでチーム内の連携が強化され、心理的な障壁が軽減。部署全体の雰囲気が明るくなったことも大きな成果です。
今後の展望と課題
B社は次のステップとして、AIを活かした具体的な業務改善策の実行に取り組む方針です。単なるツール導入だけでなく、業務フローの再設計や現場環境に合わせた教育サイクルの構築に注力し、現場主導で持続的にAI活用スキルを高めていく計画です。
「AI理解度チェック」について、B社のご担当者様より以下のようなご感想を頂いています。
「このチェックによって現実のギャップが明確になり、社員の育成施策を立てる土台となりました。無料でここまで具体的な分析ができるサービスは珍しいと思います。」
B社は、AI導入を単なるツール導入で終わらせることなく、現場の実態を客観的に把握して課題を明確化し、教育や業務改善へと着実に結びつけています。このプロセスは、中小企業のDX推進や営業現場でのAI活用を進める上で有効なモデルとなるでしょう。
既存人材活用が鍵!中堅・中小企業のAI活用の課題とは

中堅・中小企業におけるAI導入は、単なるツールの導入や技術検証で終わることが少なくありません。多くの企業が導入の一歩目でつまづくのは、現場の実態把握とスキル不足の課題です。B社の事例は、その課題と向き合い、既存人材のAIリテラシーを正しく評価・育成することで着実に成果を上げている好例です。
AI活用が進まない背景にある現場の課題
中堅・中小企業では人員体制が限られており、人材の入れ替わりや外部採用が難しいことから、新たにAI人材を大量に確保するのは困難です。また、多様化する業務・顧客対応チャネルに従業員が追われ、AI活用の検証やスキル向上に時間を割く余裕も限られます。
このため、単にAIツールを導入しても「どう使っていいかわからない」「効果が感じられない」という状態に陥りやすく、現場の不安や抵抗感が根強く残ってしまいます。
既存人材のAIスキル評価と教育がスタートライン
B社の「AI理解度チェック」による取り組みが示しているように、まずは既存の社員が持つAIの知識とスキルを客観的に測り、それをベースに育成プランを設計することが重要です。
単なる知識の有無だけでなく、実践的に活用できるスキルの有無を可視化することで、現場の具体的なギャップを把握しやすくなります。
中堅・中小企業のAI活用を妨げるポイント
- AI理解度に個人差が大きい:担当者のAI知識や経験にばらつきがあると、部署間やチーム内での足並みが揃いません。結果的にAI活用の定着が遅れます。
- リーダー層のリテラシー不足で推進力が弱い:意思決定層や管理職がAIの実務的な利活用方法を理解していない場合、導入方針が不透明になり、現場に落とし込めません。
- 教育やフォロー体制が未整備:スキルや理解不足の社員を支援する学びの場が十分でなければ、AI活用への心理的な障壁が高いままとなります。
既存人材活用で進めるAI活用のポイント
- 現状把握から始める:客観的な理解度チェックで個人・部署ごとの課題を明確にしましょう。
- リーダー層の理解を深める:管理職が主体的にAIに取り組み、現場推進のキーマンとなることが重要です。具体的には、研修やワークショップの開催によりスキルと意識の底上げを図るとともに、政策決定や導入方針の策定段階に経営層を積極的に巻き込むことが推進力強化につながります。
- 現場主導の学習文化をつくる:社内勉強会や共有会を通じて、AIに詳しいメンバーが相談役になり、助け合いながら成長できる環境を醸成することが重要です。必要に応じて外部セミナー利用も検討しましょう。
- 業務改善を目的に活用を進める:単にツール導入だけで終わらせず、業務フローの見直しや運用ルールの策定など具体的なAI活用シーンを作ることが定着の鍵です。
中堅・中小企業におけるAI活用の最大の課題は、限られた既存人材のスキル・理解度のばらつきとリーダー層の推進力不足にあります。
B社様の事例が示すように、既存社員のAIリテラシーを正しく「見える化」し、現実のギャップに即した教育と現場主導の学習体制を整備することが、成功のカギです。
これにより、単なる技術導入ではなく、着実な業務改善と組織の成長へとつなげることが可能となります。
「AI理解度チェック」がリニューアル!

ギグワークスクロスアイティが提供する「AI理解度チェック」がバージョンアップし、「生成AIの理解度」や「実務で使える知識が身についているかどうか」をより正確にチェックできるようになりました。全30問の選択式テストで構成され、単一回答・複数回答形式を取り入れながら、具体的な業務活用事例や生成AIの活用シーンを題材にした設問、さらに現場でつまずきやすい実務的な問題を通じて、受検者のAIリテラシーの実用性を可視化します。
単なる基礎知識のチェックにとどまらず、AIの理解が実際の業務遂行にどの程度役立つかを測るため、「わかったつもり」から「使える知識」へとレベルを明確に区別。これにより、企業は部署や個人ごとの弱点を具体的に把握し、的確な研修や育成プランを設計できます。
所要時間は15分から30分程度と短時間で受検でき、回答後にはカテゴリー別の詳細なスコアを含むレポートをメールで受け取れるため、現状分析と次のアクションがスムーズに進みます。また、一定数のご希望には無料での個別診断も提供しており、多くの中小企業やDX推進担当者に気軽に活用いただけるサービスです。
こんな方におすすめ
- 中小企業の経営者の方
- DX推進やAI活用担当者、情報システム部門のご担当者
- 営業現場での業務改善や提案支援にAIを活用したい営業職の方
まずは「自身のAI知識」を見える化し、現場で使えるAIリテラシーへ一歩踏み出してみませんか?