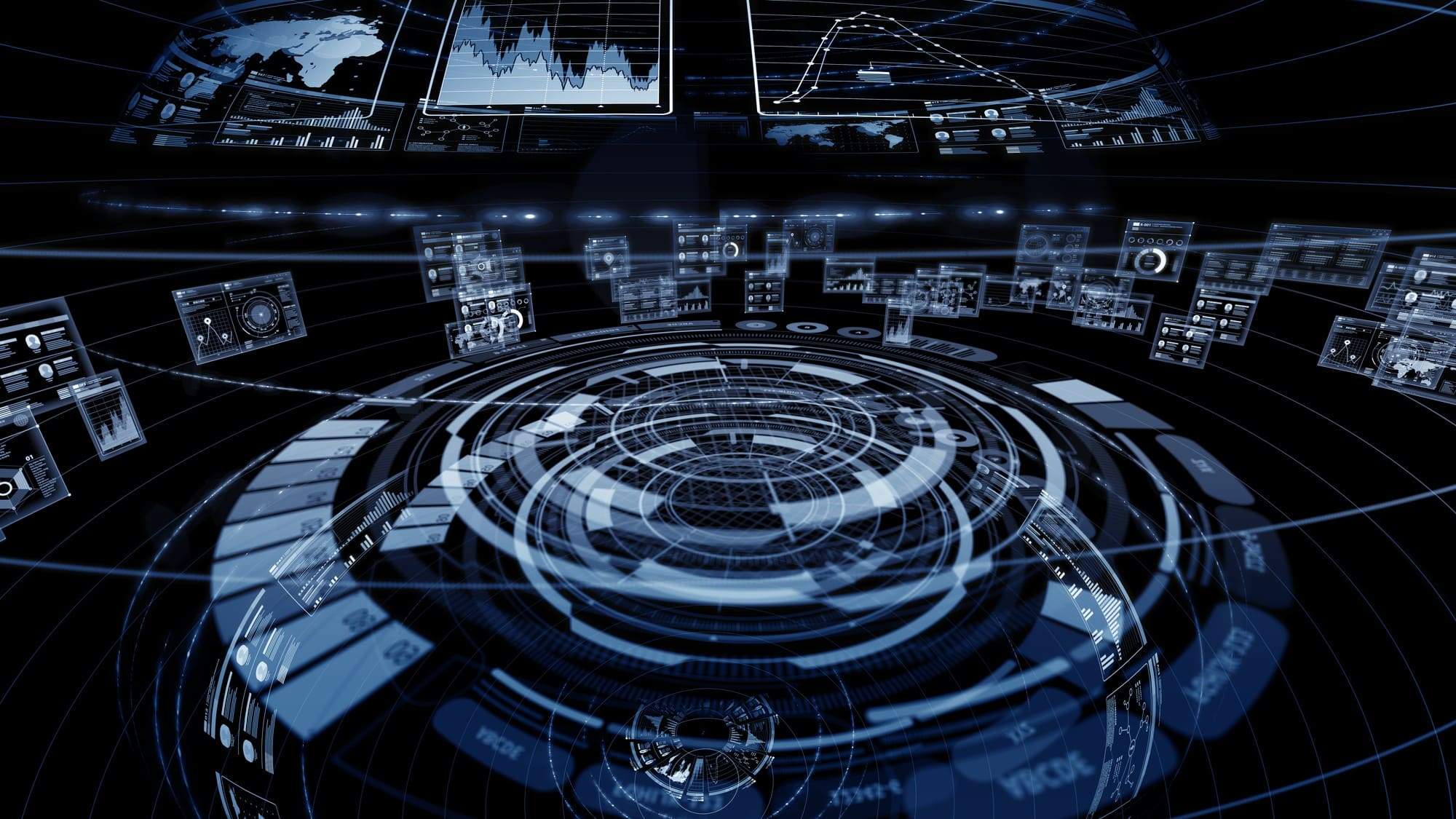オンラインゲームの新たな経済モデルとして近年注目を浴びた「P2E(Play to Earn)」は、プレイヤーがゲームを遊びながら暗号資産やNFTなどを獲得し、収益化できる仕組みです。しかし、その構造的な課題から持続性の問題が浮上し、次世代のモデルとして「プレイアンドオウン(Play and Own)」が期待されています。プレイヤーが純粋にゲームを楽しみつつ、得たデジタル資産を自分のものとして本当に所有できるという考え方は、ゲーム経済の新たな進化を示しています。
【関連記事】【2025年最新版】成熟期を迎えたDeFi市場の特徴と動向

P2Eからプレイアンドオウンへ
オンラインゲームの世界では、この数年で「P2E(Play to Earn)」という新しい概念が注目を集めてきました。これはゲームをプレイしながら暗号資産やNFTなどの報酬を得る仕組みですが、その一方で持続性やプレイヤーのモチベーションに課題が浮き彫りになっています。近年では、こうした問題点を補うかたちで「プレイアンドオウン(Play and Own)」という新しいアプローチが提案されています。プレイヤーが楽しみながら、デジタル資産を真に自分のものとして所有できるという考え方が、次の進化の方向性として注目されているのです。
P2E(Play to Earn)とは
P2Eとは「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」の略語で、ゲームプレイを通じて報酬を得る仕組みを指します。 この報酬には暗号資産(仮想通貨)やNFT(Non-Fungible Token:代替不可能なトークン)が含まれ、プレイヤーは獲得したデジタル資産を仮想通貨取引所を通じて現実世界の通貨へ換金することができます。ブロックチェーン技術が基盤となっているため、資産の透明性や取引履歴の検証可能性が担保されます。
- 魅力:ゲームをしながら収入を得られる、従来の娯楽とは違う体験を提供する。
- 仕組み:プレイで得たアイテムや通貨がNFT化され、プレイヤー間で売買可能になる。
- 透明性:ブロックチェーンにより、所有権の不正や改ざんリスクが低減される。
この仕組みは新興国を中心に大きな広がりを見せ、一部の人々にとっては重要な収入源となりました。しかし同時に、報酬性に依存したゲームデザインゆえの限界が顕在化しているのも事実です。
P2Eの限界と市場の課題
P2Eモデルは一時的な盛り上がりを見せたものの、長期的には大きな障害に直面しました。プレイヤーの多くが「遊ぶこと」ではなく「稼ぐこと」を目的とするため、ゲームの楽しさそのものが軽視されがちになったのです。「ゲームを仕事のようにこなす」状態に陥りやすく、ユーザーの継続率が低下する傾向が見られました。
- ユーザー離脱:収益が減少するとモチベーションも低下し、継続的に遊ぶプレイヤーが減少する。
- 市場の不安定さ:暗号資産価格は変動性が大きいため、ゲーム内経済は安定しづらい。
- 投機化のリスク:SNSや投資家の影響でプレイヤーが投機目的で参入し、ゲームバランスが崩壊するケースもある。
結果として、短期的な熱狂に終わり長期的なコミュニティ形成が難しいことが課題視されています。
プレイアンドオウン(Play and Own)とは
こうした課題に対応する新しい流れが、「プレイアンドオウン(Play and Own)」です。これは、ゲームを楽しむことを主体にしながら、自分が手に入れたアイテムを「所有できる」点に重きを置く考え方です。P2Eでは稼ぐことが中心にありましたが、プレイアンドオウンは「遊び」と「所有」を両立させる点で異なります。
- 定義:プレイヤーは楽しみの延長線上で獲得したアイテムや成果物をデジタル資産として所有できる。
- 特徴:遊びを第一に置きつつ、付加価値としてブロックチェーンによる所有権証明を得られる。
- 付加的価値:所有物はゲーム外でも展示・取引できるほか、報酬としてギフトカードや実物特典が用意される場合もある。
この形態は、ゲームプレイによる「体験価値」を尊重しながら、その過程で得られる資産が確かな所有物であることを保証します。稼ぐために遊ぶのではなく、遊んだ結果が資産として残るという発想の転換がポイントです。
プレイアンドオウンは、P2Eの限界を補いながらプレイヤーにより自然で持続可能な喜びを提供しようとしています。ゲーム業界において今後ますます重視されるのは、「楽しさ」と「所有体験」の両立と言えるでしょう。

なぜ注目されている?プレイアンドオウンが実現する経済モデルとは

自分が本当に好きなゲームを楽しみながら、そこで手に入れたものを自分の所有物として大切にできる少し新しい考え方。それが、多くのゲームファンや開発者から期待されている理由です。
ここでは、具体的な事例を通じてその仕組みとメリットを分かりやすく解説します。
プレイアンドオウンの具体的なゲーム事例
ここでは、プレイアンドオウンの考え方が実際にどのように活用されているかを代表的なゲームを通じて見ていきましょう。
Axie Infinity(アクシー・インフィニティ)
もともとはP2Eの代表的なタイトルですが、単に「稼ぐ」ためのゲームにとどまらず、プレイヤーがクリーチャーを育成し愛着を持てる仕組みが組み込まれています。キャラクターやアイテムはNFTとしてブロックチェーン上に記録され、プレイヤーが真の所有者となります。 また、プレイヤー同士の助け合いやコミュニティ活動が活発で、Play and Own的な持続的プレイ体験に発展している点が特徴です。
Illuvium(イルビアム)
美しいグラフィックとRPG要素を兼ね備えたゲームで、ゲーム内モンスターやアイテムはNFTとして所有可能です。希少価値が明確に提示されることで、プレイヤーは「遊び」を超えた収集と所有の楽しさを実感できます。ゲーム体験の魅力とデジタル資産の所有価値が自然に結びついた代表的成功例といえます。
The Sandbox(ザ・サンドボックス)
ブロックチェーンを土台とした仮想世界プラットフォームで、土地や建物、アイテムをユーザーがNFTとして所有し、自由に売買・利用できる点が大きな特徴です。プレイヤー自身が創造活動やコミュニティ形成に参加でき、所有するものが現実的な資産価値を持つという「Play and Own」の中核を体現しています。
これらのゲームはいずれも、資産や報酬を「持続的に所有できる価値」として提示し、プレイヤーの満足度向上と長期的な参加を支える仕組みを実現しています。
プレイアンドオウンの経済モデル
プレイアンドオウンは多くの人がゲームを長く楽しみ続けることを目指したモデルです。従来のP2Eには、簡単に言うと「遊ぶことでお金がもらえるけど、続けにくい」という問題がありました。理由は次の通りです。
ゲームが「仕事」のようになってしまう
P2Eでは「いかに稼ぐか」が最重要になり、ゲームの楽しさが薄れがちでした。お金を稼ぐために、同じ作業を延々と繰り返す必要があり、これは誰にとっても楽しい体験とは言い難い点です。
収益の変動が大きく予測しにくいこと
暗号資産などの価値が変わりやすいため、稼げる額も増減しやすいです。収入がいつ減ってもおかしくないことは、ゲームを続ける不安要素です。
コミュニティの継続性に影響する
短期間で離脱するプレイヤーが多くなると、ゲーム内のコミュニティも弱くなります。強いコミュニティがあるゲームほど、長続きしやすい傾向があります。
プレイアンドオウンはこれらの問題に対し、以下のようにアプローチしています。
「遊ぶ楽しさ」を重視する
稼ぐためだけでなく、ゲーム体験やストーリー、仲間と遊ぶことそのものが楽しい設計です。これは多くのゲーム好きにとって極めて大切なポイントです。
「所有する喜び」を提供
ゲーム内で得たアイテムやキャラクターがNFTなどのデジタル資産としてユーザーのもとに残り、単に借り物ではない「本物の持ち物」としての価値を持ちます。これによりプレイヤーはゲームを通じて積み重ねた成果を実感しやすくなります。
多様な報酬と安定性の追求
暗号資産だけでなく、ゲーム外でも利用可能なギフトカードや特典も用意され、収益が一方向に偏らず安定的な仕組みを作りやすいです。
既存ゲーム開発との親和性
従来のゲームでは課金やコミュニティ重視の仕組みがありましたが、プレイアンドオウンはこれらと融合しやすいため、開発者にとって導入が比較的スムーズです。
つまり、プレイアンドオウンは「持続可能で楽しいゲーム経済」を実現する新しいスタンダードになりつつあります。
まとめ:プレイアンドオウンが注目されている理由
- プレイヤーがゲームを長く楽しめる仕組みを提供
- 投機的な側面を抑え、健全で安定したゲーム経済を実現
- ゲームプレイの楽しさと所有する喜びを両立
- 多様な報酬システムで収益の安定化を図れる
- 既存のゲーム開発者、プラットフォームと相性が良い
2025年のブロックチェーンビジネス
2025年は、ブロックチェーンが「ビジネスの成熟」と「実装の拡大」を明確に示した年となりました。暗号資産バブルの影響で「投機的」というイメージが先行していた時代を経て、現在は実用的なソリューションとしての価値が重視されています。本稿では、新サービスの動向、各国の政策変化、そしてステーブルコインの活用拡大について整理します。
新サービスとプレスリリースから見るブロックチェーンの進化
2025年は大小さまざまな企業がブロックチェーンを応用した新サービスを発表し、具体的な実装が加速しました。かつては技術的なショーケース色が強かった発表も、実生活や既存市場に直結する形へとシフトしています。
大手ゲーム会社のWeb3参入
国内外の大手ゲームメーカーが「Play and Own」型の新作タイトルを続々発表。NFT化されたキャラクターやアイテムをゲーム内外で自由に利用できる設計を採用し、所有の実感を重視しています。公式リリースでは「収益モデルではなくプレイヤー体験の拡張」を強調し、過度な投機性を抑える工夫も施されています。
物流・小売業での導入加速
世界的に有名な米ウォルマートとIBMが共同開発した「IBM Food Trust」プラットフォームでは、農場から店舗までの食品履歴を2.2秒で追跡可能です。
また、日本でもNTTデータが政府の支援を受け推進する「スマートフードチェーン」プロジェクトにより農産物の輸送温度や製造過程の情報がブロックチェーンに蓄積され、消費者がQRコードで詳細を確認できるようになっています。
さらに、日本通運(Nippon Express)はアクセンチュアやインテルと連携し、ブロックチェーンを使った輸送網の品質管理強化に取り組んでいます
これらはトレーサビリティと品質管理を通じて消費者の信頼向上に貢献しつつ、物流効率化も進む革新的取り組みです。
クラウド事業者の取り組み
AWSやGoogle Cloud、国内クラウドサービス業者が「ブロックチェーン証跡管理サービス」を展開。契約書類や監査ログを改ざん困難な形で安全に保管でき、企業の情報セキュリティ強化に役立っています。
こうした動きは、ブロックチェーンが企業ITインフラの基盤技術として定着しつつあることを示しています。
米国の政策転換と各国規制緩和の影響
2025年、ブロックチェーン産業の成長を支える大きな追い風となったのが規制面の変化です。
米国SECの新ガイドライン
米証券取引委員会(SEC)は、「ユーティリティトークン」と「証券性トークン」を明確に区別し、規制対象を明確化しました。これによりDeFiやGameFiを含む多くの事業者が米国市場に進出しやすくなっています。
欧州の規制整備
欧州連合は2024年に発効したMiCA規制を改訂し、透明性と消費者保護を追求しつつ、金融機関のデジタル資産業務参入を促進しています。
特に、フランスやドイツの大手銀行がデジタル資産カストディサービスを正式に開始し、制度と市場が連動した発展を遂げています。
アジアの動向
日本・シンガポール・韓国は、ブロックチェーンを国内産業の競争力強化策と位置づけ、規制サンドボックス制度を活用した実証実験を活発化。
日本では金融庁による取引所規制緩和やステーブルコイン・トークン証券に関するガイドライン整備が進み、国内事業者の市場参入障壁が低下しています。
これらの措置は、規制が「制約」から「産業成長の支え」へと変わったことを示しています。
ステーブルコインの広がりと日本での活用
2025年、特に注目されているのが価格変動を抑えたステーブルコインです。法定通貨に価値が連動し、日常決済や送金に適しています。
米国での活用事例
ドル連動のステーブルコインはBtoBの国際貿易決済に広く利用され、数日に及ぶ決済時間を数分に短縮しました。JPモルガンなど大手金融機関がネットワークで採用し、既存金融と連携した実用的金融基盤に成長しています。
欧州での活用事例
ユーロ連動のステーブルコインは小売店での決済に広がり、観光地では「両替不要の越境キャッシュレス決済」として利便性を高めています。
日本での活用事例
日本では2023年の資金決済法改正後、三菱UFJ銀行などメガバンクが円建てステーブルコインの発行実験・商用化を開始し、ECや地域送金での利用が進行中です。
これにより暗号資産は「投機」から「日常利用」へと大きく進化しました。
ステーブルコインはNFTマーケットやゲーム内経済、国際オンライン取引の経済基盤としても不可欠な存在となっており、2025年の成長を支える要素です。
まとめ
2025年のブロックチェーンビジネスは、投機的な盛衰を脱して、新しい実用的サービスの登場、規制緩和、ステーブルコインの普及によって着実に現実社会に根を下ろしつつあります。
- 大手企業リリースが示すように、ブロックチェーンは技術から「実生活に結びつく手段」へ変化。
- 米国・欧州の規制転換が市場参入の後押しとなりグローバル展開を促進。
- ステーブルコインが日常に浸透し、日本でも円建て利用が具体化。
この流れは、今後数年で「社会インフラとしてのブロックチェーン」を支える礎となるでしょう。2025年は未来のインターネット経済を支える重要な転換点と記憶されるに違いありません。
「楽しさ」と「所有の喜び」の両立

P2Eの経験を踏まえた上で台頭したプレイアンドオウンは、ゲームの「楽しさ」と「所有の喜び」を両立させ、長期的なプレイヤーの維持と健全なゲーム内経済の実現を可能にしています。
- プレイヤーのモチベーションを持続させる「楽しみ」と「所有」の両立
- 投機性や短期的収益依存のリスクを抑えた安定的なゲーム経済の構築
- 既存ゲーム開発者への受け入れやすさも考慮された設計
ゲーム産業はこの新たなモデルを武器に、更なる進化と多様化を遂げていくでしょう。これからのブロックチェーンゲームがどう進むかに、多くのゲームファンやクリエイターの期待が集まっています。