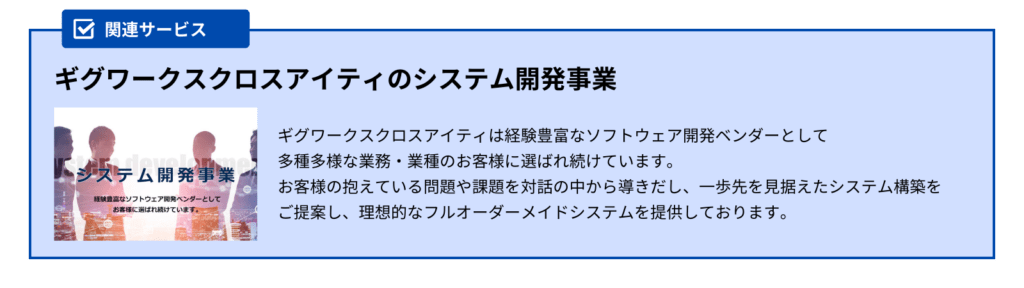企業システムの裏側では、気づかないうちにレガシー化が進んでいます。ERPや販売管理といった基幹システムでは、トラブル対応が長引いたり、刷新の計画が思うように進まなかったりするケースが目立っています。「今のままで十分」と現状維持を続けてきた結果、気づけば環境変化に追いつけない構造になってしまった――そんな企業も少なくありません。本稿では、技術・組織・業務の三つの側面から、“レガシー化の本質”を分かりやすく掘り下げていきます。
【関連記事】【2025年最新版】OCR導入のベストプラクティスとは?
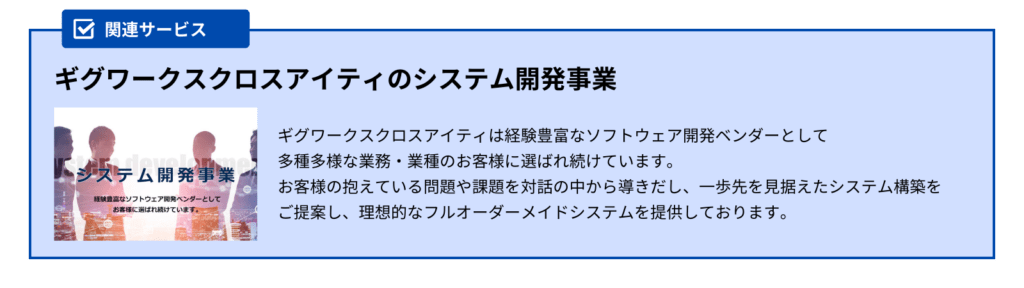
なぜ基幹システムは老朽化するのか
多くの企業で日々の業務を支える基幹システムは、長い年月を経て少しずつ維持管理が難しくなっていきます。新しい技術が次々と登場する一方で、既存システムは簡単に再構築できません。「なぜ老朽化が進むのか」を正しく理解することこそ、今後のシステム戦略の第一歩です。 ここでは、技術・組織・業務の3つの観点からその原因を整理します。
技術的要因:ベンダーサポート切れと開発環境の陳腐化
主要な技術基盤であるOS(オペレーティングシステム)やデータベース(DB)、開発フレームワークなどには、あらかじめサポート期間が設けられています。サポートが終了(EOL)するとセキュリティ更新や修正パッチが提供されず、継続利用がリスクとなります。例えば、Microsoftが旧バージョンのWindows Serverのサポートを終了するたびに、企業は移行計画を立てざるを得ません。
しかし、移行作業に必要なリソースや互換性検証の負荷が高いため、結果的に「現行のまま延命する」選択を取る企業が多いのが現状です。
- 古い開発言語の問題:COBOLやVB6といった旧言語は開発者の確保が難しく、新しいAPI連携に対応しづらいです。その結果、外部システムとの接続やクラウド移行が遅れてしまいます。
- ツールやライブラリの制約:かつて利用していたビルドツールや依存ライブラリが入手できなくなり、環境の再構築が不可能になるケースも少なくありません。
- ハードウェア依存性:オンプレミス(自社設置)環境では、ハードウェア故障が即システム停止につながるなど、運用リスクが高まります。
例えば、ある金融企業では数十年前に導入したシステムが古いCOBOLで動作しており、最新OSへの移行が困難な状況です。社内にはCOBOLエンジニアがほとんどおらず、結果として動かし続けざるを得ない状態が続いています。
こうした状況に対しては、一度の「リプレース」で終わらせるのではなく、継続的な再構築サイクルを業務プロセスに組み込む発想が求められます。クラウドサービスやコンテナ技術を活用し、部分的に刷新しながら維持する方法が現実的な選択肢となっています。
組織的要因:人材不足と属人化の連鎖
技術的な課題と並んで深刻なのが、人材面での問題です。システム開発に長年関わってきた担当者が退職・異動すると、その人が持っていた知識が失われてしまいます。特に中堅・中小企業では引き継ぎ体制が整っておらず、「誰も全体構造を把握できない」状態が常態化しているケースもあります。
この属人化は、新たな開発や改修を一層困難にし、外部ベンダーへの依存を強める悪循環を招いています。
- ノウハウの空洞化:業務ロジックがソースコード内部にしか残っておらず、設計書の更新が止まっています。
- ドキュメント不足:修正履歴や設定情報が散在しており、原因調査や不具合対応に時間がかかります。
- 技術継承の断絶:若手エンジニアが古い言語やツールに触れる機会が少なく、実務で扱うスキルが育ちません。
例えば、ある物流企業では唯一システムに精通していた担当者が定年退職した直後、主要取引先のEDI(電子データ交換)仕様変更に対応できず、受発注処理が一時停止する事態が発生しました。ソースコードのコメントや設計書が整理されておらず、外部協力会社も構造を理解できなかったのです。
IPA(情報処理推進機構)の「ソフトウェア保守白書」でも、技術者の高齢化と人材継承の難しさが主要課題として指摘されています。
結果として、企業は“維持するしかない”システムを抱え、改革の優先度を後回しにせざるを得ない状況が続いています。
業務的要因:現場の変化と乖離するシステム構造
ビジネス環境の変化はますます加速しています。市場ニーズの多様化、サプライチェーンの再構築、デジタルチャネルの拡大などにより、業務フローそのものが数年単位で見直されるようになりました。それにもかかわらず、基幹システムが十数年前の業務前提に縛られているケースは少なくありません。
- 固定化された業務ロジック:システムが「過去の正解」を前提に設計されており、柔軟な運用変更が難しくなっています。
- 業務部門との乖離:現場が必要とする機能の要望がすぐに反映されず、スプレッドシートなどの“補助ツール”が乱立しています。
- 改修の継ぎはぎ構造:要望に応じて部分的な改修を重ねた結果、整合性や依存関係がより複雑化しています。
例えばある小売企業では、EC(電子商取引)と実店舗の在庫を統合管理したいという要望が出たものの、既存システムが店舗ごとに独立した在庫台帳構造を持っていたため、改修コストが膨大になりました。結果として、現場ではスプレッドシートで在庫を補う形での運用が常態化しています。
こうした部分的改修の積み重ねにより、システム全体が矛盾を内包する形に成長します。最終的には改修よりも再構築の方が安価になる段階に至り、全面刷新が議論されます。経済産業省の「DXレポート」では、このような状態を「2025年の崖」と表現し、早期の対応を促しています。
本質的な問題は、システムだけでなく、業務と組織がともに変化し続ける前提を欠いていることです。
クラウドERP(Enterprise Resource Planning)や業務APIの利用拡大により、業務とシステムを疎結合に保つ仕組みを整えることが、今後の老朽化防止に不可欠といえるでしょう。

再生へのステップ

レガシー化の本質は「古いものを使い続けている」ことではなく、変化し続ける前提を忘れた運用文化にあります。したがって再生とは、技術の更新だけでなく、組織の知識共有や業務構造の柔軟性を同時に取り戻すことです。ここでは、そのための実践的なステップを紹介します。
変化への適応
基幹システムは企業の血流に例えられることがあります。だからこそ、突然の全面刷新よりも「少しずつ変化を受け入れる仕組みづくり」が重要です。
現状の課題を正確に把握し、どの領域を優先して改修すべきかを見極めることが出発点となります。ポイントは、“理想像ありき”ではなく、“今できる改善の積み重ね”を軸に置くことです。
経営層が策定するデジタル戦略では、IT部門だけでなく事業部門も巻き込み、意思決定の粒度が異なる組織間で目線を合わせる対話の場を設けることが欠かせません。こうした取り組みにより、持続的な改善が可能になります。
- 課題を可視化するワークショップの実施:現行システムの利用実態や運用課題を部門横断で洗い出し、業務とITの双方の視点から課題を整理します。
- 優先順位の明確化:すぐに対応すべき領域(セキュリティリスクや障害多発箇所)と、中長期的に見直すべき領域を区別します。
- 共通ゴールの設定:「コスト削減」だけでなく、「業務スピードの向上」や「顧客サービスの強化」など、効果を具体的に共有できる指標を設定します。
たとえば、販売管理と在庫管理を一度に刷新せず、まずデータ連携の自動化部分だけをAPI化する方法があります。これにより障害対応の負担軽減が期待でき、こうした小さな改善の積み重ねが現場の負担を抑えながらデジタル変革を実現します。
また、コンサルティングサービスを活用することで、第三者の視点から課題構造を整理しやすくなります。外部の専門家は、組織が見落としがちな「暗黙の前提」を可視化し、効率的な再設計を促してくれます。
モダナイゼーション
レガシー資産の再生で重要なのは、単なるリプレースではなく「業務の進化」と「技術の更新」を並行して進めることです。システムの更新は目的ではなく、変化する環境に適応するための手段として捉えることが大切です。
- 現行資産の分析:既存のコードやデータベース構造を解析し、残すべき機能と改修すべき領域を分類します。
- API化による段階的刷新:業務モジュールを切り出してAPI化し、部分的な更新と再利用を両立させます。
- クラウド基盤の活用:AWS、Azure、Google Cloudなどのクラウドサービスを利用し、スケーラビリティと可用性を確保します。
- 継続的な改善サイクル:DevOps(開発と運用の連携)を取り入れ、更新を「一度きりの移行」ではなく「定常業務の一部」として習慣化します。
たとえば、生産管理システムをすべて再構築するのではなく、まず帳票出力機能をクラウドベースのマイクロサービスとして再設計することで、経営への影響を最小限に抑えることができます。
モダナイゼーションは単なる移行作業ではなく、「業務が変化に強くなるための体質改善」と捉えることが、長期的な成功の鍵になります。
「共に創る」SIerによる伴走支援
多くの企業は外部のシステムインテグレーター(SIer:System Integrator)に再構築を委託します。しかし、単純な受託開発モデルではユーザー企業の変化スピードに対応するのが難しいため、「共創型SI」として伴走支援を行う方法が注目されています。
- 現場起点のシステム設計:業務担当者と開発パートナーが同じチームとして協働し、現場の感覚を設計に反映します。
- アジャイル開発の導入:短期間でサイクルを回し、要件の変化や仮説検証に柔軟に対応します。
- ナレッジの共有と蓄積:設計思想や開発ドキュメントを随時共有し、属人化のリスクを減らします。
伴走パートナーの存在は、“変化に追随できる強いシステム”を育てるうえで欠かせません。
ギグワークスクロスアイティの支援サービス
ギグワークスクロスアイティは、システム開発とITコンサルティングの両面から企業変革を支援します。レガシー環境解析からモダナイゼーション戦略策定、アジャイル開発まで、現場視点の「共創型プロジェクト」を多数展開。
単なる技術提供にとどまらず、業務改善を起点とした再構築支援が特徴です。現行システムの停止を避け、変化に適応したい企業は、ギグワークスクロスアイティの専門チームによるコンサルティングを活用して次なる一歩を踏み出せます。
老朽化した基幹システムを前に、「全部作り直したい」と考える企業は少なくありません。
ただし実際には、業務の連続性を維持しつつ段階的な改革を進める戦略のほうが効果的です。
真の再生とは、古さを捨てることではなく、変化に適応できる構造に変えていくことです。
キーワードは「変化への対応力」

基幹システムの老朽化とは単なる時間経過の問題ではなく、変化への対応力の問題です。市場や技術環境が常に変わり続ける以上、システムもそれに合わせて進化し続けることが求められます。レガシー化とは「古さそのもの」ではなく、「変化に適応できない状態」を指します。放置すればシステム障害の増加やコストの急増、競争力低下を招きます。2025年の崖問題に象徴されるように、多くの企業が経済的損失のリスクと隣り合わせです。だからこそ、今こそ自社のシステムを変化の速度に合う形に転換し、継続的な改善体制を整える時期に来ています。技術だけでなく組織や業務の視点も含めた包括的な対応が不可欠です。