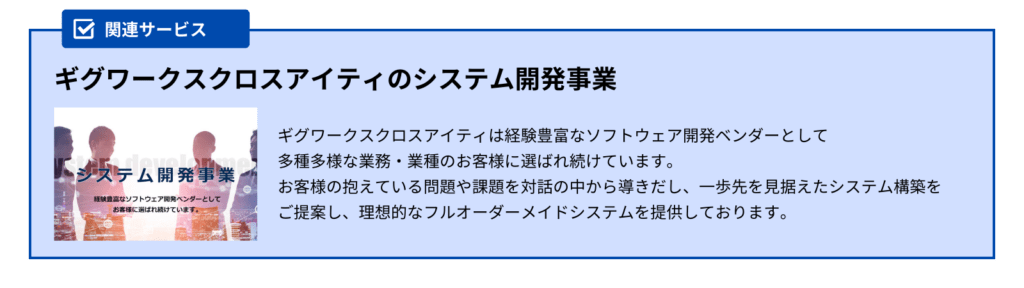企業競争が激しさを増す中、基幹システムはもはや業務を支える裏方ではなく、経営の中核を担う存在へと変わりつつあります。
DX投資の約8割が「期待した効果を生まない」と指摘される今、基幹システムの再設計が競争力を左右する鍵となっています。
しかし、多くの企業では依然として部門ごとの最適化が行き過ぎ、情報の分断や業務の重複が発生しているのが実情です。
本記事では、3社の事例を通じて、基幹システムがどのように業務効率と組織力を変革し得るかを探ります。
【関連記事】基幹システムで意思決定のスピードが変わる!デジタル時代に求められる経営変革とは
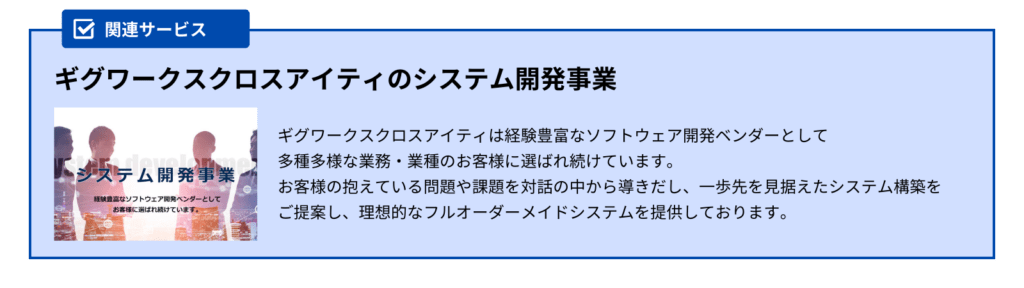
部門間のデータ連携不足がもたらす業務遅延と二重入力
DX投資が加速する一方で、「新システムを導入したのに、入力作業がかえって増えた」という声は少なくありません。
多くの企業が直面しているのは、個別最適化された業務システムが生み出す“データの分断”です。
営業、生産、購買といった部門がそれぞれ独立したシステムを運用していると、情報連携のたびに人手での再入力や確認が欠かせず、全体のスピードと精度が低下します。
A社は、まさにそうした構造的な非効率に悩まされていた中堅の製造業です。
分断されたシステムによる「見えない損失」
A社では、営業・生産管理・購買の各部門がそれぞれ異なるシステムを使用していました。
営業担当が受注情報を登録しても、製造や購買では自部門のシステムに再入力しなければ業務を続けられず、同じ情報を最大3回入力する状況が常態化していました。
現場からは「入力データが他部署に反映されない」「誤登録があれば全員に連絡し直す」といった不満が日常的に寄せられていました。
ミスは月に約40件発生し、その修正には1営業日程度かかっていました。
さらに、在庫データの更新タイミングが部門ごとに異なるため、営業が「在庫あり」と案内した製品が、実際には欠品しているケースも発生していました。
こうした手戻りが積み重なり、A社では毎月数百時間もの工数が“確認と修正”の対応に費やされていました。
情報の分断が生む重複作業と非効率
A社の経営層は、既存システムの機能不足そのものではなく、情報の流れが見えないことが根本的な課題であると認識しました。
情報システム部門を中心に、全社の業務プロセスを横断的に分析し、データがどの部署でどのように扱われているのかを明確にしました。
その結果、営業で入力した情報の約70%が他部署でも再入力されていることが判明しました。
部門ごとに「確認」「整理」「加工」といった目的でデータを扱っており、重複作業が全社的に常態化し、非効率が慢性化する結果となっていました。
既存システムをつなぐ共通データ基盤
A社は全面刷新ではなく、既存システムを“接続”する形で再構築する方針を選択しました。
一見シンプルな選択に見えますが、コストや現場定着のリスクを踏まえた、戦略的な判断でした。
その結果、共通データ基盤を構築し、既存システム間の連携を実現しました。
この基盤により、営業・生産・購買の全システム間で受注データをリアルタイムに共有できるようになりました。
営業が登録した情報は即座に他部門へ反映され、転記や確認の手間を根本からなくすことができました。
さらに、各部門をまたぐ運用ルールも標準化しました。
たとえば、営業が見積を確定登録するタイミングを明確にし、購買部門が参照するデータを「確定データのみに限定」しました。
その結果、曖昧な情報が後工程へ流れるリスクを抑え、業務の精度を高めることができました。
このルール統一が、システム改修以上に現場への定着を後押しする要因となりました。
時間削減と信頼性向上を同時に実現
共通基盤の稼働から半年後、A社は生産性と精度の両面で確かな成果を確認しました。
入力作業時間は約60%削減され、入力ミスは月40件から10件未満へと減少。
営業から生産計画へのデータ反映にかかる時間も、従来の半日から数分へと大幅に短縮されました。
こうした定量的な成果に加え、現場では“データの信頼性が担保されている”という安心感が広がりました。
「どの情報が最新か」を確認する会話が減り、「次の提案をどう進めるか」といった前向きな議論が増えました。
情報の一貫性が確立されたことで、組織全体の意思決定スピードが着実に向上しました。
効率化の鍵は「つながりの設計」
A社の事例は、効率化の出発点が個々のシステムの高度化ではなく、データの流れをどう設計し直すかにあることを示しました。
多くの企業では、「部門最適の積み重ねは全体最適にはならない」という現実が見落とされがちです。
基幹システムは単なる社内インフラではなく、組織の構造と判断の仕組みを支える基盤です。
A社は“接続”の在り方を見直すことで部門間の壁を取り払い、経営と現場が同じ情報を共有しながら動ける体制を整えました。
統合基盤がもたらす業務プロセスの自動化と標準化

部門ごとに最適化された業務やシステムは、表面上は効率的に見えるものです。
しかし、それが長年積み重なると、情報の断片化や判断の遅れを引き起こし、「見えない摩擦」として全体最適を阻みます。
B社は、まさにその構造的課題を打破するため、全社統合基盤の導入に踏み出しました。
目的は単なる業務効率化ではなく、誰が担当しても同じ品質で正確に業務を進められる仕組みづくりでした。
拠点ごとに異なる情報と判断
物流業のB社は全国に拠点を持ち、営業所ごとに独自のExcelや在庫管理ツールを使用していました。
現場は担当者の勘と経験で運用を回していましたが、データの粒度や更新タイミングがそろわず、全社的な在庫計画や配送最適化が難航していました。
現場からは、「在庫数を確認するだけで複数のファイルを開かなければならない」「請求データを合わせるのが毎月一苦労だ」といった声が絶えませんでした。
情報が各所で分断された結果、在庫過多と欠品が同時に発生し、経営的なロスを招いていました。
経営会議で現状を把握するまでに数日を要し、経営判断のスピードが著しく低下していました。
既存システムを活かす全社基盤構想
B社が選んだのは、クラウド型の全社統合基幹システムの導入でした。
受注、在庫、配送、請求データを一元化し、全拠点が同じ情報をリアルタイムで共有できる仕組みを構築。
全データを一枚の基盤で見通すことで、「どの顧客に、いつ、何を配送しているのか」が瞬時に把握できるようになりました。
この決断には明確な戦略がありました。
既存の業務システムをすべて破棄するのではなく、現場の慣れとナレッジを生かしつつ、“接続”を軸に再構築する方針を取りました。
刷新より低リスクで、実装スピードが速く、現場の納得感も得やすいアプローチでした。
現場リーダーが動かす標準化設計
導入初期からB社は、営業所リーダーやシステム担当者を中心とした横断型プロジェクトチームを立ち上げました。
各部門の実態を分析し、共通化すべき作業と地域特有の要素を残す部分を議論しました。
その結果、業務の約8割を標準化し、残りの2割は柔軟にカスタマイズできる設計としました。
受注情報が登録された時点で配送便やドライバーを自動割り当てするフローも構築。
手作業で調整していた工程が、数秒で完了するようになりました。
また、請求処理のフォーマットを統一し、誤請求や重複請求のリスクも解消しています。
こうした取り組みは、単なるルール統一ではなく、“業務をどう流すか”という全体設計の再構築にほかなりません。
現場が設計段階から意思決定に関与していたことが、実装後のスムーズな定着につながりました。
スピード経営と属人化排除を実現
統合基盤の稼働後、B社の現場は大きく変わりました。
出荷処理時間は平均2日から1日に短縮され、誤配送率は30%改善しました。
受注・在庫・配送の各情報が一元化されたことで、在庫補充の自動通知や配送ルートの最適化など、データを活用したオペレーションが実現しました。
経営層にとっても変化は大きく、会議で求められるレポートや数値分析がリアルタイムに生成され、意思決定サイクルは月次から週次へ短縮されました。
「現場の実態に即した即断」ができる体制が整いました。
一方、現場では「情報を知っている人」に依存していた属人的な業務がなくなり、誰もが同じ手順で処理できる環境が定着しました。
属人化の排除はスキル継承の課題を解消し、組織の持続性を高める効果を生みました。
現場を巻き込み、歩幅を合わせる
B社のプロジェクトが成功した鍵は、現場を置き去りにしない導入方針にあります。
トップダウンで一斉展開するのではなく、まず数拠点で試験運用を行い、段階的に拡張しました。
実データで課題を検証しながら「現場が納得できる標準化」を積み上げることで、反発を最小限に抑えました。
現場リーダーが主体的に改善提案を行い、本社がそれを技術的に支援する“協働型改革”として進めた点も特徴的です。
この姿勢は、システム面での統合にとどまらず、「全員で改革に関わる文化」を育てました。
統合は「働き方」そのものを変える
B社の事例は、統合がシステムの統一ではなく、組織の判断構造と働き方の再設計であることを示しています。
基幹システムの統合によってデータと業務プロセスが一貫し、現場と経営層が同じ情報を基に判断できる体制が整いました。
それは単なる業務効率化にとどまらず、意思決定のスピードと品質を高める経営基盤へと発展しています。
B社の取り組みは、効率化の先に「働き方の自律」と「組織の一体感」を実現しました。
現場担当者の負担軽減と顧客対応力の向上
これまで取り上げたA社・B社の取り組みが社内プロセスの最適化を目的としていたのに対し、C社の改革は「顧客との接点」を中心に据えていました。
顧客対応のスピードと精度は、企業の信頼を左右する重要な経営基盤の一部です。
C社は、基幹システムとCRMを統合することで、現場業務の効率化と顧客満足度の両立を実現しました。
情報分散が生む「顧客対応の遅れ」
製品販売と保守サポートを手掛けるC社では、営業・サポート・経理の各部門がそれぞれ独自のシステムを運用していました。
営業は契約情報をExcelで、サポートは問い合わせを専用ツールで、経理は請求履歴を別管理として扱っていました。
仕組みが増えるほど、顧客対応に必要な情報収集の手間も増え続けていました。
顧客から問い合わせが入るたび、担当者は3つ以上のシステムを横断して検索していました。
1件あたりの対応に平均20分以上を要し、場合によっては情報の整合が取れず翌日対応に持ち越すこともありました。
社内では「顧客対応の遅れが商談機会の損失につながっている」という危機感が高まり、現場の疲弊も深刻化していました。
顧客からは「問い合わせのたびに何度もIDを聞かれる」「担当者によって回答が違う」といった苦情が寄せられ、顧客満足度の指標は3年連続で下がっていました。
CRM一体型システムへの刷新
C社は、基幹システムとCRM(顧客管理)を一体化した統合基盤の構築を決断しました。
狙いは、単に顧客情報を整理することではなく、一度の確認で完全な顧客像を把握できる仕組みをつくることにありました。
営業・サポート・経理の各データを共通基盤上で統合し、顧客単位で全履歴をリアルタイムに参照できるようにしました。
設計では、顧客データと取引データを同一テーブルで関連づけ、問い合わせ内容から契約情報や請求状況、過去履歴までをワンクリックで確認できる構成とした点が特徴です。
導入段階では、現場メンバーが自ら業務フローを整理し、経営層も意思決定のデータ要件として関与しました。
現場の視点と経営の判断を両立させた設計で、導入段階から高い納得度を得られました。
システム稼働から6か月後、1件あたりの対応時間は20分から8分に短縮しました。
顧客満足度は前年より15%上昇し、担当者の残業時間も25%削減されました。
表面的な工数削減だけでなく、「迅速に・正確に答えられる」ことが、企業としての信頼向上につながりました。
データ統合が変えた「働き方」の質
新システムの導入によって、C社の現場は大きく変わりました。
以前は情報探しに追われていた担当者が、今では顧客と向き合う時間を取れるようになりました。
問い合わせ履歴から過去の対応傾向が自動で提示されるため、担当交代時の引き継ぎもスムーズです。
対応の一貫性が保たれることで、顧客が感じていた担当者への依存不安も解消されました。
現場では次第に、情報を抱える個人ではなく、顧客を理解するチームとして行動する意識が生まれました。
属人化の解消とともに、担当者間でナレッジが共有され、サービスの精度も向上しました。
経営面でも変化は明確でした。
顧客セグメントごとの対応状況やサポートコストを即座に可視化できるようになり、経営会議での意思決定もスピードアップしました。
販売後支援(アフターサービス)を利益構造の一部として位置づけ直す取り組みも進みました。
顧客対応データがそのまま経営判断データになる――。
これこそが、C社が得た最も大きな成長効果でした。
データを軸に現場と経営が会話
C社の改革を成功に導いた最大の要因は、システム導入を単なるITプロジェクトではなく、組織改革の一環として位置づけたことです。
経営層と現場担当者が同じデータ設計を共有しながら議論し、「どのデータが本当に顧客に価値を与えるか」を共有したことで、システムが両者の共通言語として機能しました。
導入後も、毎週のレビュー会でユーザーの声を反映し、画面設計や自動通知のルールを継続的に改善しました。
システムを“育てる”という姿勢が、定着率と利用満足度の向上につながりました。
社員にとってシステムは「負担」ではなく、「自分の判断を支える信頼できる味方」へと変わっていったのです。
業務効率化は顧客体験の出発点
C社の事例が示す通り、業務効率化の本質は社内負担の削減ではありません。
焦点はむしろ、顧客に正確で一貫した対応を届けるための基盤整備にあります。
現場の作業負担が減れば、その余力をより質の高い提案やフォローに充てることができ、結果として顧客体験の質が向上します。
まさに、内側の効率が外側の信頼を生み出す仕組みです。
今後はAIを活用した顧客行動予測や自動提案など、次世代の顧客体験設計への発展も見据えています。
C社の改革は、単なるシステム刷新ではなく、働きやすさと顧客満足を同時に高めるモデルケースといえるでしょう。
基幹システムを「組織の設計図」に

ここまで紹介した3社の事例は、それぞれ異なる段階で業務改革を実践しつつも、最終的に共通した方向性を示しました。
それは、基幹システムを単なる業務支援としてではなく、企業を動かす中核的な設計図として再定義する姿勢です。
- A社:データ連携で部門間の壁を解消し、生産性を底上げしました。
- B社:統合基盤で業務を標準化し、経営判断を迅速化しました。
- C社:CRM統合で現場の効率化と顧客体験の向上を両立しました。
3社に共通するのは、「情報をつなげ、組織を整えること」が生産性革新の出発点であるという認識です。
基幹システムは、情報を統一し、人とデータを結び、組織を一つに動かす“設計図”として機能します。
そして次の進化の局面では、AIやデータ分析との融合によって、予測力と意思決定の質を引き上げ、経営のあり方自体を進化させる基盤としての役割がさらに重要になります。
変化の激しい時代だからこそ、自社の“設計図”を見直し、現場と経営をつなぐ仕組みを進化させ続けることが、これからの競争力を左右します。