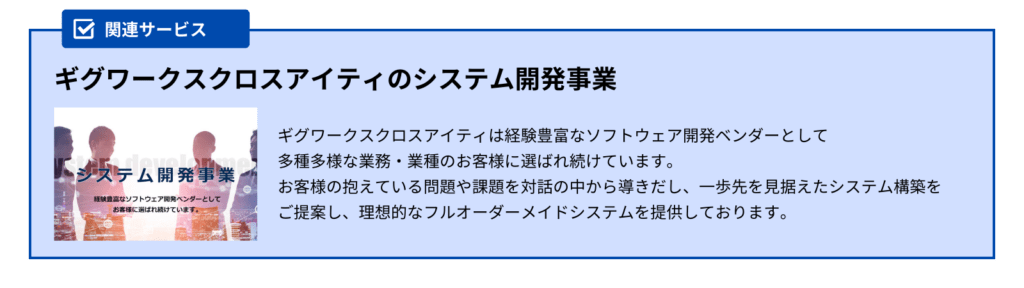かつて基幹システムの刷新は、ハードウェアの保守切れやソフトウェアのサポート終了といった「IT部門の都合」で語られることが大半でした。しかし、現在その文脈は一変しています。パンデミックや地政学リスクによるサプライチェーンの寸断、急速に厳格化されるESG経営への要請、そして慢性的な人材不足。これら複合的な危機に対し、企業が生き残るための「経営のOS」そのものを書き換える行為こそが、現代における基幹刷新の本質です。本記事では、なぜ今、多くの企業が痛みを伴う刷新を決断するのか。その必然性を、市場・非財務・人・戦略の4つの視点から紐解きます。
【関連記事】AI・クラウド技術が競争力を生み出す!基幹システムの未来とは
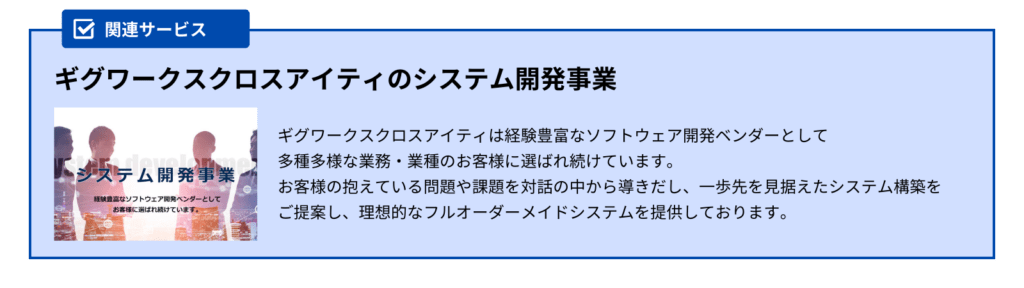
急激な市場の変化(パンデミック/地政学リスク)が基幹刷新を「必然」に変えた
ビジネスを取り巻く環境は、過去数十年の常識が通用しないフェーズに突入しました。2020年のパンデミックは、IMFが「大封鎖(Great Lockdown)」と称したように、世界経済を一瞬で停止させました。さらに、近年の紅海危機やスエズ運河の物流混乱といった地政学リスクは、グローバルサプライチェーンがいかに脆いバランスの上に成り立っていたかを露呈させています。需要、供給、物流、そして働き方が短期で激しく反転する現代において、企業に求められるのは「予測する力」以上に「変化に即応する力」です。この章では、なぜ既存のレガシーシステムが変化対応の足かせとなり、刷新が不可避となっているのかを構造的に解説します。
「変化への対応」のボトルネック
日本企業は長らく、現場の献身的な調整能力、いわゆる「現場力」によってシステムの不備を補ってきました。しかし、現在起きている変化のスピードと規模は、もはや人手による調整で吸収できる限界を超えています。
例えば、ある製造業で特定の原材料調達が地政学リスクにより不可能になったケースを想定します。即座に代替サプライヤーへの切り替え、輸送ルートの変更、それに伴う原価計算の修正、販売価格への転嫁、在庫の再配置といった一連のプロセスを回さなければなりません。しかし、多くの企業ではここで意思決定が止まります。
- マスターの不整合:各工場や事業部が個別にシステムを構築しているため、代替部品のコードや仕様が統一されておらず、全社在庫を即座に把握できません。
- ブラックボックス化:長年の継ぎ足し開発によりロジックが複雑化しており、調達先の変更が生産計画や原価にどう波及するかのシミュレーションに膨大な時間を要します。
- 改修の長期化:システム変更を行おうにも、影響範囲の調査だけで数ヶ月かかり、ビジネスの機会損失を招きます。
経済産業省のDXレポートが指摘する「2025年の崖」の本質はここにあります。レガシーシステムを放置することは、単に古いITを使っているだけの問題ではありません。市場の変化に対してビジネスモデルや商流を柔軟に変更できない構造的な硬直を生み出し、年間最大12兆円規模の経済損失につながるリスクそのものなのです。現場がどれほど優秀でも、基盤となるデータとプロセスが分断されていれば、組織としての俊敏性は失われます。
俊敏性を高める「データ×プロセス×権限」
市場変化に打ち勝つ「俊敏性(アジリティ)」とは、精神論ではありません。「正しいデータに基づき、プロセスを即座に変更し、適切な権限で意思決定を下す」という実務能力の総体です。そして、この能力を担保できるのは、統合された基幹システムをおいて他にありません。
パンデミック以降、需要変動に合わせて生産計画を週次から日次へ短縮したり、物流コストの高騰を受けて顧客別・製品別の真の採算性を可視化したりするニーズが急増しました。これらを実現するには、受注・生産・在庫・会計といったデータがリアルタイムに連携していることが大前提です。
- 統合データの価値:部門ごとにサイロ化されたデータではなく、全社で「一つの真実(Single Source of Truth)」を共有することで、計画と実績の差異を即座に検知し、アクションにつなげることが可能になります。
- プロセスの標準化:OECDが指摘するように、テレワーク等の柔軟な働き方が定着する中で、属人的な業務プロセスはリスク要因となります。基幹システムによって業務が標準化されていれば、担当者が変わっても、あるいは場所が離れていても、一貫した品質で業務を遂行できます。
- 技術的負債の解消:IDC等が警鐘を鳴らす「技術的負債」は、将来の変革コストを指数関数的に増大させます。現在のシステム延命に予算の大半を費やす状況から脱却し、攻めのIT投資へリソースを振り向けるためにも、刷新による負債の清算が必要です。
「変えられる構造」への転換
外部環境の変化は、今後も予測不能な形で発生し続けます。今日最適化されたサプライチェーンが、明日には機能不全に陥ることも珍しくありません。このような環境下において、硬直的なレガシーシステムを抱え続けることは、経営そのものをリスクに晒す行為です。
基幹システムの刷新は、単なるツールの入れ替えではありません。予期せぬ変化が起きた際に、データに基づいて迅速に構成を組み替え、ビジネスを継続させるための「変えられる構造」を手に入れる投資です。変化への対応力を現場のマンパワーに依存するのではなく、デジタル基盤によって組織能力としてスケールさせること。これこそが、不確実性の時代における競争優位の源泉となります。
【参考】D X レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~
【参考】IMPACT TO GLOBAL TRADE OF DISRUPTION OF SHIPPING ROUTES
ESG・SDGsと規制強化で求められる「説明できるデータ」

「環境や社会に配慮することは良いことだ」という理念的な時代は終わりを告げました。現在、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGsへの対応は、投資家、取引先、そして規制当局から厳しく求められる「参加資格」であり、明確な開示と説明責任を伴う経営課題へと変貌しています。欧州を中心とした規制の波は日本企業にも押し寄せ、サステナビリティ情報の開示は財務情報と同等の精度と信頼性を要求されるようになりました。この章では、厳格化する非財務情報の開示要求に対し、なぜ基幹システムの刷新が不可欠な解となるのか、ガバナンスとデータ品質の観点から論じます。
「データの出どころ」まで問われる
近年、サステナビリティ情報の開示基準は世界的な統合が進んでいます。ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)によるIFRS S1/S2の確定や、EUにおけるCSRD(企業サステナビリティ報告指令)の適用開始は、企業に対し、自社のみならずサプライチェーン全体を包括したデータ開示を義務付けています。
ここで重要なのは、求められているのが単なるスローガンや定性的な活動報告ではない点です。CO2排出量、人的資本、人権デューデリジェンスなど、具体的かつ定量的なデータが求められます。しかも、そのデータはGRIスタンダードや各国の規制といった複数の基準に準拠しつつ、投資家の判断に耐えうる粒度で提供されなければなりません。
- 説明責任の厳格化:もし開示データに誤りや根拠の欠如があれば、それは「グリーンウォッシング(見せかけの環境対応)」として厳しく指弾され、企業価値を大きく毀損するリスクになります。
- デジタル報告の潮流:EFRAG(欧州財務報告諮問グループ)などが進めるデジタル報告の枠組みでは、人間が読むレポートだけでなく、機械可読なデータとしての提供が視野に入っています。これは、データの定義が全社で統一され、システム間で整合性が取れていることを意味します。
「集計」ではなく「トレーサビリティ(証跡)」
多くの企業が直面している課題は、これらの膨大なデータをどう収集・管理するかです。従来のように、各部門からExcelでデータを集め、手作業で集計する手法は限界を迎えています。CSRDなどで導入が進む「第三者保証(Assurance)」の要件を満たせないからです。
監査人や保証機関は、提出された数値が正しいかどうかを確認するために、その数値が生成されたプロセスと元データを辿ります。これを「トレーサビリティ(追跡可能性)」と呼びます。GHG(温室効果ガス)排出量を例に取れば、どの工場の、どのラインで、いつ、どれだけのエネルギーが消費されたかという一次データまでドリルダウンできる状態が必要です。
- データの一元管理:基幹システムにおいて、購買・生産・物流・販売の各トランザクションデータが統合されていれば、製品ごとのカーボンフットプリントなどを自動的かつ正確に算出する基盤となります。
- 監査証跡の確保:誰がデータを入力し、誰が承認し、いつ変更されたかというログ(証跡)がシステムに残ることは、データの信頼性を担保する上で必須条件です。Excelのリレーでは、この証跡が途絶えやすく、監査に耐えられません。
- マスター管理の重要性:取引先や品目のマスターデータが統一されていなければ、グローバル全体での人権リスク評価や環境負荷の集計は不可能です。
規制対応・ガバナンス強化における基幹の存在意義
ESG対応は、広義の「ガバナンス(内部統制)」の一部として捉えるべきです。金融庁の内部統制基準や米国のSOX法が求める財務報告の信頼性確保と同様に、非財務情報においても、不正や誤謬を防ぐ統制環境が求められています。
基幹システムを刷新することは、この統制を「人の注意」ではなく「業務プロセス」に埋め込む絶好の機会です。例えば、承認ルートの自動化、権限分離(SoD)の徹底、異常値の自動検知といった機能をシステムレベルで実装することで、コンプライアンス遵守を効率的かつ確実に行うことが可能になります。
- 統制の自動化:人手によるチェックは抜け漏れが発生しやすく、コストもかかります。システムによる自動統制(IT全般統制・業務処理統制)は、監査対応の工数を削減しつつ、ガバナンスのレベルを飛躍的に高めます。
- 説明可能な経営へ:ステークホルダーから「なぜこの数値になったのか」と問われた際、システムに基づいた明確なロジックと証跡を提示できること。これが、不確実な時代における企業の信用力(トラスト)を形成します。
ESGが突きつける「データ経営」
ESGや規制対応を「コスト」として捉え、手作業の継ぎ接ぎで乗り切ろうとすることは、長期的には最大の非効率を生み出します。これらは企業に対し「透明性の高いデータ経営」への移行を迫る強力な強制力(ドライバー)です。
基幹システムの刷新は、規制対応という守りの側面だけでなく、自社の活動を正確に把握し、対外的に説明できる能力を獲得するための戦略投資です。監査に耐えうる強固なデータ基盤を構築し、透明性を確保すること。それは、サステナビリティが経営の核心となった現代において、企業が社会からの信頼を勝ち取り続けるための必須条件といえます。
刷新を成功させる方針と意思統一・目標設定の指針
市場の変化に対応し、規制要求を満たすための基盤が必要であることは前章までに述べました。しかし、これらを実行するのは最終的には「人」です。そして今、日本企業にとって最大の制約条件となっているのが、深刻な人材不足です。IT人材の枯渇だけでなく、実務を担う現場の人手不足も恒常化しています。生産年齢人口が減少する中で、もはや「人を増やして対応する」という選択肢はありません。限られたリソースで成果を最大化するためには、業務の徹底的な効率化と標準化が不可避です。本章では、人材不足を前提とした基幹刷新のあり方と、プロジェクトを成功に導くための具体的な方針・目標設定について提言します。
「ERPの導入」を目的にしない
多くの刷新プロジェクトが失敗する最大の要因は、目的が「古いシステムを新しくすること(ERP導入)」自体になってしまう点にあります。これでは、現場の業務をそのまま新システムにコピーするだけの結果となり、投資対効果は生まれません。
人材不足時代における刷新の真の目的は、「生産性」と「意思決定速度」の劇的な引き上げに置くべきです。採用難が世界的な課題であり、世界経済フォーラムがスキルの陳腐化とリスキリングの必要性を説く中、企業は「人が介在しなくても回る業務」を極限まで増やす必要があります。
- 業務量の絶対削減:月次決算の早期化や、例外処理の自動化、手入力の廃止など、システムが自動処理できる領域を広げ、人間は人間にしかできない付加価値業務に集中する環境を作らなければなりません。
- 経営に直結する成果:例えば、「計画と実績の差異をリアルタイムで把握し、週次で対策を打てるようにする」といった、経営のスピードアップに直結する成果を定義することが重要です。
意思統一の4原則
基幹刷新は長期にわたる難易度の高いプロジェクトです。迷走を防ぐためには、経営層が以下の4つの原則を明確に打ち出し、組織全体の意思を統一する必要があります。
- North Star(北極星)の確立
「何のために刷新するのか」という揺るがない指針を明文化します。「老朽化対応」ではなく、「市場変化への即応」「グローバルでのガバナンス強化」「圧倒的な生産性向上」など、経営戦略とリンクした優先順位を定めます。これが、判断に迷った際の唯一の拠り所となります。 - Fit-to-Standard(標準への適合)
日本企業の悪癖である「過度なカスタマイズ」を封印する原則です。自社の独自業務にシステムを合わせるのではなく、グローバル標準の業務プロセス(ベストプラクティス)に自社の業務を合わせます。例外的なカスタマイズは、それが競争優位の源泉であると証明された場合のみ、経営レベルで承認するという厳格な運用が必要です。 - データ資産化原則
データは部門の持ち物ではなく、全社の資産であると定義します。コード体系やマスターデータの管理権限(Data Owner)を明確にし、部門の壁を超えたデータ活用を最優先します。DX銘柄企業に見られるように、データの整理・統合こそが変革の要です。 - 段階移行の原則
リスクを最小化し、早期に成果を出すために、全社一括導入(ビッグバン方式)ではなく、段階的な移行を推奨します。Gartnerが提唱する「Composable ERP」の概念のように、特定の事業や地域、あるいは機能モジュールごとに順次導入し、成功体験を積み重ねながら展開していくアプローチが有効です。
目標設定の指針
方針を具体的なアクションに落とし込むためには、定量的かつ多層的な目標設定が欠かせません。
- KGI(重要目標達成指標):経営視点での成果指標です。「価格改定の意思決定から反映までのリードタイム短縮」「監査証跡の自動整備率100%」「決算早期化による経営判断の前倒し日数」など、ビジネス価値に直結する指標を設定します。
- KPI(重要業績評価指標):プロジェクトの健全性を測る指標です。「マスターデータの重複率」「標準機能の利用率(Fit率)」「例外プロセスの発生件数」など、方針が守られているかをモニタリングします。
- ガードレール(守るべき制約):セキュリティ要件や内部統制上の権限分離(SoD)など、絶対に譲れない条件を「後付け禁止」の要件として先に確定させます。これにより、手戻りを防ぎます。
基幹刷新は「経営変革」
SAPの保守期限やOracleのサポートポリシー変更といった外部要因は、あくまで刷新を検討するきっかけに過ぎません。それらを単なる「期限」と捉えて対応するのか、それとも自社を筋肉質な体質へ変える好機と捉えるかで、得られる結果には雲泥の差が生まれます。
基幹刷新はITプロジェクトではなく、経営変革そのものです。成功の条件は、経営トップが不退転の決意で「方針を固定」し、現場に対して「目標を可視化」し続けることにあります。グローバルな人材獲得競争と効率化の波に飲み込まれる前に、標準化されたデータとプロセスを武器にできる企業へと生まれ変わること。それこそが、次の時代を生き抜くための最良の戦略なのです。
基幹システムは経営の「中枢神経」

本記事では、不確実性の時代における基幹システム刷新の必然性を多角的に解説しました。
- 市場変化への対応:パンデミックや地政学リスクによる急激な変動に対し、レガシーシステムの硬直性は経営の致命的なリスクとなります。データを統合し、プロセスを標準化することで初めて、組織は変化に対する俊敏性を獲得できます。
- 透明性と説明責任:ESGや法規制の強化は、データに対する厳格なトレーサビリティを求めています。基幹刷新は、監査や保証に耐えうる「説明可能なデータ基盤」を構築し、ガバナンスを運用に埋め込むための必須投資です。
- 人材不足と生産性:労働力減少が加速する中、Fit-to-Standardによる業務の標準化と自動化は避けて通れません。経営トップが明確なNorth Star(目的)とKGI/KPIを掲げ、システム導入を通じて「変えられる会社」へと体質改善を図ることが成功の鍵です。
もはや基幹システムは、バックオフィスの事務処理マシンではありません。経営の意思を現場に伝え、現場の事実を経営に還流させるための中枢神経です。この中枢神経を最新化し、透明性と俊敏性を両立させることこそが、不確実な未来に対する最も確実な備えとなるでしょう。