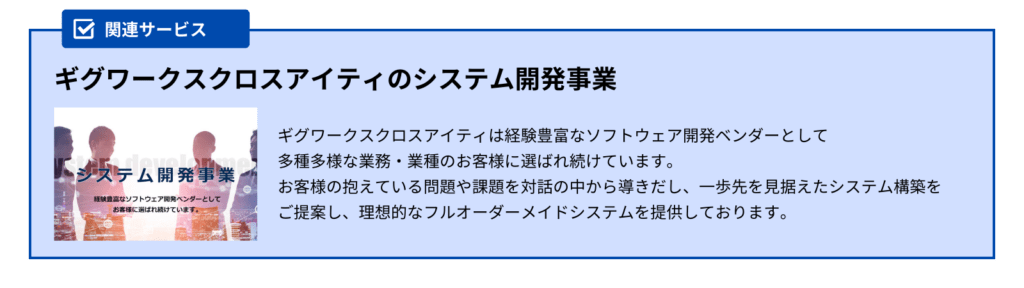多くの日本企業において、長年使い続けてきた基幹システムが経営の足かせになる事態が起きています。かつては効率化の要であったシステムが、現在では市場の変化や新しいビジネスモデルへの対応を阻む「見えない壁」となっています。本記事では、単なるIT設備の更新にとどまらない、企業の成長速度を劇的に向上させるための基幹システムの刷新について詳しく解説します。
刷新の適切なタイミングをいかに見極めるべきか、そしてクラウドやAPIを活用した最新のアーキテクチャがどのような経営的価値をもたらすのかを掘り下げます。さらに、グローバル企業の成功事例を通じて、刷新を成功に導くための具体的な型を提示します。基幹システムの刷新をコストではなく、未来への投資として捉えるための一助となれば幸いです。
【関連記事】市場の変化から読み解く!不確実性の時代に「基幹システム刷新」はなぜ必然なのか
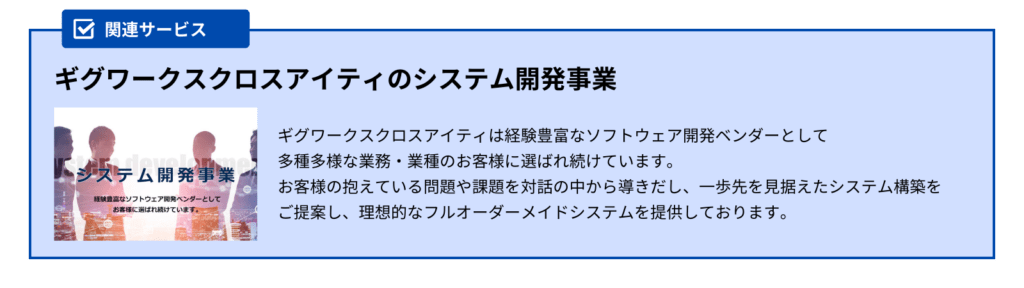
市場環境の変化と「刷新タイミング」の重要性
多くの経営者やIT部門の責任者にとって、基幹システムの刷新は多大な労力と予算を要する「重たいプロジェクト」と捉えられがちです。しかし、現在の激しいビジネス環境において、基幹システムの刷新は単なるIT機器の入れ替えではありません。それは「成長速度を上げるための制約の解除」であるといえます。古いシステムという重りを外すことで、企業は本来持っているポテンシャルを最大限に発揮できるようになります。
市場の変化がシステムを「負債」に変える構図
かつてのビジネス環境は、一定の予測が可能で、変化のスピードも緩やかでした。しかし、現在は需要の激しい変動やサプライチェーンの不確実性、さらには原材料高騰に伴う価格変更の頻度増など、外部環境が目まぐるしく変化しています。また、規制や監査の強化、M&Aによる組織統合、海外展開の加速、さらには直販(D2C)やサブスクリプションといった販売チャネルの多様化も進んでいます。
こうした変化に対して柔軟に対応できない古いシステムは、企業の機会損失を招きます。例えば、新しい料金プランを導入しようとしても、システムの改修に半年かかると言われれば、その間に競合他社にシェアを奪われてしまいます。また、データが古い形式のまま固定されていると、精度の高い需要予測ができず、在庫過多や欠品による売上の機会損失が発生します。さらに、老朽化したシステムの維持には多額の保守費用がかかり、最新のセキュリティ対策も不十分になりがちです。変化に追随できないことは、売上の減少とコストの増大を同時に引き起こすという、極めて危険な状態を招きます。
自社のシステムが「刷新すべき状態」にあるかの判断基準
自社の基幹システムが限界を迎えているかどうかを判断するために、以下のチェックリストが有効です。これらに当てはまる項目が多いほど、システムが経営の足を引っ張っている可能性が高くなります。
- 過度なカスタマイズの弊害:業務に合わせすぎて独自の改修を重ねた結果、システムが複雑怪奇になり、わずかな修正にも膨大な時間とコストがかかっている。
- データの分断とサイロ化:部門ごとに異なるツールが乱立し、データが統合されていないため、経営層がリアルタイムで正確な数字を把握し、迅速な意思決定を行うことができない。
- ベンダーロックインの加速:特定のITベンダーに依存しすぎており、契約更改の交渉が困難であったり、新しい技術への乗り換えが物理的に不可能な状態に陥っている。
- 技術的負債の増大:古いプログラミング言語や設計思想で構築されており、現在の技術者がメンテナンスできない、あるいは最新のAIや分析ツールと連携できない。
日本の経済産業省が発表した「DXレポート」では、こうしたレガシーシステム(老朽化したシステム)が残ることで、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告されています。これを「2025年の崖」と呼びますが、これは単なる予測ではなく、多くの企業ですでに現実の問題として顕在化し始めています。保守運用にIT予算の大部分が吸い取られ、新しい価値を生むための攻めの投資ができない構造を打破することが、経営における最優先事項の一つです。
「いつやるか」を経営と言語で定義する
システム刷新のタイミングを考える際、多くの企業は「現在のシステムのサポート期限」を基準にします。例えば、世界的なシェアを持つSAP社の製品などには、2027年や2030年といった保守期限が設定されています。しかし、期限が来るから移行するという「守り」の発想だけでは不十分です。刷新のタイミングは、以下の3つの軸で多角的に判断する必要があります。
第一に「外部期限」です。これにはソフトウェアのサポート終了だけでなく、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法規制への対応も含まれます。第二に「成長イベント」です。新しい拠点を開設する、海外市場へ進出する、あるいは新しいサービスを開始するといった、ビジネスを拡大させるタイミングこそが刷新の好機です。第三に「内部限界」です。システム障害が頻発する、特定の担当者しか操作できない属人化が進んでいる、あるいは改修のリードタイムが許容範囲を超えているといった、現場の課題を見逃してはいけません。
重要なのは、期限に追い込まれてから着手するのではなく、「数年後の成長計画を実現するために、いつまでにシステムが整っているべきか」という逆算の視点を持つことです。準備には時間がかかるため、ビジネスチャンスが到来したときにシステムが完成している状態を目指さなければなりません。
「刷新」は最大のリスク回避である
基幹システムの刷新を単なる「費用」として計上し、先送りにすることは、企業にとって大きなリスクとなります。古いシステムに固執し続けることで、DX(デジタルトランスフォーメーション)は未達成に終わり、データの活用も進まず、結果として市場での競争力を失うからです。逆に、この刷新を機に最新のテクノロジーを導入すれば、それは企業の機動力を高める強力なレバレッジとなります。「ITの更新」ではなく「経営基盤の再構築」であるという認識を持つことが、成功への第一歩です。
【参考】DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~
クラウド×API連携で俊敏な経営変革を実現する「モダンな基幹」

現代の企業が目指すべき新しい基幹システムの姿は、一言でいえば「標準化されたデジタルコアを中心に、APIでつながる周辺サービスとデータ基盤が連携し、変化に合わせて機能を自由に組み替えられる構造」です。かつてのように、一つの巨大なシステムですべての業務を賄おうとする考え方は、もはや過去のものとなりました。
モノリスからエコシステムへの転換
従来の基幹システムは、あらゆる機能が一つの塊として作られた「モノリス(一枚岩)」のような構造でした。これに対し、モダンなERP(企業資源計画)は、複数のクラウドアプリケーションが連携して価値を生み出す「エコシステム」のような存在です。ERP単体ですべてを解決しようとせず、会計や購買、在庫管理といった中核機能に特化し、特定の業務に強いクラウドサービスを外部からつなぎ合わせる形が主流となっています。
この「つなぎ合わせる」ための技術が、API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)です。APIは異なるソフトウェア同士が対話するための窓口のようなもので、これを利用することで、自社独自のシステムや他社の便利なサービスと、基幹システムを簡単かつ迅速に連携させることができます。システム全体を壊すことなく、一部の機能だけを最新のものに入れ替えるといった柔軟な運用が可能になります。
「Composable(組み替え可能)」という新しい発想
近年、ガートナー社などの調査機関が提唱しているのが「Composable ERP」という概念です。これは、システムをレゴブロックのように独立した部品(モジュール)の集まりとして捉える考え方です。例えば、新しいECサイトを立ち上げる際には、その分野で最適なクラウドサービスを選び、APIで基幹システムと接続します。数年後にそのサービスが古くなれば、そこだけを別の新しいサービスに差し替えることができます。
この仕組みは、スマートフォンのアプリに似ています。スマートフォンのOS(基幹部分)はそのままに、必要に応じてカメラアプリやSNSアプリを追加したり削除したりするのと同じ感覚で、企業のシステムも組み立てていくのです。この「必要な能力を必要な分だけ組み立てる」発想こそが、予測不能な市場環境において企業が生き残るための鍵となります。
モダンな基幹の4つのレイヤー
図解を使わずに、最新のシステム構造を文章でイメージしてみましょう。大きく分けて、以下の4つの層(レイヤー)で構成されます。
- デジタルコア(中核層):会計、購買、在庫、生産、販売といった、企業の背骨となる標準的な業務プロセスを担当します。ここは極力カスタマイズせず、標準機能を使うことで安定性と更新性を保ちます。
- 連携レイヤー(接続層):API管理やiPaaS(異なるアプリケーションをつなぐクラウドプラットフォーム)を活用し、システム間のデータの流れを制御します。B2B連携や電子データ交換(EDI)もここに含まれます。
- 周辺レイヤー(拡張層):CRM(顧客関係管理)や高度なSCM(サプライチェーン管理)、分析ツール、最新のAIなど、ビジネスの差別化要因となる機能を配置します。
- データレイヤー(統合層):バラバラに存在するデータを統合し、マスタデータを一元管理します。データの品質を保つためのガバナンスを効かせ、いつでも分析に使える状態にしておきます。
役割を分担させることで、「コア部分は堅牢に守り、周辺部分は俊敏に攻める」という二段構えの経営基盤が完成します。
「俊敏さ」を定量的な指標(KPI)で測る
システムを刷新した効果は、単なるコスト削減だけでなく、経営のスピード感として現れるべきです。社内での説明や評価を行う際には、以下のような指標を活用すると、経営層にも価値が伝わりやすくなります。
まず、新しい機能のリリース頻度や改修にかかるリードタイムです。かつて数ヶ月かかっていた機能追加が、数週間や数日で完了できるようになれば、ビジネスの機会損失を大幅に減らせます。また、月次決算の短縮や、新しいデータ連携にかかる日数の削減も重要な指標です。さらに、障害が発生した際の復旧時間(MTTR)や、定型的な運用工数の削減も挙げられます。運用に割いていたリソースを、新しい成長施策の開発へ再配分できているかという視点が欠かせません。
理想と現実のバランス:段階的な移行の提案
すべてのシステムを一度に入れ替える「ビッグバン移行」は、リスクが極めて高く、現代のスピード感には合いません。現実的な解として、いくつかの段階的なアプローチがあります。例えば、顧客接点に近い周辺システムから先に刷新する、あるいはデータ基盤を先行して構築するといった手法です。また、本社は最新のERPを使い、拠点や子会社には軽量なクラウドERPを導入して連携させる「二層(2-Tier)ERP」という戦略も有効です。
経営陣が注視すべき論点は、技術の詳細ではなく、「どこまでを標準化し、どこに独自性を残すか」という線引きです。現場のこだわりをすべて聞き入れるのではなく、全体最適の観点から優先順位を決定する強いリーダーシップが、刷新を成功させるための必須条件となります。
【参考】ERP integration strategies for cloud, API, and AI readiness
業務効率と成長投資を両立する「刷新の型」
他社の事例を参考にする際は、単に「成功した」という結果だけを見るのでは不十分です。その企業がどのような課題を抱え、どのような「型」で解決したのかを抽出することで、自社の戦略に応用することができます。ここでは、グローバルで大きな成果を上げている3社の事例から、基幹システム刷新の真髄を探ります。
Nestlé(ネスレ):効率化でブランド投資を加速
世界最大級の食品メーカーであるネスレは、消費者のトレンド変化が激しい市場で戦っています。同社が直面していたのは、グローバル規模でのスピード向上と運用効率の改善という課題でした。そこでネスレは、次世代のクラウド基盤である「SAP S/4HANA Cloud」への大規模なアップグレードを決断しました。
この刷新のポイントは、単なるソフトウェアの更新ではなく、最新のAIや自動化技術をいつでも組み込める「デジタルコア」を構築した点にあります。これにより、定型業務の効率が飛躍的に向上しました。特筆すべき成果は、この効率化によって生み出された余剰リソースを、「製品ブランドへの投資や新たな成長機会の創出」へ大胆に再配分したことです。システムを最新に保つことが、直接的にマーケティングや商品開発の原動力となることを証明した事例といえます。
Unilever(ユニリーバ):「無限の拡張性」で実験を繰り返す
ユニリーバは、世界中に多くの拠点と複雑なIT資産を抱えていました。彼らの目的は、ITの複雑さを解消し、新しいビジネスのアイデアを素早く試せる「実験の場」を作ることでした。同社は、4つの中核的なERPを含む基幹システムの大部分を、わずか18ヶ月という短期間でクラウド(Azure)へ移行しました。
クラウド化によって得られた大きな恩恵は、「無限に近い拡張性」を手に入れたことです。新しいデジタルキャンペーンを展開する際や、新市場への進出を検討する際、インフラの制約を気にすることなく、即座にシステムを拡張して実験を行うことができます。また、システムを100%クラウド化することで、セキュリティとレジリエンス(回復力)も向上しました。これにより、従業員は日々のシステムトラブル対応から解放され、ブランドを成長させるためのクリエイティブな業務に集中できるようになったのです。
HEINEKEN(ハイネケン):標準化と柔軟性の両立
ビール大手のハイネケンは、世界各国で展開する拠点の独自性を尊重しつつ、グローバル共通の「背骨」を作る必要がありました。彼らがIBMと共に進めたのは、ハイブリッドクラウドを活用した「クリーンコア」戦略です。
中核となるERPは極めてシンプル(クリーン)に保ち、拠点ごとに異なるニーズや最新の機能は、周辺の「ベストオブブリード(各分野で最適な製品)」なツールをAPIで接続することで対応しました。さらに、システムの構築や展開を自動化する仕組みを取り入れ、複数拠点への導入速度を劇的に高めました。この「標準化されたコアと、柔軟に差し替え可能な周辺」の組み合わせにより、データの使いやすさとビジネスの俊敏性を同時に実現しています。
成功事例から抽出される「刷新の型」
これら3社の事例には、共通する成功のパターンが見て取れます。これから刷新を目指す企業が参考にすべき「型」は、以下の5点に集約されます。
- コアは「軽く・標準で」:基幹部分には手を加えず、ベンダーが提供する標準機能をそのまま使う(Fit to Standard)。
- 周辺は「APIで差し替え可能」に:変化が激しい機能は外部サービスを使い、いつでも入れ替えられる柔軟性を確保する。
- データを使える形で統合:分析やAI活用を前提に、データが部門を越えてシームレスに流れる仕組みを作る。
- 自動化で運用を「薄く」する:人の手による作業を徹底的に排除し、IT部門の負荷を成長領域へシフトさせる。
- 浮いた資源を「成長」へ:コスト削減だけで終わらせず、生まれた時間と予算を新しい価値創造へ投資する。
失敗を避けるための「落とし穴」と回避策
一方で、多くの企業が陥りがちな落とし穴も存在します。最も多い失敗は、刷新のプロセスで「現場の要望をすべて叶えようとして、結局またカスタマイズだらけのシステムを作ってしまう」ことです。これを防ぐには、経営層が「業務をシステムに合わせる」という強い意志を示す必要があります。
また、データ移行の難易度を過小評価することも危険です。古いシステムの不正確なデータをそのまま移すと、新しいシステムでも同じ問題が再発します。さらに、ROI(投資対効果)を「ITコストの削減」という狭い視点だけで捉えると、プロジェクトの真の価値が見えにくくなります。「この刷新によって、どれだけビジネスの意思決定が速まり、どれだけ新しい挑戦ができるようになるか」という経営視点での目標設定が不可欠です。
基幹システム刷新を「成長への投資」に

基幹システムの刷新は、単なる古い設備の買い替えではありません。それは、企業が抱える技術的負債を解消し、成長速度を劇的に高めるための「制約の解除」です。市場環境が激変する中で、従来の硬直化したシステムを維持し続けることは、機会損失という名の大きなリスクを背負い続けることに他なりません。
刷新のタイミングを検討する際、サポート期限などの「外部からの要請」を待つのではなく、自社の成長戦略から逆算して「今、何をすべきか」を判断することが求められます。最新のクラウド技術とAPIを駆使した「Composable」なシステム構造を採用することで、変化に柔軟に対応できる、攻めの経営基盤を構築することが可能になります。
成功しているグローバル企業の事例が示しているのは、「効率化を徹底した先に、真の成長投資が生まれる」という明確な順序です。システム刷新を通じて業務の無駄を削ぎ落とし、そこで生まれたリソースを顧客体験の向上や新事業の創出に振り向ける。このサイクルこそが、デジタル時代の勝者に共通する戦略です。
貴社の基幹システム刷新に向けたロードマップの策定をお手伝いすることも可能です。まずは、現状のシステムがどの程度「成長の足かせ」になっているか、可視化することから始めてみてはいかがでしょうか。