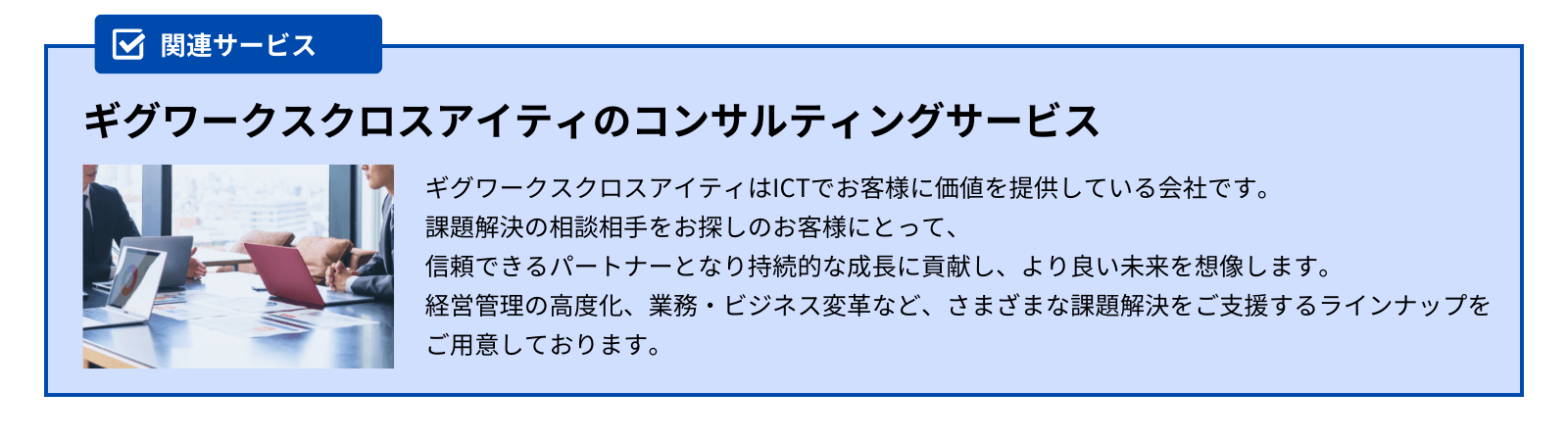新しい商品をつくるとき、最初に考えるべきなのは「どんな技術を使うか」ではありません。
本当に重要なのは、顧客の「困った」をどれだけ深く理解できるかという点です。
どんなに優れた技術でも、誰も困っていない問題を解いても意味がありません。
逆に、日常のちょっとした不便を正確にとらえられれば、自然と売れる仕組みが生まれます。
本記事では、課題発見の考え方から具体的な調査手法、そしてJTBD(ジョブ・トゥ・ビー・ダン)の活用までを一貫して解説します。
顧客視点で「価値の種」を見つけたい開発担当者や企画者のために、すぐ実践できるアプローチを紹介します。
【関連記事】口下手でも大丈夫?顧客の信頼を得る営業の本質とは
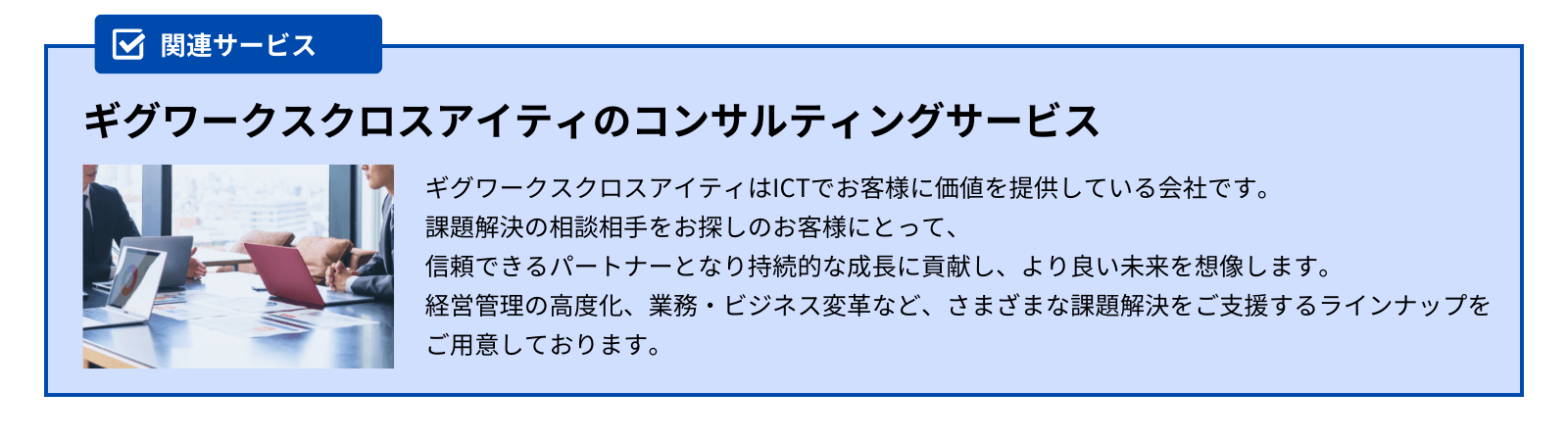
なぜ顧客の「困った」を探すことが大切なのか
商品開発を成功させる最大の要因は、技術の優秀さではなく、「顧客の困りごと」を正確に見抜く力です。
どれほど高性能な技術を使っても、誰も困っていない問題を解こうとすれば、市場は動きません。
一方で、顧客が日常で感じている小さな不便を的確にとらえられれば、売れる仕組みは自然とでき上がります。
ここでは、「課題発見」がなぜ重要なのか、そしてそれを実践的に高める方法を整理して紹介します。
技術ではなく“課題設定力”が競争力を生む
多くのチームは「どんな技術を使うか」から企画を始めがちです。
しかし、そこで生まれるのは多くの場合「技術主導の商品」です。
技術はあくまで手段に過ぎず、価値を生むのは「誰の」「どんな不便」を解消するかという問いの精度です。
優れた課題設定は、開発の方向性を定める“羅針盤”になります。
一方で、曖昧な課題設定のまま開発を続けてしまうと、「良いのに売れない」「コストばかり増える」といった結果を招きがちです。
課題発見の3つの実践ステップ
課題発見はセンスではなく、再現可能なプロセスとして体系化できます。
次の3ステップを回すことで、誰でも発見の精度を高めることができます。
- 観察する:顧客が実際に商品やサービスを使う場面を観察し、言語化されていない“不便”を探ります。ここでは「使っていない瞬間」にも目を向けることがポイントです。
- なぜ?を掘る:「なぜそうなるのか」を繰り返し、本質的な原因を突き止めます。表面的な不満の裏にこそ、本当の課題が隠れています。
- 検証する:仮説を立て、試作品やモックを通じて顧客の反応を確かめます。このサイクルを早く回すほど、課題の解像度は上がります。
適切な「課題の粒度」を見極める
課題発見でよく起きる失敗は、問題設定のスケールを誤ることです。
曖昧すぎると方向が定まらず、細かすぎると手応えを失います。
たとえば、次のような例です。
- 大きすぎる課題:「家事の負担を減らしたい」
- 適切な課題:「掃除機を出し入れするのが面倒」
後者のほうが具体的で、設計や検証のイメージが描きやすくなります。
課題を「行動単位」まで分解できる力が、開発の方向と質を決めます。
課題発見がもたらす3つの効果
1. 売れる土台をつくる
顧客が「これがないと困る」と感じる課題にフォーカスすることで、自然と購入動機が生まれます。
“小さな痛み”がビジネスの種になります。
2. 差別化を実現する
技術や機能は真似されても、どんな課題をどう捉えるかは真似できません。
誰も気づいていない不満を掘り当てることが、競合との差を生みます。
3. ムダを減らす
解くべき課題が明確になれば、「やらないこと」もはっきりします。
その結果、開発の時間とコストを最適化できます。
ケーススタディ:掃除機メーカーの気づき
ある家電メーカーは当初、競合よりも「吸引力の強さ」で勝負していました。
社内では「性能で上回れば市場を取れる」という意識が根強く、開発チームも改良を重ね、吸引力の数値をいかに上げるかに注力していました。
しかし販売が伸び悩んだため、チームはその理由を明らかにするためにユーザー宅で行動観察を行いました。
休日の午後、一般家庭のリビングや廊下、和室など、実際の生活空間を訪ね、掃除機の使い方や使用後の動作を丁寧に記録しました。
その結果、意外な“非利用時の課題”が見えてきました。
多くの顧客が「掃除機をしまう場所がない」と感じており、掃除を終えたあと、部屋の隅や家具の裏などに一時的に立てかけている様子が見られたのです。
収納スペースが限られた住宅環境では、性能よりも「置きやすさ」や「取り出しやすさ」が快適さを左右していることが明らかになりました。
この発見をきっかけに、同社は“スリム設計型”掃除機の開発に舵を切りました。
狭い空間にも収まる細身のフォルムや、ワンアクションで取り出せるスタンド設計など、掃除しない時間の不便を解消する仕様が導入されました。
技術が課題を生むという視点
一方で、技術革新によって新しい課題が生まれることもあります。
たとえば生成AIの普及によって、「誰でも作れるようになった」一方で、“アウトプットを選ぶ難しさ”という新たな不便が生じました。
このように、課題と技術は常に相互に影響し合う関係にあります。
技術の進化が生む“迷い”を読み取れる企業ほど、次の市場を先取りできます。
課題発見とは、顧客の声を集めることにとどまらず、「自分たちの前提を問い直すプロセス」です。
顧客がどんな不便を感じているのかだけでなく、「なぜそう感じるのかという構造」に目を向けることで、発想の質が変わり、開発の方向性も確実に変わります。
どうやって顧客の「困った」を見つける?

顧客の「困った」を見つけることの重要性は、多くの企業が理解しています。
しかし、実際にどう探せばいいのかとなると、手が止まってしまうケースも少なくありません。
「何が不便ですか?」と尋ねても、顧客自身が本当の課題を言葉にできていない場合が多いのです。
だからこそ、定性調査と定量調査を組み合わせて検証することが欠かせません。
顧客の声や数字を個別に見るのではなく、「理由」と「規模」をセットで捉えること。
この視点が、課題発見の精度を高める鍵になります。
定性調査:理由の奥を掘り下げる「なぜの連鎖」
定性調査の目的は、表面的な発言の背後にある行動の文脈と感情の理由を理解することです。
インタビューや観察を通じて「なぜそう感じるのか」「どんな状況で起きるのか」を掘り下げれば、顧客の奥に潜む“痛み”が見えてきます。
その際に役立つのが、定番の「5回のなぜ」です。
質問テンプレート
- 何に不満を感じますか?
- なぜそう感じるのですか?
- それによってどんな困りごとが生じますか?
- それが解決したらどんな良いことがありますか?
- なぜそれが今、重要だと思いますか?
この質問の連鎖によって、顧客自身も気づいていなかった本質的な課題にたどり着けます。
たとえばある家電メーカーの調査では、「掃除機が重い」という声の裏に、「狭い場所で動かしづらい」「物をどけるのが手間」といった行動上の障害が隠れていました。
顧客の「言葉」ではなく、「動きの止まる瞬間」に注目したことで、真の課題を見つけました。
実際の利用現場を観察するエスノグラフィ調査も有効です。
現場で見られる“ため息”や“手戻り”、“沈黙”など、言葉にならない動きの中にこそ核心が潜んでいます。
観察とは、数字では拾えない「なぜこの瞬間に迷ったのか」を明らかにする行為です。
定量調査:規模と優先度を見極める
一方、定量調査はどの課題がどれほど多くの人に影響しているのかを数値で把握するための手法です。
アンケートやログデータ、問い合わせ履歴などを分析し、課題の深刻度と発生頻度を定量化すれば、開発リソースをより効果的に配分できます。
課題評価マトリクス(深刻度×発生頻度)
課題を評価する際は、「どれだけ困っているか(深刻度)」と「どれだけ多くの人が困っているか(発生頻度)」の二つを組み合わせて考えます。
この2軸で整理すると、おおまかに次の3つの領域に分けられます。
- 深刻度も発生頻度も高い課題
→ 解決できれば多くの人に大きな効果をもたらす、最優先で取り組むべきテーマです。 - 深刻度も発生頻度も低い課題
→ 影響が限定的なため、開発リソースを大きく割く必要はありません。後回しでも問題ありません。 - 深刻度は高いが、発生頻度が低い課題
→ 一見ニッチに見えますが、将来大きな市場に育つ可能性を秘めた“芽”として注目すべき領域です。
また、コールセンターの問い合わせ履歴や、ウェブサイトの離脱ログなども重要なデータ源です。
たとえば、離脱率の高いページを特定し、その理由を定性調査で確認する。
このように、数字(定量)と声(定性)を行き来させるプロセスこそが、単なる統計を“生きた発見”へと変えていきます。
定量データを“生の声化”する
データは現象を示しますが、その原因までは教えてくれません。
数値だけを見ても、「何が起きているのか」までしかわかりません。
だからこそ、データを「生の声」と照らし合わせて解釈する力が求められます。
たとえば、離脱データのピークが注文画面で発生している場合、観察によって「入力が煩雑」「エラー時の再入力が面倒」といった行動上の要因を結びつけて考えます。
このように「数字×体験」で課題を定義するアプローチは、今のリサーチには欠かせません。
よくある落とし穴とその回避策
課題発見のプロセスでは、次の2つの誤解が特によく見られます。
- 「顧客の言った通りに作ればいい」
→ 発言の多くは“解決策の提案”であり、本質的な課題ではありません。
真に聞くべきは「どんな状況で何に困っているのか」です。チームで発言の背景を整理し、意味を共有することが重要です。 - 「データを見れば課題がわかる」
→ データは答えではなく、あくまで判断の素材です。数値をどう解釈し、どんな意味づけをするかという現場起点の洞察力が欠けていては、意味を成しません。
定性と定量の「行き来」で課題を立体化する
定性と定量のどちらが優れているかという話ではありません。
優れた企業は、この2つを行き来しながら活用しています。
まず定性調査で仮説を立て、定量調査で影響の大きさを確かめます。
あるいは、定量データで異常値を見つけ、観察でその背景を掘り下げます。
この往復によって「理由と規模の可視化」が進み、課題発見の精度が大きく高まります。
顧客の声は出発点にすぎません。
真に価値のある発見は、データや発言の背景にある構造を見抜くことから始まります。
JTBDの視点で考える
前章で見つけた「顧客の困りごと」を、どのように価値へ変えていくか。
その答えを導くヒントとなるのが、JTBD(ジョブ・トゥ・ビー・ダン)の視点です。
顧客が求めているのは商品そのものではなく、それを使って実現したい結果(Job)です。
たとえば「ドリル」を買う人の目的は「穴を開けること」ではなく、「壁に棚を取り付けたい」という結果を手に入れることです。
この発想に立つことで、既存商品の改良にとどまらず、新しい価値提案を見いだすことができます。
顧客は「手段」ではなく「結果」を買っている
多くの開発チームは、顧客の要望を機能に変換しようとします。
「軽くしてほしい」「使いやすくしてほしい」といった声に応えて改良を重ねることも重要です。
ただし、視点が「手段」にとどまると、差別化の限界が訪れます。
JTBDの本質は、「顧客がその機能を通じて何を達成したいのか」を問うことにあります。
言い換えれば、「どんな成果を得たいのか」「どんな前進を望んでいるのか」を見立てる思考法です。
ドリルの例でいえば、「穴を開けたい」ではなく「棚を取りつけて部屋を整えたい」が真のジョブです。
もし“穴を開けない棚の取りつけ方”を提案できれば、顧客の目的をより簡単に達成できます。
ジョブ志向の発想は、既存市場の外側で新たな価値を生み出す起点となります。
【参考】ジョブ理論とは?
JTBDに潜む3つの層を見抜く
ジョブを理解するには、単なる作業目的にとどまらず、顧客の心理や社会的背景まで視野に入れる必要があります。
多くの企業が活用しているのが、「ジョブの三層構造」という考え方です。
- 機能的ジョブ(Functional Job)
顧客が実際に成し遂げたいこと。例:「棚を取り付けたい」「手早く夕食を準備したい」 - 感情的ジョブ(Emotional Job)
それを通じて得たい気分や心の状態。例:「部屋を整えて安心したい」「家族に喜ばれたい」 - 社会的ジョブ(Social Job)
他者との関係に関わる願望。例:「センスのいい暮らしを見せたい」「DIYが得意だと思われたい」
優れた製品ほど、この3層を同時に満たしています。
たとえばスターバックスは、「コーヒーを買う」という行為だけでなく、
「落ち着きたい」(感情的ジョブ)や「自分らしく過ごしたい」(社会的ジョブ)といったニーズを満たす場を提供しています。
ジョブの深度を理解することで、単なる機能価値を超えた体験価値が生まれます。
「誰が・どんな状況で・なぜ」採用するのか
JTBDを具体的に運用するには、顧客像と利用シーンの文脈を組み合わせて考えることが重要です。
つまり、ジョブは「誰が・どんな状況で・なぜ」その商品を選ぶのか、という3つの視点で捉えます。
例えば同じコーヒーでも、コンテクストが変われば顧客のジョブは変わります。
- 通勤途中の人は「集中力を切り替えたい」
- 昼休みに同僚と飲む人は「雑談を楽しみたい」
- 夕方ひとりで飲む人は「一人の時間を整えたい」
この視点をもつことで、自社商品の本当の役割を再定義できます。
違和感こそ新しいジョブのサイン
顧客自身が「不便」と気づいていない場面に次のビジネスチャンスがあります。
日常で見過ごされがちな小さな違和感やズレを観察することこそ、ジョブ発見の入り口です。
ある食材メーカーでは、共働き家庭のキッチンを観察した際に、「冷蔵庫を開けて何を作るか悩む時間」が意外に長いことに気づきました。
そこから、「今日の食材で何を作ればいいかすぐにわかる」アプリを開発。
結果として、“食材の視覚管理”という新たなジョブを満たすサービスへと発展させました。
このように、違和感とは顧客の理想的な状態(こうありたい)と現実の行動との間にある摩擦です。
その摩擦を特定し、解消する方法を設計することで、まだ誰も手をつけていない領域が立ち上がります。
JTBDを使うときに陥りがちな誤解
JTBDは広く知られる一方で、次のような誤解が生じやすい概念です。
- 「ジョブ=顧客のタスク」
→ 実際のジョブは「進捗」や「成果」であり、行為そのものではありません。 - 「ジョブ=特定の人物像」
→ JTBDはペルソナ分析ではなく、「固定された誰か」ではなく「状況と動機」に焦点を当てる思考法です。
この2点を踏まえて使わないと、ジョブは単なる“マーケティング用語”で終わってしまいます。
大切なのは、顧客の行動から「なぜその進捗を望むのか」を導くことです。
JTBDの目的は、顧客を分類したり発言を整理したりすることではありません。
それは、人が何かを達成しようとするときの変化の構造を読み取る思考法です。
顧客が求めているのは「製品の性能」ではなく、自分の行動がどれだけ楽に、確実に進めるかという点です。
企業は、その進捗を最短で実現できる手段を提案する存在であることが求められます。
小さな違和感を拾い、それを「未充足のジョブ」として再定義します。
この思考を組み込むことで、商品開発は改良の段階から創造の段階へと発展します。
「ヒットの種」は観察から

商品開発の出発点は、顧客の立場に立って考えることです。
顧客の不満や違和感に共感し、その背景をデータと観察で探ることが、成果を生み出す第一歩です。
技術や機能よりも前に、「本当に誰の、どんな進捗を助けたいのか」を問う姿勢が、強い企画を生み出す原動力になります。
ここからすぐ実践できる行動を2つ紹介します。
- 日常観察のすすめ:「最近、時間を無駄にしていると感じる場面は?」を1日3つ記録する。
- 会議での話題提案:チーム全員で「最近聞いた“ちょっとした不満”」を1人1つ共有する。
小さな観察と会話の積み重ねが、次の“ヒットの種”を見つける一番の近道になります。