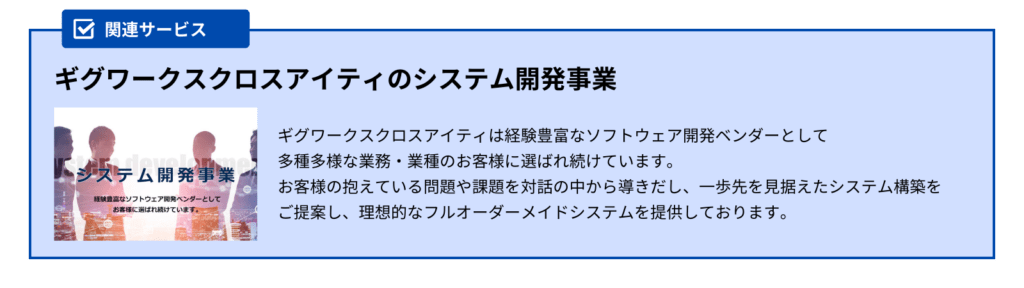本プロジェクトは、電気設備業界で全国規模のBtoB事業を展開する企業が抱えていた「複雑化する問い合わせ対応」や「分散した顧客情報管理」といった課題を克服するため、デジタル化と現場改革を両軸で推進した取り組みです。
コールセンター業務の再構築から基幹システムとの連携、そして全社データの統合まで、ステップ的な導入を通じて現場に定着するシステムと業務改善の両立を実現しました。
その全体像と私たちの取り組みを、3つのフェーズに分けて紹介します。
【関連記事】次の10年を支えるシステム構築:基幹システム刷新プロジェクトの記録
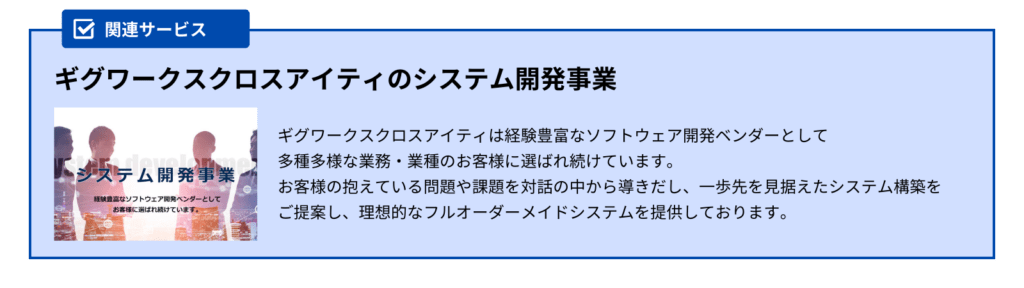
フェーズ1:プロジェクトの開始まで
老朽化した基幹システムと複雑化した問い合わせ対応体制に課題を抱えていた電気設備関連企業。
本プロジェクトでは、現場の実務に即したシステム再構築を軸に、問い合わせ対応の迅速化・情報の一元管理・ナレッジ共有の最適化を実現しました。
以下では、その導入過程とプロジェクトチームの取り組みを紹介します。
顧客概要
今回支援を行ったのは、電気設備の卸売およびエネルギーコンサルティング事業を展開するBtoB企業です。再生可能エネルギー関連案件を積極的に拡大しており、社員は約900名。営業やコールセンター、技術支援、物流、管理部門が複数拠点に分散しながら事業を推進しています。
2011年に構築されたオンプレミスの基幹システム(.NET Framework 4.0+SQL Server)は老朽化が進み、特にコンタクトセンター業務では、問い合わせチャネルの分散により対応履歴を一元管理できない状況でした。これにより、問い合わせの重複対応や応答遅延が頻発し、ナレッジ共有不足が重なって顧客満足度低下のリスクが顕在化していました。
デコールCC.CRMとは
こうした課題に対し、当社が提供するコールセンター向けCRMシステム「デコールCC.CRM」が採用されました。
20年以上の実績を持つ本製品は、AI技術による対応内容分析機能を備え、電話・メール・チャット・SMS・FAXなど多様な通信チャネルを一括管理できる設計となっています。これにより、運用効率の大幅な向上が期待できます。
特に、既存電話設備やIP-PBXとシームレスに連携可能なマルチベンダーCTI機能を搭載しており、着信時の顧客情報自動表示や通話録音の自動紐付けを実現。応対品質の向上と記録業務の省力化を両立します。
また、複数拠点を統合的に管理できるマルチテナント機能により、運用コスト削減と高い柔軟性を提供します。
顧客は他社製品も比較検討する中で、基幹システムとのAPI連携によって、社内に分散していた顧客情報や受注・請求データを一画面で統合表示できる点を高く評価。情報整合性の向上と迅速な対応を可能にする機能が、導入決定の決め手となりました。
顧客との初回ミーティング
2024年3月、東京本社で実施された初回ミーティングには、顧客側のシステム部門責任者とコールセンター運営責任者を中心に、当社から技術・営業・導入支援の各担当が参加しました。
冒頭では、顧客から現場の課題が率直に共有され、「問い合わせ対応に手を取られ、ナレッジ活用が追いつかない」といった具体的な声も上がりました。会場には緊張感と同時に、“現場をどう変えていくか”を前向きに検討する活気が感じられました。
当社は、これまでの導入実績や類似事例をもとに、問い合わせチャネルの一元管理と再発問い合わせ削減の重要性をプレゼンテーションで提示。デモ画面を活用して応答履歴統合の効果を説明すると、顧客側からは連携方式や導入スケジュールに関する具体的な質問が相次ぎ、議論は活発に進行しました。
この議論を通じて、単なる機能比較ではなく「業務課題の解決」という共通目標を両者が共有できたことが、本プロジェクトの大きな転機となりました。
ミーティングを終え、プロジェクト責任者は「単なるシステム導入ではなく、現場の実態に即した提案ができたと感じた」と振り返っています。全員が次のステップに向けた確かな手応えを掴む好スタートとなりました。
要件定義
初回ミーティングを経て、プロジェクトは実質的な設計段階である要件定義フェーズに入りました。
会議室のホワイトボードには業務フローや問い合わせパターンがびっしりと描かれ、「ここが詰まる」「この分類では対応が追いつかない」といった具体的な課題を検討しました。
このフェーズでは、顧客の日常業務に即した詳細調査を実施し、問い合わせカテゴリ整理やFAQ構築、対応品質向上をワンパッケージにまとめた実用的な要件定義を策定しました。
重要なポイントは以下の通りです。
- 問い合わせ種別の明確化:オペレーター負担を軽減し、対応品質の向上を図るため、問い合わせのカテゴリと対応フローを整理しました。
- 音声認識技術の導入:通話内容をリアルタイムに要約し、自動で分類タグを付与することで、対応内容の把握と分析を容易にしました。
- 社内ナレッジベースとの連携:FAQリコメンド機能を即時反映し、オペレーターが迅速かつ的確に回答できる体制を整えました。
- 基幹システムとのハイブリッド連携設計:API連携と夜間バッチ処理の両方を組み合わせ、システム間のデータ整合性と処理タイミングを最適化しました。
会議のたびに顧客側の担当者も意見を持ち寄り、「単に新しくするのではなく、今より確実に楽になる」業務像を共有しました。
プロジェクトチームの編成と役割分担
要件定義を経て、実装に向けた体制づくりが始まりました。
複数の専門領域を横断するプロジェクトであったため、チームビルディングの段階から活発な意見交換が行われ、各メンバーが自らの専門性をどう活かすかを真剣に議論しました。
2024年3月上旬、当社からは技術・営業・インフラ・API開発など多様な分野の専門家12名が参画。顧客側担当6名と密接に連携し、4週間スプリントによる段階的リリースを軸にスムーズな進捗管理を行いました。主な確認ポイントは以下の通りです。
- 多様な部門構成と業務フローの把握:顧客の各部門および業務フローの全体像を詳細に理解しました。
- 問い合わせ管理・データ共有の課題明確化:現状の課題点を具体的に洗い出しました。
- 役割分担・責任範囲の明確化:各メンバーの役割と責任を定義し、効率的なチーム運営を図りました。
- 短期スプリントによる進捗管理:品質とスケジュールを両立する管理方法を採用しました。
日々の打ち合わせでは、課題を「誰が」「いつまでに」「どう解決するか」を具体的に定め、全員が同じ目標を共有。
プロジェクトマネージャー主導のもと、目的と方針の共有を徹底し、並行開発と運用の両立を現実的な計画へと落とし込みました。
次章では、これらの要件をもとに進めたシステム開発の具体的な取り組みや課題克服のプロセス、導入効果の検証について詳しく紹介します。

フェーズ2:デコールCC.CRMの導入

コールセンター改革の第一段階として、基幹システムと連携した顧客対応基盤の再構築を進めました。
本フェーズでは、「デコールCC.CRM」を導入し、分散していた問い合わせ履歴やナレッジを統合。
短期間での運用定着を目指し、現場主体のトレーニングと並行検証を重ねながら、顧客対応品質と生産性の両立を実現しました。
現状の課題と目的
コールセンター業務の効率化を目的とした本フェーズでは、顧客が長年抱えていた対応記録の分散・応答遅延・ナレッジ共有不足の課題に正面から取り組みました。
近年、電力契約や省エネ設備、補助金制度に関する問い合わせが急増し、電話・メール・Webフォームなど複数チャネルに履歴が分散。記録検索や過去履歴の確認に時間を取られ、対応のばらつきが目立っていました。
特に、再生可能エネルギー導入に伴う補助金申請や機器換装計画などでは、顧客対応ナレッジが共有されず、同様の問い合わせが繰り返される「再発対応」が多発していました。
そこで、短期間での業務基盤統一と生産性向上を目的に、「デコールCC.CRM」を中核としたコールセンター刷新プロジェクトを始動しました。
プロジェクト責任者はこう語ります。
「単に新しいツールを導入するのではなく、現場の動線全体を整えることが何より大事でした。」
作業の進め方と重点ポイント
導入フェーズでは、4か月という短期間で実運用レベルまで仕上げることを目標に、コールセンター業務の実態に即した設定・検証を進めました。主な取り組み内容と重点ポイントは以下の通りです。
- 問い合わせカテゴリの整理と要件定義
電力契約、機器保守、再エネ補助金対応を中心に、主要カテゴリを再編。対応手順を標準化し、重複対応を防ぐ仕組みを整えました。 - 問い合わせ履歴の一元化とFAQリコメンド設定
顧客・案件マスタをCRM環境に統合し、FAQを自動提示する機能を追加。問い合わせ対応中に関連過去事例を即参照できるようにしました。 - CTI連携による着信情報自動ポップアップ
PBXとCRMを接続し、着信時に顧客情報と対応履歴が即座に画面表示されるようにしました。顧客識別から聞き取り開始までの時間を大幅短縮しました。 - 音声認識技術の導入
デコール独自の音声認識エンジンを採用。オペレーターの通話内容をリアルタイムで要約し、内容タグを自動付与。タグ情報はCRMに即時反映され、FAQ・ナレッジ共有の精度を高めました。 - 管理者ダッシュボードの拡張
問い合わせ種別や応答時間を自動集計できるダッシュボードを追加。改善状況をリアルタイムで把握できるようにしました。
並行運用の開始とトレーニング
本番切替に先立ち、1か月間の並行運用期間を設け、旧システムとCRM双方の応答履歴を詳細に比較しました。
音声認識結果の精度、タグ付け内容、FAQ引用率、平均対応時間などの指標を継続的にモニタリングし、改善の余地を継続的に分析しました。
併せて、オペレーターやSV(スーパーバイザー)から現場の意見を収集し、実際の運用状況に合わせて設定チューニングを繰り返しました。
教育面では、「新人が3日で実務対応を始められる」運用マニュアルの整備を目標に、操作手順書を全面的に刷新しました。
研修会では実際の通話データを使用したケーススタディを実施し、参加者からは
「このFAQは、自分たちの手で育てていくものだという意識が芽生えた」
といった声も聞かれました。
また、段階的なシステム切替を採用することで、障害やデータ遅延の発生リスクを最小限に抑制。最終段階では全拠点への展開を完了し、システムの安定稼働を確認しました。
データ移行の計画と実施
データ移行は2段階構成で実施しました。
第1回の試行移行では、過去12か月分の問い合わせ・契約データを投入し、検索速度やレスポンス性能を検証しました。
第2回の本番移行では、最新履歴を含む全データを統合し、API経由で基幹システムと同期。重複や欠損データを自動検出する仕組みを導入し、整合性を確実に担保しました。
開発担当者はこの移行作業を以下のように振り返ります。
「旧データの整合性を保ちながら、新環境へスムーズに統合できたことが、成功の大きな要因でした」
導入効果の実績
CRM本稼働後、コールセンターでは明確な成果が確認されました。
- 平均対応記録時間が約2分から40秒へ短縮
- 音声認識による自動分類精度91%達成
- 対応内容の再利用率が30%向上し、FAQ参照件数が増加
- 問い合わせ増加にも関わらずオペレーター増員なしで完了率95%超を維持
オペレーターからは、
「記録作業に追われなくなり、次の顧客対応に集中できるようになった」
という声が挙がり、現場満足度の向上も顕著でした。
管理者層からは、
「履歴が整理され、トラブル発生時の原因分析や横展開がしやすくなった」
との評価がありました。データ集約によって分析指標が明確化し、全体最適を意識した運営判断が可能になりました。
成果と今後への展開
本フェーズの最大の成果は、「システム導入と業務の定着を同時に実現したこと」にあります。
単なるツールの刷新ではなく、ナレッジを共有し業務を更新していく運用文化の形成が確認できた点で、組織の成熟を象徴する段階となりました。
プロジェクトマネージャーは最後にこう振り返っています。
「最短のスケジュールで現場が自走できるレベルまで落とし込めた。今回の知見は、この先のシステム開発フェーズにつながる財産になりました。」
次章では、この導入成果を踏まえ、デコールCC.CRMを核とした業務最適化フェーズについて詳しく紹介します。
フェーズ3:デコールCC.CRMと基幹システムの連携
コールセンター基盤の再構築を終えた後、次の重点テーマは基幹システム(ERP)との連携強化でした。
本フェーズでは、営業活動・受注処理・請求管理などの業務をCRMとERPで統合し、組織全体がデータを共有できる基盤を短期間で整備しました。
営業・コンサル・経理の各部門をリアルタイムで連動させ、顧客対応から請求完了までを一貫して管理できる体制の確立を目指しました。
課題と狙い
各部門が個別のシステムで運用していたため、顧客・契約・見積情報の重複や漏れが頻発していました。
営業部では、CRMに登録された見積データをERPへ転記する手間が発生し、経理部ではデータ不整合の確認に時間を要していました。
この状況を受け、プロジェクトでは短期間での連携フレーム構築と部門横断のデータ同期を目標に掲げました。
リーダーは当時をこう振り返ります。
「CRMに閉じていた情報をERPとつなげることで、初めて“業務全体が動く”仕組みを実感できました。 効果を実感するためには欠かせないフェーズだと認識していました」
主な作業内容と採用した技術
約5か月という限られた期間で完了させるため、開発チームは設計段階からプロトタイプを作成し、API中心の柔軟な構成へと移行しました。
主な作業と実装技術は以下の通りです。
- 連携設計
JSONスキーマを統一し、API連携と夜間バッチ処理を併用するハイブリッド構成を採用。
即時同期が必要な項目はAPIで処理し、集計処理は夜間バッチへ移行しました。 - 開発技術基盤
Java(Spring Boot 3.0)を中心としたAPIサーバを構築。
ORMにはHibernate/JPAを採用し、バッチ処理はSpring Batchで実装しました。
認証はOAuth 2.0+JWT方式を用いてセキュリティを強化しました。
また、画面側にはReact+TypeScriptを採用し、CRMとERP双方の操作性と視認性を向上させました。 - CRM→ERP間連携の実装
顧客・案件・請求データを双方向でリアルタイム同期。
ERPからCRMの対応履歴を直接参照できる履歴参照APIを新たに実装し、部門間での情報共有を円滑にしました。 - ERP機能改修
ERPの顧客管理画面に「問い合わせ履歴タブ」と「案件ステータス照会」機能を追加。
CRM連携により、営業・経理・コンサルが同一画面で最新状況を確認できるようになりました。 - 並行運用と安定化
旧環境との整合性を確認するため、1か月間の並行稼働期間を設定。
本稼働後はバッチ監視と障害復旧訓練を実施し、エラー発生時のリカバリ手順を明文化しました。
成果と運用効果
システム本稼働後は、営業から経理までの情報共有がリアルタイムで実現しました。
- 顧客・契約データの統合により、手入力業務を35%削減
- コンサル提案から請求処理までの平均リードタイムを2日短縮
- 各部門間での情報不整合がほぼ解消し、進行状況の認識が統一
オペレーションチームからは、
「請求作業前に営業情報を再確認する手間がなくなり、月末処理が一気に楽になった」
という声も聞かれました。
経理責任者も次のように語ります。
「これまで別々だった“顧客状況”と“売上処理”が同じ文脈で見られるようになり、 経理判断が早くなりました。」
結果として、情報の一元化が組織の業務スピードを全体的に引き上げ、
部門間での連携の質を高めることで、“データの共有”から“価値の共有”へと意識が変化しました。
このフェーズをもって、CRM導入と基幹システム連携を統合的に完了し、営業・コンサル・経理の三部門間でデータの整合性と一貫性を確立しました。
これにより、顧客対応から請求処理までの業務がシームレスにつながり、全社レベルでリアルタイムな経営データ基盤が確立しました。
プロジェクトが提供した価値と私たちが得たもの

既存基幹システムとの連携は、私たちにとって大きな挑戦でした。
しかし、この取り組みこそが、デコールCC.CRMが最大の価値を発揮するために欠かせないプロセスだったと考えています。
今回のプロジェクトでは、
- 業務の自動化による作業負荷の軽減
- 業務内容の見える化
- 分散した情報の一元化
という三つの成果を同時に実現することができました。
単なるシステム導入にとどまらず、現場の運用改善と全社的なデータ整合を両立できたことは、私たちにとって大きな収穫です。
この成果を糧に、私たちは次の挑戦へと歩みを進めていきます。